「先にかけ算? でもカッコがあると順番が変わるって本当?」
小学生の算数で意外とつまずきやすいのが、「計算の順番」のルールです。
とくにカッコ・かけ算・たし算が混ざった式では、「順番通りに読めばいい」と思ってしまう子どもも多く、間違いやすいポイントの一つ。
この記事では、四則計算の正しい順序ルールはもちろん、カッコの使い方や文章題での注意点、家庭での教え方までをわかりやすく解説します。
「なぜその順番になるのか」をしっかり理解できれば、計算ミスはぐっと減り、文章題にも強くなれます。
お子さんの「なんでこの順番なの?」という疑問に答えながら、楽しく学べる工夫を一緒に見つけていきましょう。
目次
なぜ「カッコ」の計算でつまずくの?

かっこのある計算は、子どもたちが混乱しやすい単元のひとつです。
計算の順番が変わるだけで答えが大きく変わるため、しっかりと理解していないとミスを重ねてしまいます。
「かけ算・たし算・カッコ」の順番をどう教えるかで、つまずきを減らせるかが決まります。
その理由は、「かっこは先に計算する」というルールが、普段の読み方や計算習慣とズレているからです。
左から順番に読んで計算するクセがあると、ルールを無視して間違えてしまうのです。
また、「かけ算はたし算より先」というルールも混在するため、整理できていない子はさらに混乱します。
とくに低学年のうちは、かけ算とたし算の順序を一緒に考えるだけでも難しいのに、そこに「かっこ」が加わることで負荷が増します。
以下では、つまずきやすいポイントを3つに分けて詳しく解説します。
- よくある間違いは「順番通りに読んでしまう」
- 「先にかけ算」だけでは解けない問題とは?
- 文章題でカッコを見落とすとどうなる?
よくある間違いは「順番通りに読んでしまう」
計算の問題を左から順に解こうとしてしまう子はとても多いです。
とくに「かけ算」「たし算」「カッコ」の順番が混在しているとき、式をそのまま読む感覚で進めてしまい、正しい答えにたどりつけません。
この間違いの背景には、「日本語を読むように、式も左から右へと読む」という思い込みがあります。
また、学校で習う順序を完全に理解しきる前に、複雑な式に触れると、混乱しやすくなるのです。
たし算とかけ算の違いを知っていても、順番のルールが頭に入っていなければ、正しく使い分けることはできません。
「3+4×2=14」と誤って答えるケースは典型例です。
本来はかけ算を先にするべきですが、左から順に「3+4=7」「7×2=14」と進めてしまうのです。
次の見出しでは、このようなミスが起きやすい他のケースを詳しく解説します。
「先にかけ算」だけでは解けない問題とは?
「かけ算はたし算より先」と習った子どもが、すべての計算をそのルールだけで解こうとしてしまう場面があります。
ところが、かっこが入った計算式では、その考え方だけでは正しい答えにたどり着けません。
これは、かっこの役割が「その部分を優先的に計算する」というルールだからです。
どんなにかけ算が強い計算でも、かっこ内の計算は最優先で行うという原則があります。
そのため、「先にかけ算」というルールよりも、「かっこを優先する」というルールが上位になるのです。
例えば「(3+4)×2」のような式では、「3+4=7」を先に計算し、次に「7×2=14」と進めなければなりません。
以下では、このような混乱を招きやすい問題の種類や注意点を詳しく解説します。
文章題でカッコを見落とすとどうなる?
文章題では、式の意味を正しく読み取る力が求められます。
ところが、カッコの存在に気づかずに計算してしまうと、問題文の意図とは違う式になり、まったく別の答えを出してしまうのです。
カッコは「先にまとめて考える」ための大切な記号です。
たとえば「合計を出してからかけ算をする」場面や、「差を出してからわり算をする」場面など、処理の順番を明確にする役割を持っています。
これを見落とすと、単なるたし算・かけ算のミスではなく、意味を取り違えた答えになるため、文章題での正答率が大きく下がります。
特に中学受験や学力テストでは、式を立てる段階での判断ミスが命取りになります。
次のセクションでは、カッコを見落としてしまう典型的なパターンを紹介し、その対策について詳しく解説します。
「カッコ かけ算 たし算」の順番ルールをやさしく解説

計算の順番に迷う子は多く、「かけ算を先にする」「カッコがあるときはどうするの?」と混乱しやすい場面です。
そこで大切なのは、ルールを一つずつ丁寧に整理して理解すること。
順番の基本をおさえれば、正しく計算できるようになります。
順序の考え方には段階があります。
まず、たし算・ひき算より、かけ算・わり算を先に行うというルール。
そして、カッコがある場合は最優先で計算するという原則があります。
これらを正しく覚えることで、式を読む力と計算力の両方が身につきます。
とくに複雑な式では、「どこから計算するか」を判断できる力が問われます。
以下では、それぞれのルールを以下の3つに分けて、わかりやすく解説します。
- 四則計算の順序ルール(たし算・ひき算・かけ算・わり算)
- カッコがあるときのルールは?
- カッコが二重になっているときの考え方
四則計算の順序ルール(たし算・ひき算・かけ算・わり算)
計算の順番に迷ったとき、まず覚えておきたいのが四則計算の基本ルールです。
たし算・ひき算・かけ算・わり算が混在している式では、「かけ算・わり算を先に、たし算・ひき算は後から計算する」のが原則です。
このルールは、式を正確に処理するために必要不可欠です。
もし順番を間違えると、答えが大きくズレてしまいます。
特に小学生にとっては、「左から順に計算してしまうクセ」がついていることも多いため、意識的にこのルールを練習で定着させることが大切です。
たとえば「3+4×2」のような式では、たし算よりもかけ算を先に計算して「3+8=11」とする必要があります。
以下では、四則計算の順序を守るための具体的なコツをわかりやすく紹介します。
カッコがあるときのルールは?
カッコが出てきたら、まずその中を一番先に計算するというのが大原則です。
たとえ、かけ算やわり算がカッコの外にあっても、カッコの中のたし算・ひき算を優先する必要があります。
このルールがあるのは、計算の流れを整理し、意図した順序通りに処理させるためです。
カッコは「先にまとめて計算してくださいね」という目印。
これを無視して進めると、式の意味が大きく変わってしまい、誤答の原因になります。
たとえば「(3+5)×2」は、カッコを先に計算して「8×2=16」とするのが正解です。
外側にかけ算があっても、中のたし算を先に終わらせることが重要です。
以下では、カッコがある場合の計算順をより深く解説します。
カッコが二重になっているときの考え方
二重カッコ(入れ子のカッコ)は、内側から順番に計算するのが基本ルールです。
カッコが複数あると混乱しやすいですが、焦らず「一番内側」から解きほぐすイメージで進めるとスムーズに解けます。
このルールは、計算の流れを明確にし、複雑な式でも順序を保って正確に解けるようにするために必要です。
二重カッコは、小学校高学年や中学受験レベルでよく出てくるため、早い段階で慣れておくことが大切です。
たとえば「(5+(3×2))−4」のような式では、まず内側の「3×2=6」、次に「5+6=11」、最後に「11−4=7」と計算します。以下では、二重カッコの処理手順と練習方法をくわしく解説します。
カッコのある計算を正しく解くためのステップ

カッコが含まれた計算は、順番をしっかり整理して解くことが大切です。
とくに小学生のうちは、「かけ算」「たし算」「カッコ」が混在する式に戸惑いやすいため、手順を視覚化しながら進めることが正解への近道になります。
理由は、頭の中だけで順序を整理するのが難しく、式全体を感覚で処理してしまう子が多いからです。
書き込みながら手を動かすことで、計算のルールと式の構造を自然に理解できるようになります。
たとえば「(3+5)×2」のような式で、「どこから計算すればいいのか」を自分で判断できるようになるためには、順序の見える化が効果的です。
以下では、具体的なステップや練習方法を次の3つのポイントに分けて紹介します。
- まずは計算の順序に線を引いて整理しよう
- 「かけ算→たし算」だけでは解けないときの対処法
- 間違いを防ぐ練習方法(小学生向け)
まずは計算の順序に線を引いて整理しよう
カッコ・かけ算・たし算が混ざった式を正しく解くためには、計算の順番を目で見える形にすることが大切です。
とくに慣れないうちは、計算の優先順位に沿って「どこから手をつけるか」を線で示しておくと、間違いがぐんと減ります。
これは、計算順序をあいまいなまま処理してしまうと、思い込みで進めてしまう子が多いためです。
線を引くことで頭の中の整理ができ、式の構造を視覚的に理解できるようになります。
簡単な工夫ですが、効果はとても大きいです。
たとえば「(4+3)×2−1」の式では、先にカッコの中、次にかけ算、最後にひき算という順で線を引くと、計算の道筋が明確になります。
以下では、線の引き方や活用例について詳しく解説します。
「かけ算→たし算」だけでは解けないときの対処法
計算の順番は「かけ算が先、たし算は後」と覚えていても、それだけでは正解できない問題があるのが現実です。
特に「カッコ」が入ると、優先順位の考え方が変わるため、単純なルールだけでは対応しきれません。
こうした混乱を防ぐには、「かけ算が先」ではなく、“カッコが最優先”というルールを最初に頭に入れておくことが大切です。
そして式を見たときには、まずどこにカッコがあるかを確認し、そこから順番を整理するクセをつけましょう。
たとえば「3+(4×2)」は、かけ算を先にすべきですが、「(3+4)×2」ならたし算が先です。このように、式の形を読み取る力が必要です。
以下では、順番に頼りすぎないための考え方と練習の工夫を紹介します。
間違いを防ぐ練習方法(小学生向け)
カッコ・かけ算・たし算の順番でつまずかないためには、「式を読む力」を育てる練習が何よりも効果的です。
解き方を丸暗記するのではなく、「なぜこの順番で解くのか」を意識するような声かけや問題演習が大切になります。
その理由は、間違いの多くが「順序を理解していない」ことから生まれるからです。
特に小学生は、一度覚えたルールをすべての式に当てはめてしまいがちなので、場面に応じて判断する力を育てる必要があります。
効果的な練習方法としては、次のような取り組みがあります。
- 計算の順番に色鉛筆で印をつけながら解く
- 式のどこから計算するかを先に口で説明させる
- カッコの意味を問う○×クイズで遊び感覚を取り入れる
以下で、これらの方法をさらに詳しく紹介します。
家庭でできる!カッコつき計算の教え方とコツ

カッコのある計算は、ちょっとした工夫で家庭でも楽しく学べます。
ポイントは、「順番のルールを覚えさせる」のではなく、日常の中で自然と“カッコの役割”を感じ取らせることです。
理解が深まると、計算の順番にも自信が持てるようになります。
その理由は、頭の中だけでルールを整理しようとすると混乱しやすいからです。
とくに小学生は、「なぜこの順番になるのか?」を体感しながら学ぶ方が定着しやすく、学習がスムーズに進みます。
家庭では、食材の数やお手伝いの順番など、身近な体験にカッコの意味を結びつけるのが効果的です。
以下では、次の3つのコツに分けて、カッコつき計算を無理なく教える方法を紹介します。
- 日常生活の中で「カッコ」をイメージさせる
- 「式を読む力」を育てる声かけ例
- 市販教材・アプリを使った反復練習法
日常生活の中で「カッコ」をイメージさせる
カッコのある計算に慣れていない子どもには、まず「カッコって何のためにあるの?」という感覚を、身近な体験で伝えることが効果的です。
遊びや会話の中にカッコの考え方を取り入れることで、計算の順番も自然と理解しやすくなります。
理由は、抽象的なルールよりも、目の前の出来事を通じて「先にまとめて考える」感覚をつかむ方が、記憶にも残りやすいからです。
特に小学生は、実生活と学びが結びつくことで、学習内容への関心が高まりやすくなります。
たとえば、「おやつを食べる前に、(手を洗って→机を片付けて)からにしようね」という流れもカッコの考え方と同じです。
以下では、日常生活に「カッコ的な考え」を取り入れるアイデアをいくつかご紹介します。
「式を読む力」を育てる声かけ例
カッコやかけ算・たし算の順番を正しく理解させるには、単に計算させるだけでなく「式を読む力」を育てる声かけが欠かせません。
式の構造や意図を問いかけることで、子どもは自分で考える習慣を身につけていきます。
その理由は、正しく解くことよりも、どうしてその順番になるのかを説明できることの方が理解の定着につながるからです。
言葉で整理することで、ルールの意味を深く捉えることができ、応用力も高まります。
たとえば次のような声かけが効果的です。
- 「この式、どこから先に計算すると決まってる?」
- 「なんでここにカッコがついてると思う?」
- 「全部で何回計算するの?順番に言ってみて」
以下では、さらに具体的な声かけパターンと活用のポイントを紹介します。
具体的な声かけパターン(場面別)
① カッコを含む式を見たとき
- 「このカッコの中って、何をまとめてるのかな?」
- 「先にカッコをやるって、どうしてなんだろう?」
- 「カッコがなかったら、どう計算しちゃいそう?」
② かけ算・たし算が混ざっているとき
- 「かけ算とたし算、どっちを先にするルールだっけ?」
- 「この式、もし左から順にやったらどうなると思う?」
- 「“先にかけ算”って、どんなときでもそうかな?」
③ 間違えたとき・考え直させたいとき
- 「今の式、もし先生に説明するとしたら何て言う?」
- 「どの順番で解いたか、自分の言葉で言えるかな?」
- 「カッコがあっても、いつも通りでよかったかな?」
声かけ活用のポイント
「正しいかどうか」よりも「考えたプロセス」に注目
→ 答えを出す前に、考え方を話す時間を作りましょう。
失敗もOKという雰囲気をつくる
→ 間違えても「よく気づいたね」とフィードバックすることで、自信を失わずに学べます。
すぐに正解を教えず、問いで導く
→「ここはこうだよ」と言う前に「なんでそう思ったの?」と聞いてあげましょう。
紙に書かせて言葉にさせる
→「この式の順番、説明してみて」でアウトプット力が育ちます。
こうした声かけを日常的に取り入れることで、子どもは「式を読んで理解する」力を少しずつ育てていきます。
計算ミスが減るだけでなく、文章題や応用問題でも式を立てる力につながるので、習慣化する価値は大いにあります。
必要であれば、音読・ミニホワイトボード・家庭用プリントなども活用しましょう。
市販教材・アプリを使った反復練習法
カッコ・かけ算・たし算の順番をしっかり定着させるには、市販教材や学習アプリを活用した「反復練習」が効果的です。
特に間違えやすい順序の問題を繰り返し解くことで、自然と計算ルールが身につきます。
その理由は、同じパターンの問題を反復することで、「考え方」を体に覚え込ませられるからです。
視覚や操作も使えるアプリ学習なら、集中力が続きやすく、楽しみながら学習習慣をつけることができます。
家庭で取り入れやすいのは次のような方法です。
- ドリル系の市販教材(例:「ハイレベ算数」「くもんの算数」など)
- 順序判断に特化した学習アプリ(例:「Think!Think!」「トドさんすう」など)
- タブレット教材の自動採点機能で計算ミスを即確認
以下で、それぞれの特徴と活用のコツを詳しくご紹介します。
1. 市販教材(紙のドリル)の特徴と活用のコツ
特徴:
- 解く量が確保できる
- 式を書く・消す・書き直す動作を通じて理解が定着
- 保護者が進度を把握しやすい
おすすめ教材例:
『ハイレベ算数 小学◯年』(奨学社)…応用問題で順序の理解を強化
『くもんの小学ドリル』シリーズ…基礎反復に最適
活用のコツ:
- 計算順序を示す線や番号を自分で書かせる
- 解いたあとに「どこから計算した?」と声かけする
- 間違えた問題を日をあけて2〜3回くり返す
2. 学習アプリの特徴と活用のコツ
特徴:
- ゲーム感覚で取り組めるため、集中が続きやすい
- アニメーションや音声でルールを直感的に学べる
- 繰り返しの練習もストレスになりにくい
おすすめアプリ例:
- 『Think!Think!』…図形や思考力と合わせて順序判断を養える
- 『トドさんすう』…ストーリー仕立てで学年別ステップが明確
活用のコツ:
- 1日5~10分など「短時間×毎日」を習慣化
- 終わったあとに「今日はどんな問題だった?」と内容確認
- 間違えた問題はアプリ内の復習機能を使ってすぐリトライ
3. タブレット教材(通信教育型)の特徴と活用のコツ
特徴:
- 自動採点・解説つきで誤答をすぐに修正できる
- 学年をまたいだレベル調整がしやすい
- 紙よりもテンポよく取り組める
おすすめ教材例:
- RISU算数…思考力問題も多く、カッコを含む複雑な式に対応
- スマイルゼミ…学習履歴や間違えやすい傾向を可視化できる
活用のコツ:
- 「わからなかったところに印」をつけて、後日親子で復習
- 計算ミスの多い単元は、プリントに書き出して紙で再確認
- アニメ解説を見た後に同じタイプの問題を出してもらう
このように、教材ごとに特性と目的を意識して使い分けることで、「カッコ・かけ算・たし算の順番」が着実に身につくようになります。
カッコを使いこなせると、文章題にも強くなる

カッコを正しく使えるようになると、計算力だけでなく文章題を読み解く力もぐんと伸びます。
式の構造を自分で考え、状況に合った順番で計算できるようになるからです。
これは、文章題で問われる「順序の判断」や「情報の整理」が、まさにカッコの役割そのものだからです。
たとえば「何人かの合計を出してからかけ算をする」「差を出してからわり算をする」など、一連の処理をまとめて考える力が求められます。
つまり、カッコの理解は単なる記号の知識ではなく、論理的に式を立てる思考の土台でもあります。
以下では、文章題でのカッコの活用場面を3つに分けて詳しく紹介します。
- 計算式を立てるとき、カッコの力が役立つ理由
- 中学受験でも問われる「カッコの理解力」
- 「計算の工夫」としてカッコを使う問題もある
計算式を立てるとき、カッコの力が役立つ理由
文章題で計算式を立てるとき、カッコを使いこなせることが正しい式づくりのカギになります。
どこを先に計算すべきかをカッコで表現することで、複雑な問題もシンプルに整理できるからです。
カッコの役割は、「この部分をまとめて先に考える」ことを視覚的に示すこと。
これによって、文章中の数量関係を正しく式に落とし込めます。
逆に、カッコを使わないと、かけ算やたし算の順序を誤ってしまい、答えがまったく変わってしまうこともあります。
たとえば「兄と妹の合計人数にケーキを配る」ような場面では、(兄+妹)×ケーキの個数とカッコを使うことで、意図した順番が明確になります。
以下で、カッコが文章題でどう使われるかを具体的に解説します。
カッコが文章題で使われる典型パターンと考え方
① 合計してからかけ算するパターン
文章題例:
「兄に3個、妹に4個ずつクッキーを配りました。兄と妹は合わせて何人かいて、全体で何個配ったでしょう?」
考え方:
まず「兄+妹」の合計人数を出す必要がある
その合計人数に1人あたりの個数(例:3個)をかける
式:
(兄の人数+妹の人数)×クッキーの個数
ポイント:
「先に人数をたす」必要があるので、たし算の部分をカッコでまとめることが必須。
② 差を出してから割り算するパターン
文章題例:
「100円玉が20枚、50円玉が12枚あります。100円玉のほうが何倍多いでしょう?」
考え方:
「何倍多いか」は差を出してから、50円玉の数で割る
先に引き算をしてから割り算をする順番が大事
式:
(100円玉の枚数 − 50円玉の枚数)÷ 50円玉の枚数
ポイント:
引き算を先に行う必要があるため、カッコが重要になります。
③ 計算の工夫でまとめるパターン
文章題例:
「25+38+75を計算するとき、どれかをまとめて先に計算すると楽になります。どこをまとめますか?」
考え方:
「25+75=100」と気づけると楽
先にまとめる部分をカッコにして計算を楽にする
式:
(25+75)+38
ポイント:
カッコで「まとまり」をつくることで、処理が簡単になるという「工夫としてのカッコ」もある。
まとめ:カッコは「先に考えるべき部分」を示す道具
カッコの本質は、「この部分をひとまとまりとして最初に処理する」という考える順番の可視化です。
文章題では、問題文を読んで、「どこがまとまりか?」を見抜く力が求められます。
これを身につけるには、式を立てる前に「どういう順で考えるか?」を口に出させたり、文章中に出てくる数量関係を図や言葉で整理する練習がおすすめです。
中学受験でも問われる「カッコの理解力」
中学受験では、「カッコの意味を正しく理解しているか」が頻繁に試されます。
単なる計算の順番だけでなく、文章題の中でどこにカッコを使うか判断する力が求められるからです。
これは、与えられた数字や条件から自分で式を立てる力=論理的思考力が重視されるためです。カッコがあるかないかで計算の意味がまったく変わってしまう問題が出されるため、「カッコ=計算の優先順位を明確にする道具」として理解しておく必要があります。
たとえば、「全体の人数にまとめてかけるのか、部分ごとにかけるのか」といった差が、カッコの有無で大きな違いとなって表れます。
以下で、実際に中学受験に出題されるような事例を交えて詳しく解説します。
事例①:全体にかける?部分にかける?
問題例:
兄が2人、妹が3人います。1人にノートを4冊ずつ配りました。全部で何冊必要ですか?
考え方:
全員の合計人数に対して、ノートを配る → 「先に足してからかけ算」
式:
(2+3)×4=20
カッコのポイント:
ここでカッコをつけ忘れて「2+3×4=14」とすると、妹にだけかけ算が適用されてしまい、答えがずれてしまいます。
「たす→かける」の順を明示するためのカッコが必須です。
事例②:条件をグループ化してまとめる
問題例:
大人が3人、子どもが4人で、遊園地の入場料は大人が800円、子どもが500円です。全体の合計金額はいくらですか?
考え方:
大人の合計と子どもの合計をそれぞれ計算してから、最後にたす
式:
(3×800)+(4×500)=2,400+2,000=4,400
カッコのポイント:
計算の順序をはっきりさせるために、かけ算のペアごとにカッコでまとめることで、たし算の前に何を処理すべきかが明確になります。
これは文章の流れと一致させる上でも重要です。
事例③:逆に「カッコをつけると間違う」ひっかけ問題
問題例:
りんごが8個あります。
3人の子どもに、まず2個ずつ配り、残りを4人で分けます。1人分のりんごは何個ですか?
考え方:
まず「2×3=6」で配った数を出す
残りは「8−6=2」、それを「2÷4=0.5」ずつ配る
式:
(8−(2×3))÷4=0.5
カッコのポイント:
このように入れ子構造(二重カッコ)で処理の順序を示さないと正解できないタイプの問題もあります。
ここでは先に配った量を「2×3」で出し、それを全体から引くことが重要です。
中学受験のカッコは「式の言語力」を問う
中学受験での「カッコの理解力」は、式で正しく状況を表現する国語力や論理力にも直結しています。
ただ計算するのではなく、「なぜこの部分を先に処理するのか?」を言語化できる子は、複雑な問題にも対応できます。
声かけや図解を交えた練習と、「計算の順番=意味の順番」を理解させるトレーニングが、中学受験対策では特に効果的です。
「計算の工夫」としてカッコを使う問題もある
計算の順番に正しく従うだけでなく、より速く・正確に解くために“カッコを使って工夫する”問題も中学年以降に増えてきます。
ただのルールではなく、“便利な道具”としてカッコを活用できるようになると、計算力の質が大きく変わってきます。
その理由は、カッコを使うことで「まとまり」や「共通部分」を見つけて、計算を効率化できるからです。
たとえば、同じ数を何度も足すより、かけ算でひとまとめにしたり、分配法則を使って式を簡略化したりできます。これは文章題だけでなく、計算力の底上げにもつながります。
実際に、工夫を促す問題では次のような例があります。
- 48+47+52 を「(48+52)+47=100+47」で先に簡単にできるペアを使う
- 25×4+25×6 を「25×(4+6)」にまとめてかけ算を1回にする
- (35+45)÷5 を「1つのまとまりで割る」と意識して計算する
このように、カッコは順番を守るだけでなく、「見やすく・解きやすく」するための工夫にも使えるのです。
文章題で使いこなす前に、まずはこうした身近な例で「なるほど」と思える経験を積ませましょう。
まとめ:カッコ・かけ算・たし算の順番で迷わないために
計算の順番に迷わないためには、「カッコ」「かけ算」「たし算」のルールを正しく理解し、繰り返し練習することが大切です。
子どもが混乱しやすいポイントを丁寧に整理することで、計算力と読解力の両方が育ちます。
順序を誤ると正しい答えにたどりつけないため、単なる暗記ではなく「なぜその順番になるのか」を納得して覚えることが重要です。
特にカッコの役割や優先順位を実感をもって学ぶことが、応用力を育てるカギとなります。
本記事では、よくあるつまずきから正しいルールの教え方まで段階的に紹介しました。文章題への応用や中学受験にもつながる内容を踏まえ、「順番」の理解が深まるように構成しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
「カッコ・かけ算・たし算の順番」について、少しでもヒントや気づきがあったならうれしいです。
もし記事の内容に共感いただけたり、「うちの子はこうでした!」といった体験談があれば、コメント欄でぜひ教えてくださいね。
みなさんの声が、これからの記事づくりの励みになります!

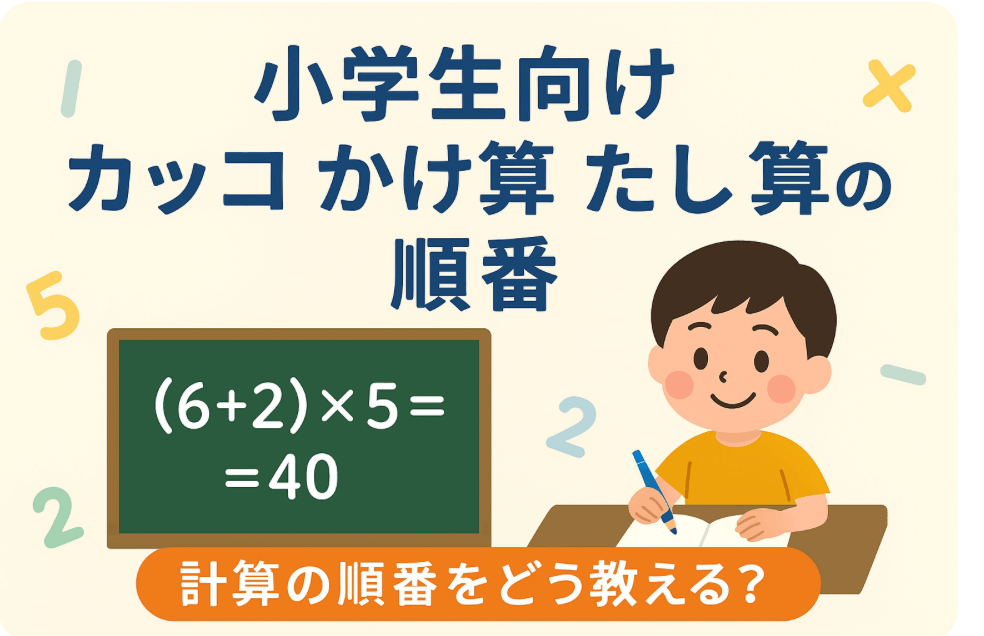



















コメントを残す