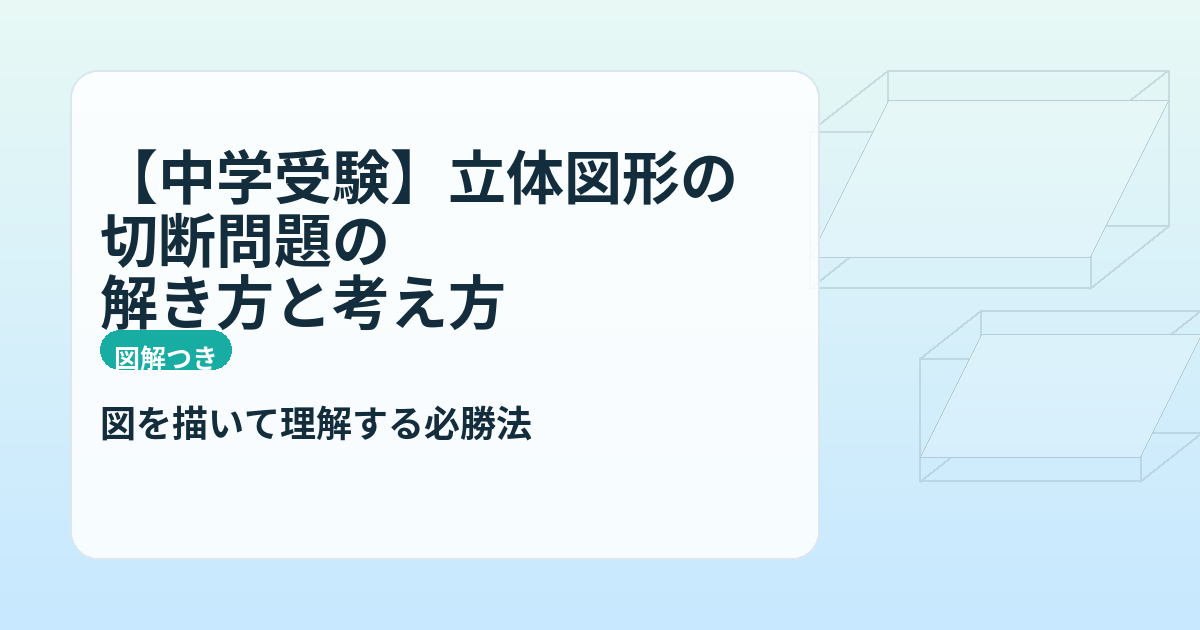今日の結論
- 解き方:切断平面の3点を先に確定→各面で交点を結ぶ。
- まず見る所:相似の高さ比で体積比=相似比³・対向辺の平行関係。
- ミス回避:頂点対応表を作る・補助線は薄く、結論線は濃く。
目次
立体図形の切断問題とは?
[sc_ok]立体図形の切断問題とは、立方体や三角柱などの立体を平面で切ったときにできる「切り口」や体積・表面積を考える問題のことです。
中学受験算数では頻出分野であり、図を描く力と空間認識力を同時に鍛えられます。
苦手になりやすい分野ですが、仕組みを理解すると得点源に変えやすいのが特徴です。
なぜ重要かというと、第一に入試での出題率が高く差がつきやすいからです。
第二に、頭の中で立体をイメージする力は算数全体の理解にもつながります。
さらに、図を描いて考える習慣は文章題や図形全般の学習に応用でき、長期的な学力定着に役立ちます。
筆者の教室でも、紙立方体を切る体験を取り入れた後、正答率が着実に上がった事例があります。
- 中学受験でよく出る切断パターンが分かる
- 保護者が学習意義を理解して家庭でサポートできる

中学受験でよく出る切断のパターン
典型パターンを知っておくと、立体図形切断の解き方を効率的に身につけられます。
試験本番で迷わず取り組めるようになり、得点力の安定につながるでしょう。
重要視される理由は三つ。
- 出題頻度が高く差がつきやすい。
- 切り口や体積計算を通じて空間認識力(立体を頭で回転・投影する力)が鍛えられる。
- 平面図形と直結し算数全体の理解を深めるからです。
教室でもこの分野を強化した生徒は、図形大問の正答率が目に見えて向上しました。
例えば立方体を対角線で切ると切り口は三角形、中点どうしを結ぶ切断では台形や五角形が現れることがあります。
最初は意外でも、反復で「出やすい形」が見えてきます。

保護者も知っておきたい「切断」の学習意義
保護者が意義を理解しておくと、家庭でのサポートが的確になります。
空間認識力を高めつつ、入試で差がつく分野を強みに変えられるからです。
- 多くの入試で出題・配点が大きい
- 平面図形や体積計算と密接で総合力が問われる
- 図を描く習慣が作図・文章題にも波及する
の三点が主理由。実際、切断を重点練習した生徒は模試順位の安定が見られます。
紙で立方体を作って対角線で切る親子体験は効果的です。
実感を伴う学びは記憶に残りやすく、家庭学習の雰囲気も良好になります。
立体図形の切断の基本的な考え方
学習指導要領(算数)で求められる図形の学習目標(文部科学省)この基本を押さえると、複雑に見える問題も整理しやすくなります。
図を描きながら取り組む習慣が身につけば、本番でも落ち着いて対応でき、得点源に変えられるでしょう。
大切な理由は三つ。
- 平面と立体の関係を誤ると切断後の形を誤認しやすい
- 投影図(立体を平面に写す図)で頭の中の操作を視覚化できる
- 実物を切る体験が理解を深め長期記憶につながる
です。

参考動画:立方体の切断を題材に、投影図と補助線の使い方・断面確定の流れを解説
次に以下の3つのポイントについて解説をします
- 平面と立体の関係をイメージする方法
- 投影図を使った理解の手順
- 実際の切断体験が学習効果を高める理由
平面と立体の関係をイメージする
立体を回転したり、断面を思い浮かべたりする力は必須です。
断面を正確に把握できないと計算へ進めません。
正面・真上など複数視点へ「投影」することで誤解を減らし、展開図や体積計算ともつながります。
投影図を継続練習した生徒は図形大問の安定感が増しました。
正面・真上・横から見る「投影図」を活用
投影図は頭のイメージを可視化する道具です。問題条件を整理しやすく、切断後の形の推測が安定します。
複数方向から確認する習慣は空間認識力を総合的に高め、他の図形分野にも波及します。
参考動画を合わせて視聴すると、作図から断面確定までの流れが掴みやすくなります。
実際に切ってみると理解が深まる(紙や発泡スチロール)
手を動かすと視覚+触覚で記憶に残ります。切断後の断面を直接見ることで「イメージとのズレ」を修正でき、体積・展開図の理解にも自然に結びつきます。
厚紙の立方体を中点で切ると五角形の断面が現れることがあり、驚きが納得に変わる過程が強い学習効果を生みます。

立体切断問題の解き方ステップ
手順を体系化すると、複雑な問題もブレずに解けます。
以下の4ステップを習慣化すれば、得点力が安定し本番でも自信が持てます。
参考動画と併用して、視点の切り替えと補助線の入れ方を確認しましょう。
- 問題文の条件を整理する
- 立体に補助線を入れて図を描く
- 切り口の形を予想する
- 切断後の展開図・体積・表面積を確認する

① 問題文の条件を整理する
切断位置や基準点などの細かな指定を読み落とすと解答が大きくズレます。
条件整理で補助線・投影図の方針が明確になり、複数条件でも混乱を避けられます。
教室でも「条件の書き出し→図示」の徹底で正答率が安定しました。
② 立体に補助線を入れて図を描く
補助線は条件の可視化です。対角線や中点を結ぶことで断面の形をイメージしやすくなり、計算ミスも減ります。
立方体なら中点を先に印し、結ぶ線を描いてから切断を考えると、台形・五角形の断面が見通せます。
③ 切り口の形を予想する
断面形は三角形・四角形・五角形など多様。誤った予想は後工程をすべて崩します。
条件から形を論理的に絞る習慣が、空間認識力と応用力を底上げします。
立方体の中点切断で五角形が出る例など、参考動画の実演でイメージを固めるのも有効です。
④ 切断後の展開図・体積・表面積を確認する
展開図で切り口の位置・形を整理し、体積・表面積の整合をチェック。
分割後の立体の合計体積が元と一致するか、途中式に矛盾がないかを必ず検証しましょう。
仕上げの確認が得点の安定を支えます。
よく出る立体の切断例
頻出パターンを押さえるのが近道です。代表的な立体をどう切るかを理解しておけば、応用が利き、得点に直結します。
- 立方体の切断(対角線で切る、辺の中点で切る)
- 三角柱の切断(底面と頂点を結ぶ)
- 四角錐・円錐の切断(高さの途中で切る)
立方体の切断(対角線/中点)
対角線で切ると断面は三角形。中点を結ぶ切断では台形や五角形が現れます。
実演を確認したい場合は参考動画で、視点と補助線の取り方を合わせてチェックしましょう。
三角柱の切断(底面と頂点を結ぶ)
立方体より形が複雑で、切断面が四角形や五角形になる場合が多いタイプ。
底面の辺の中点と反対側の頂点を結ぶ切断など、典型例を一通り描いておくと判断が速くなります。
四角錐・円錐の切断(高さの途中で切る)
水平切断では相似比で体積・表面積を扱います。円錐を高さの半分で切ると、上が小円錐、下が台錐(小錐を切り取った立体)に。
相似と体積を結びつける練習に最適です。
立体図形の切断で注意すべきミス
よくある誤りを先に知っておくと、時間を節約しつつ正確な答案を書けます。
- 切り口の形を思い込みで決める
- 図を描かずに頭の中だけで処理する
- 展開図・体積の計算で条件を見落とす
切り口の形を勘違いする
思い込みで三角形と決めつけるなどの誤認は、展開図・計算を連鎖的に崩します。
複数視点の投影図+補助線で検証するのが鉄則です。
図を描かずに頭の中だけで解こうとする
人は空間情報を正確に保持しにくいもの。
図示は条件の整理とミスの予防、さらに部分点の確保にもつながります。参考動画で「作図→断面確定」の流れを一度見てから手を動かすと安定します。
展開図・体積の計算で条件を見落とす
分割後の立体を把握しきれず、長さ・面積の数え落としが起こりがち。
展開図を描いて、体積合計=元の体積かを必ず確認しましょう。
家庭学習でできる立体切断の練習法
家庭では「教材×作図×実物」の三本柱で進めると効果的です。
最初の取っかかりは、上記の参考動画で流れを掴み、すぐに手を動かしましょう。
市販教材・アプリ・動画を活用する
頻出パターンを網羅した問題集、立体の変化を動きで示す動画は定着に有効です。
まずは参考動画で基本の流れを掴み、アプリや問題集で反復しましょう。
紙で立方体を作って実際に切る
厚紙や折り紙で立方体を作り、中点や対角線で実際に切ると、断面の形が直感的に理解できます。
予想とのズレを実体験で修正できるのが強みです。
過去問や塾のテキストで段階的に練習する
基本→標準→応用の順で負荷を上げます。
最初は立方体、次に三角柱や円錐へ広げると効果的。
作図スピードと処理精度が上がり、時間内に解き切る力がつきます。
<!– 図解 8:家庭学習の3種類(教材・紙模型・過去問)イメージ図をここに挿入 –>
まとめ|立体図形の切断を得意分野にするために
結論、図を描く→典型パターン→実物体験の順で段階的に練習すれば、切断は必ず得点源になります。
出題頻度が高く差がつく単元だからこそ、学習の「型」を身につける価値が大きいのです。
まずは本記事のフローと参考動画の手順をなぞり、手を動かす学習へ一歩踏み出しましょう。
この記事で扱った主な参照・補助
- 参考動画(投影図と補助線の使い方・断面確定の流れ):
https://youtu.be/cYSReJnzzuk
※本記事の効果に関する言及は、筆者(学習塾)での指導経験・集計に基づく一次情報です。