「九九は完璧に覚えているのに、文章題になると手が止まってしまう…」
そんなお子さんの様子に、心当たりはありませんか?実は今、多くの小学生が「かけ算 九九 だけでは足りない」壁にぶつかっています。
九九の暗記はスタート地点にすぎません。本当に必要なのは、“かけ算を使いこなす力”です。
この記事では、小学3〜4年生で求められるかけ算の考え方や、「九九はできるのに成績が伸びない」理由、そして家庭でできる具体的なサポート方法まで、丁寧に解説します。
今後の算数力を左右する“九九のその先”を、いっしょに見ていきましょう。
目次
かけ算・九九が「足りない」とはどういう意味?

かけ算九九を覚えたのに、3年生・4年生になってから「つまずき」が見えてくる。
そんなとき、「九九だけでは足りない」と感じる保護者や先生は多いでしょう。
実は、九九の暗記はあくまでスタート地点にすぎず、かけ算の本質的な理解にはもっと広い力が必要なのです。
九九は「答えをすぐに出す」ための道具ですが、かけ算の力とは「場面に応じて使いこなす力」を意味します。
文章題や図形問題、単位の変換など、小3以降で登場する複雑な問題には、単なる九九の知識だけでは対応できなくなっていくのです。
たとえば「3つの箱にりんごが4個ずつあるとき、全部で何個?」という問題。
九九の知識があっても、「なぜ×を使うのか」「式の意味は何か」がわかっていなければ正しく答えることができません。
以下では、九九だけで解けない理由や、3〜4年生で求められる力について詳しく解説していきます。
九九だけで解けない問題が出てくる理由
九九を完璧に覚えていても、それだけでは対応できない問題が小学校3〜4年生で増えてきます。「九九はできるのに成績が伸びない」という悩みの裏には、かけ算の“使い方”に関する理解が不十分なケースが多く見られます。
というのも、九九はあくまで「計算結果をすぐに出すための道具」であり、それ自体が“かけ算の本質”ではありません。
文章題や図形、単位の変換といった問題では、「なぜその式になるのか」「何と何をかけているのか」といった思考力が問われるため、単なる暗記では太刀打ちできなくなるのです。
とくに、次のような場面で九九だけでは解けない問題が登場します。
- 「1個120円のりんごを3個と2個で買った。合計金額は?」などの複合的な文章題
- 「正方形の面積を求めよう」といった図形問題
- 「時速×時間=距離」といった単位のかけ算
以下で、これらの問題に必要な力を詳しく解説します。
複合的な文章題:「1個120円のりんごを3個と2個で買った。合計金額は?」:必要な力:数量の分解と構造化、式の組み立て力
この問題は「かけ算×2+たし算」の構造を含んでおり、次のような理解が必要です。
- 120円×3個 と 120円×2個 の2つのかけ算に分ける力
- それらを足して「全体の金額」を求める力
- 「何に対してかけ算しているのか」を文脈から読み取る力
→九九の暗記だけでは、このような構造を見抜いて適切に式を立てるのは難しく、「文章の意味を数式に変換する力」が求められます。
図形問題:「正方形の面積を求めよう」:必要な力:図と数の関係の理解、単位の意味の把握
- 図形の面積=「たて×よこ」で求められますが、これは単なる九九の活用ではありません。長さと面積(1次元と2次元)の違いを理解する力
- 単位(cm・cm²)の変化に気づく力
- 「たて×よこ=面積」という構造の意味づけ
→「何をかけたら面積になるのか」「なぜこの計算で面積になるのか」を理解していないと、式は立てられても意味のある学力にはなりません。
単位のかけ算:「時速×時間=距離」:必要な力:抽象的な数量の関係理解、単位の運用力
このような物理量を含むかけ算は、より抽象的であり、次のような力が必要です。
- 時速1時間あたりの距離」という意味の把握
- 「時間が何倍になれば、距離も何倍になる」比例関係の理解
- 単位(km/h × 時間 = km)という数量の正しい扱い
→「九九を知っていても、単位の意味がわかっていないと誤った数値を出してしまうケースが多く見られます。
これらの問題に共通して求められるのは、「なぜこの式になるのか?」「何と何をかけているのか?」と考える数量関係の理解力や文脈を読み取る力です。
九九の習得は基礎でしかなく、その先にある“使いこなす力”を育てることが本質的なかけ算力につながります。
小学3〜4年で求められるかけ算の力
小学3〜4年生では、単に九九を覚えているだけでは通用しない「かけ算の応用力」が求められます。
計算の正確さだけでなく、式の意味や使い方まで理解しているかどうかが、今後の算数力を大きく左右します。
たとえば、文章題の中で「かけ算を選ぶべき場面かどうか」を判断したり、図形やグラフから情報を読み取って式に表したりする力が必要になります。
これは、九九を覚えていることとは別の思考力や読解力が関係してくるからです。
この段階で必要とされる力は、以下のようなものです。
- 文章題の条件を読み取り、自分でかけ算の式を立てる力
- かけ算と割り算の関係を理解し、場面に応じて使い分ける力
- 単位の意味や、数量と数の違いを意識する力
以下で、それぞれの力をどのように育てていくかを具体的に解説します。
「覚える」だけでなく「使う」ための理解とは
九九をスラスラ言えるようになっても、それを「使える」力が伴っていなければ、かけ算の本質を理解しているとは言えません。
計算の速さや正確さだけでなく、「なぜその式を使うのか」を理解していることが、真の意味での数学的思考につながります。
かけ算を使いこなすには、「何を何倍しているのか」「この場面でなぜかけ算なのか」を自分の言葉で説明できる力が求められます。
単なる暗記ではなく、数量の関係性や問題の構造を捉えることが、3〜4年生の算数では特に重要になります。
この“使うための理解”を育てるには、以下のような視点が欠かせません。
- 計算式が「何を表しているのか」を言葉で説明させること
- 図や絵を使って「かけ算の構造」を視覚化すること
- 日常の中で「かけ算って便利だね」と実感させること
計算式が「何を表しているのか」を言葉で説明させること
九九や計算問題を解いたあと、「この式って何を意味しているの?」と問いかけてみましょう。
たとえば「3×4=12」であれば、「3人にみかんが4個ずつあるとき、全部で何個かを表している」と自分の言葉で説明できるかを確認します。
これにより、「式=現実の状況の言い換え」であることを体感でき、単なる数字遊びにならず、意味のある知識として定着します。
図や絵を使って「かけ算の構造」を視覚化する
とくに有効なのが「配列モデル(たて×よこ)」「面積図」「絵カード」などの視覚的な支援です。
- 配列モデル:3行4列の○を描いて「3×4」の意味を見せる
- 面積図:縦3cm・横4cmの長方形を描き、面積が「3×4=12」となる仕組みを示す
- 絵カード:具体物(りんご、文房具など)を並べて数量の繰り返しを体感させる
こうした可視化により、「数が繰り返される意味」や「なぜかけるのか」が直感的に理解できます。
日常の中で「かけ算って便利だね」と実感させる
九九は“生活で役立つもの”として実感できると、自然と「使う力」も身につきます。
たとえば:
- 料理:卵1個でホットケーキ2枚 → 3個なら?「1×2」「3×2」など
- 買い物:100円のジュースを4本買うと?「100×4」
- お出かけ:1人2枚のチケットを家族4人分 → 「2×4」
「かけ算って便利!」「使える!」という体験の積み重ねが、九九を“意味ある知識”に変えていきます。
このように九九は暗記して終わりではなく、「どう使うか」「なぜ使うか」を考えさせることが大切です。
言葉にする・図にする・日常に活かす、という3つのステップで、“使えるかけ算力”を育てていきましょう。
九九の覚え方だけではダメ?見落としがちな落とし穴

九九を「早く」「正確に」言えるようにすることばかりに目が向きがちですが、それだけでは本当の意味で“かけ算力”は育ちません。
かけ算を「覚えたのに使えない」というケースは、まさにこの“落とし穴”に入っている状態です。
九九はあくまで計算の道具であり、「どう使うか」「なぜ使うか」が理解できていなければ応用がききません。
文章題や図形問題、日常場面での計算に対応するには、九九の暗記に加えて“使う力”を育てる工夫が欠かせないのです。
とくに以下のような点が、九九の覚え方に潜む落とし穴となりやすい要素です。
- 九九を「順番にしか言えない」状態になっている
- 意味のない繰り返しで機械的に覚えてしまう
- 覚えた九九を実際の問題に結びつけられない
これらの問題点とその対処法について、以下で詳しく解説します。
九九の丸暗記が子どもに与える影響
九九を丸暗記するだけの学習は、一時的にはスラスラ言えるようになりますが、かけ算の理解が伴っていないと、応用問題でつまずきやすくなります。
「九九は覚えたのに問題が解けない」というギャップが、子ども自身の自信を失わせてしまうことも少なくありません。
これは、九九の数字の並びを機械的に覚えることで「意味のある計算」ではなく「ただの呪文」のように捉えてしまうためです。
その結果、式の意味を考える習慣が育たず、「何を×何しているのか」がわからないまま進んでしまいます。
とくに次のような影響が見られることがあります。
- 九九の順番でしか答えられず、逆算や文章題に対応できない
- 単位や数量の意味を無視した機械的な計算になる
- 「計算は苦手」という思い込みから算数全体への苦手意識が広がる
こうした問題を防ぐためには、「覚える」ことに加えて「意味づけ」や「使う体験」が必要です。
「九九の丸暗記が子どもに与える悪影響」を防ぎ、意味のあるかけ算理解につなげるための具体的な対策を3つに分けて解説します。
すべて家庭や授業で手軽に取り入れやすい方法です。
「九九=意味ある数の関係」として視覚化する
九九の式を図や絵で見える形にすることで、ただの暗記ではなく「数のしくみ」として理解させることができます。
例:
- 「4×3」を4列3行の●で表す(配列モデル)
- 「5×2」を、5本のえんぴつが2束ある絵で表現する
- 「面積=たて×よこ」で九九が図形とつながる体験をさせる
こうした視覚化は、九九の“意味”を頭の中でイメージできるようにする大切なステップです。
九九の「言い換え」をさせて式の意味を深掘りする
九九を言わせた後、「これはどういう意味?」と尋ね、状況に置き換えて説明させることで、言葉と式の結びつきを育てます。
例:
- 「6×4=24」→「6人が4つずつ持っているとき、合計いくつ?」
- 「3×5=15」→「5円玉を3枚持っていたら、合計いくらになる?」
言い換えることで「数の組み合わせ」「かける意味」を実感できるようになります。
日常の体験を通じて「九九を使う場面」を増やす
九九を“実際に使うもの”として体験することで、「覚えたけど使えない」状態から脱却できます。
日常生活の中にかけ算の場面を意識的に仕込むことがポイントです。
活用例:
- 料理:1人前100gのパスタを4人分作る →「100×4」
- 買い物:1個150円のパンを3個買う →「150×3」
- おでかけ:1人に2枚ずつチケットを配る →「2×家族の人数」
こうした体験を積み重ねることで、「九九は便利!」「使える!」という実感が定着し、学習意欲も高まります。
九九の丸暗記はスタート地点であり、本当に大切なのは「意味を理解し、自分で使えるようになること」。
図・言葉・体験という3つの角度からアプローチすることで、九九の“その先”の力が育ちます。
学校任せにせず、家庭でもこうした工夫をぜひ取り入れてみてください。
「意味のない繰り返し」が苦手意識を生む
九九をひたすら何度も唱えさせるだけの練習は、表面的には「覚えている」ように見えても、子どもの中に意味が伴っていない場合があります。
その結果、「何のためにやっているのか分からない」という不満や、苦手意識へとつながりやすくなります。
これは、九九を“音のかたまり”として覚えることで、計算の背景にある数量の関係や、かけ算の意味が理解されずに進んでしまうからです。
意欲が低下し、「かけ算=つまらない」「九九=苦手」という印象が残ってしまうのです。
とくに以下のような傾向があると、苦手意識を強めやすくなります。
- 「ににんがし、にさんがろく…」と意味も分からず唱えている
- 正しく言えるのに、なぜその計算になるのかを説明できない
- つまずいたときに「覚えてないからダメ」と決めつけられる
こうした状況を避けるためには、「唱える」だけでなく「考える」「使う」学び方が必要です。
以下に、「九九の意味のない繰り返し」によって苦手意識が生まれることを防ぐための、具体的な3つの工夫を紹介します。
どれも家庭や教室で簡単に実践できる方法です。
数字を“モノ”に置き換えて理解させる
九九の式を、実際のものや状況に結びつけて考えさせましょう。
例:
- 「3×4=12」は「みかんが3つのお皿に4個ずつのってる」
- 「5×6=30」は「1箱に5個入りのクッキーが6箱ある」
こうすることで、「なぜかけ算を使うのか」が自然に理解でき、式が“意味のある言葉”になります。
反対の質問をして思考を深める
九九の復唱だけでなく、「どうしてその式になるの?」「逆に、5×2と2×5は同じかな?」などの問い返しをすることで、子どもに考えさせる力が育ちます。
こうした“頭を使うやりとり”は、記憶の定着だけでなく、九九を「使える知識」に変えていく第一歩です。
日常生活の中で「かけ算を使う場面」を意識する
九九は、ドリルの中だけでなく生活の中で使うことで初めて意味を持ちます。
活用例:
- 洗濯物干しで「ハンガー1本に2枚ずつあると全部で?」
- おやつを配るとき「3人に2個ずつ配ると、全部で?」
- 買い物で「100円のものを4つ買うといくら?」
このように、“意味のない繰り返し”を「意味のある体験」に変えることが、かけ算への苦手意識を防ぐ最大のポイントです。
九九を「唱える」ことは大切ですが、それだけでは“使える力”にはなりません。
言葉で説明する・図にする・生活で使う、この3つの視点を取り入れて、九九の学習を“意味あるもの”にしていきましょう。
九九を「覚えたけど使えない」子どもたちの特徴
九九を暗唱できるようになっても、それを実際の問題に活かせない子どもは少なくありません。
こうした場合、「覚えている=理解している」わけではなく、かけ算の意味や使い方が身についていない可能性があります。
九九は計算の道具ですが、それを「どの場面でどう使うか」という思考が伴っていないと、文章題や図形問題になると手が止まってしまいます。
言われたことには答えられても、自分から式を立てる力がないのが大きな特徴です。
とくに以下のような特徴が見られることがあります。
- 九九は言えるのに、文章題になると式が立てられない
- 「3×4」と「4×3」の違いを説明できない
- 問題文に出てくる数量をうまくイメージできない
こうした状態を放置すると、「かけ算 九九 足りない」まま学年が上がり、算数への苦手意識が強くなってしまいます。
ただ九九を暗記しているだけでは、応用問題に対応できないことがあります。
そんなときには、四則計算の基本的な教え方を見直してみるのも有効です。
→ 〖完全版〗足し算・引き算・掛け算・割り算の教え方|子どもにわかる基本とコツ
また、筆算の際に間違いが多いお子さんには、家庭でできるミス対策もおすすめです。
→ 〖保存版〗筆算ミスを防ぐ!家庭でできる3つのチェックポイント
九九が「足りない」と感じたときの教え方の工夫

九九をしっかり覚えたはずなのに、かけ算の応用になると急につまずく――。
そんなときは、ただ覚えるだけでなく「どう使うか」を教える工夫が必要です。
九九の“意味”に立ち返りながら、子どもが納得して使える状態を目指すことが大切です。
というのも、九九を「音」として暗記しているだけでは、場面に応じた使い方が身につきません。
かけ算は数量の関係を表すものなので、「なぜその式になるのか」「何に何をかけているのか」を自分で考える力が求められます。
これこそが、九九だけでは“足りない”と言われる理由です。
こうした力を育てるには、九九の復唱に加えて、かけ算の意味づけや使い方に焦点をあてた教え方が効果的です。
以下で、具体的な工夫を3つの視点から詳しく解説していきます。
かけ算の「意味」を視覚化する
かけ算のつまずきは、九九の暗記だけで終わってしまい「かけ算の意味」が理解できていないことに起因します。
だからこそ、数字だけでなく“視覚”で理解させることが、算数嫌いを防ぐ大きなカギになります。
視覚化することで、「何と何をかけているのか」「なぜかけ算になるのか」が子どもの中でつながりやすくなります。
九九を唱えるだけでは足りないと感じる場面で、図や絵、具体物を使ってかけ算の構造を見せることが有効です。
たとえば、次のような方法で視覚化することができます。
- 配列モデル(たて×よこに●を並べる)
- 面積図(長方形のたて・よこをかける)
- 絵カードや実物を使った数量の再現
以下で、それぞれの視覚化方法と活用例について詳しく解説します。
配列モデル(アレイ図)
たて×よこの並びで、かけ算の意味を「見える化」する方法。
活用例:
「3×4=12」を、3行4列の●を描くことで表します。
●●●●
●●●●
●●●●
この図から「4個が3列分ある」「4を3回足したら12になる」ことが直感的に伝わります。
指導ポイント:
縦×横、横×縦を入れ替えて、「順序が違っても答えは同じ」を体感させる。
慣れてきたら、数字を隠して図だけで「式を言わせる」練習も有効です。
面積モデル(面積図)
かけ算が図形(長方形)の面積に応用されることを示す方法。
活用例:
「5×2=10」は、たて5cm×よこ2cmの長方形を描き、「面積=たて×よこ」の考えにつなげます。
これは小3以降の面積の単元でも使われる考え方なので、かけ算の実用性を理解する助けになります。
指導ポイント:
単位(cm、cm²)に注意して、「何を表すか」まで意識させる。
正方形・長方形の構造に合わせた「たて×よこ」の意味を考えさせる。
絵カード・具体物を使ったモデル化
目に見えるものを使って、「かけ算=同じ数のくり返し」を体感する方法。
活用例:
・お皿にりんごを4個ずつのせたカードを3枚見せて「4×3」
・100円玉を5枚ずつ入れた袋を2袋出して「5×2」
こうすることで、子どもが頭の中で“数のまとまり”をイメージしやすくなります。
指導ポイント:
「何個が何セットあるか?」を子ども自身の言葉で言わせる。
このように実際の文房具・お菓子など身近なものを使うと、理解と記憶が深まりやすい。
かけ算は「数字の操作」ではなく、「数量の関係を表す考え方」です。
九九だけでは足りないと感じたときは、図や絵、実物で“意味”を伝えることが、子どもの理解力を飛躍的に高めるカギになります。
「式の意味」と「単位」をセットで教える
かけ算を本当に使いこなすには、「式の意味」と「単位」の両方をセットで理解させることが重要です。
九九だけを覚えていても、「何をかけているのか」「その結果が何を表すのか」が曖昧だと、応用問題や文章題でつまずいてしまいます。
たとえば「3×200=600」と答えられたとしても、「3つの箱に200個ずつ商品が入っている」という具体的な状況と、「600個」という単位の意味を理解していなければ、かけ算の本質には近づけません。
九九は万能ではなく、“使い方の理解”がなければ足りないのです。
このような理解を深めるためには、以下のような工夫が効果的です。
- 「式に登場する数字が何を表しているか」を必ず言葉にさせる
- 計算結果に「単位」をつけて読む(例:600円、12人、24個など)
- 単位が変わると意味も変わることを体験させる(円と個など)
以下で、それぞれの具体例と実践のヒントをご紹介します。
数字を「もの」や「人」に結びつける練習
式に出てくる数字が何を表しているのかを言葉で説明させる。
具体例:
「3×4=12」なら、
「3人にアメを4個ずつ配ると、全部で12個」
→ 3は「人」、4は「個」、12は「全部の個数」という関係になります。
実践のヒント:
「これは何人?何個?」と問いかけて確認する
数字の後ろに単位(人・円・cmなど)をつけて言わせる
反対に「3×?=15。1人あたり5個なら、何人?」と逆算で確認するのも効果的
計算結果に「単位」をつけて読む練習
式の答えは“数”だけでなく、“意味のある数量”として扱うことが大切。
具体例:
「5×100=500」なら、
「100円の品物を5個買うと、合計500円」
→ 答えを「500」とだけ言わせず、「500円」と言う練習を繰り返す。
実践のヒント:
ドリルでも口頭でも「単位つき」で読むルールにしてしまう
小テストで「答えに単位がないと不正解」にして意識づけ
計算だけでなく「何の数?」をセットで問いかける
同じ式でも「単位」で意味が変わることを体験させる
式が同じでも、場面や単位が違えば“答えの意味”はまったく変わる。
具体例:
「4×2=8」
・4人に2個ずつお菓子→「8個」
・4人が2時間ずつ走った→「8時間」
・4冊の本が2キロずつ→「8kg」
実践のヒント:
同じ式で複数の場面(ストーリー)をつくって比較させる
答えだけ見て「何の数か」を言い当てるゲーム形式も有効
生活場面の写真を見せて「これは何を×何してるのか?」を考えさせる
このように九九の暗記では届かない「かけ算の本質」は、式の意味と単位の意識づけによって身についていきます。
単なる数のやり取りから「意味のある数量の計算」へと導くことで、子どもの算数力は飛躍的に高まります。
「なぜそうなるの?」を考えさせる質問例
九九を言えるようになったあとに大切なのは、「その式がどうして成り立つのか」を子ども自身に考えさせることです。
暗記だけでは足りない“思考力”を育てるためには、「なぜそうなるの?」という問いかけが非常に効果的です。
かけ算は単なる計算ではなく、「数量の関係を表す式」です。
だからこそ、「何を何回くり返しているの?」「なぜその式を使うの?」という問いを通して、九九を使う“意味”を理解させることが重要です。
これにより、九九が“使える知識”として定着します。
具体的には以下のような質問が効果的です。
- 「この式は何を表しているの?」
- 「なんでたし算じゃなくて、かけ算を使ったの?」
- 「この“3”と“4”は、それぞれ何を意味しているの?」
- 「1個ずつだったら、どうなると思う?」
- 「同じ答えになる別の式はあるかな?」
こうした質問を日常的に投げかけることで、「九九は言えるけど使えない」状態から抜け出し、かけ算の本質的な理解につながります。
かけ算が苦手な子へのアプローチ方法

かけ算に苦手意識をもつ子には、「できない」ことを責めるのではなく、「どこでつまずいているか」を丁寧に見極めるアプローチが大切です。
九九が言えても、実際の問題になると手が止まる場合、「覚えたけれど使えない」という状態に陥っている可能性があります。
これは、かけ算の“仕組み”や“意味”の理解が十分でないために起こることです。
九九の暗記だけでは足りないと感じるとき、視覚化・対話・日常活用といった多角的な支援が必要になります。
机上の学習だけでなく、体験的な学びを取り入れることが、理解の土台づくりにつながるのです。
具体的には、学年別のサポート法・習得が遅れている場合の対処・発達特性に応じた工夫などがあります。
以下で、それぞれの視点から詳しく解説します。
つまずきの傾向と学年別サポート例
かけ算が苦手な子の多くは、学年ごとに異なる“つまずきポイント”を抱えています。
その子に合った段階的なサポートを行わないと、九九だけでは足りない理解不足が積み重なり、学年が上がるごとに算数嫌いが深刻化してしまいます。
つまずきの原因は、「九九を暗唱できても意味がわかっていない」「計算はできるけれど、式を立てられない」など様々です。
とくに3〜4年生では、文章題や図形問題を通して“かけ算の使い方”が問われるため、表面的な知識だけでは対応できません。
学年別のサポートでは以下のような視点が効果的です。
- 【1〜2年生】九九の暗記と並行して、絵や図を使った意味理解を
- 【3年生】式の意味や場面とのつながりを「言葉」で説明させる
- 【4年生以降】文章題・単位・図形との連動を意識した応用練習
以下に、「かけ算 九九 足りない」と感じる子どもへの学年別の具体的な支援方法を、1〜4年生に分けて丁寧に解説します。
各段階でのつまずきやすいポイントを押さえつつ、実際に使えるアプローチを紹介します。
【1〜2年生】九九の習得期:イメージと言葉で“意味づけ”する
つまずきやすいポイント:
「ただの音」として九九を丸暗記してしまい、意味が伴わない
数字の順序だけに頼り、逆に言えない・応用できない
支援の方法:
配列モデル(○を並べる)や絵カードを使って視覚化する
「3×4=12は、3人に4個ずつ配ったときの合計」と言葉で説明させる
日常の中でかけ算の場面を探し、一緒に「式にしてみよう」と声かけする
【3年生】応用・理解の転換期:式と場面を結びつける
つまずきやすいポイント:
九九を言えるのに、文章題になると式が立てられない
「なぜかけ算なの?」に答えられない
支援の方法:
式を作る前に「何を何回くり返してる?」「どんな場面?」と問いかける
式の数字に「単位(人・円・本など)」をつけて説明させる
“同じ式だけど意味が違う”体験(例:「3×4=12」でも“3人に4個”と“4列に3つ”では場面が異なる)を繰り返す
【4年生】文章題・図形との接続期:「使う力」の定着を
つまずきやすいポイント:
「式は立てられても、意味が理解できていない」
面積・割合・速さなど、新しい単元でかけ算を使いこなせない
支援の方法:
面積図や単位換算の演習で「なぜかけ算なのか」を一緒に確認する
「式を説明して」と求め、言語化によって論理的に整理させる
買い物・調理など実生活の中で応用体験を増やす(「100円の品を5個でいくら?」など)
かけ算は、九九を覚えるだけでは足りない“使う力”が問われる単元です。
こうした学年に応じた支援を行うことで、「できない」から「わかる」「使える」へのステップアップをサポートできます。
教科書の進度に合わせるのではなく、理解の深さに寄り添うことが何より大切です。
九九の習得が遅れている場合の対処法
九九の習得がクラスの平均より遅れていると、保護者も本人も不安を感じがちです。
しかし、九九が言えない=算数が苦手と決めつけるのは早計です。
焦らず、一人ひとりに合った進め方を見つけることが大切です。
九九が覚えにくい原因は、暗記の負担が大きいことだけでなく、「かけ算の意味」が十分に理解できていないことにもあります。
ただ繰り返すだけでは定着せず、「かけ算 九九 足りない」と感じるような状態に陥ってしまうのです。
効果的な対処法として、以下のような取り組みが挙げられます。
- リズム・歌・カードを活用して、楽しみながら定着をはかる
- 図や具体物を使って、九九の意味や構造を視覚的に理解させる
- 言える段から少しずつ応用へとつなげ、「使える感覚」を積み重ねる
以下で、それぞれの具体的な方法と実践例を詳しく解説します。
以下に、「九九の習得が遅れている場合の対処法」として紹介した3つの方法を、それぞれ具体的な実践例とともに詳しく解説します。
九九を“楽しく・意味をもって・使えるように”する工夫がポイントです。
リズム・歌・カードを活用して、楽しみながら定着をはかる
九九の暗記に抵抗を感じている子には、「覚えること=つらい」と思わせない工夫が大切です。
音・視覚・体のリズムを使って、遊び感覚で学ぶことが効果的です。
実践例:
九九のリズム歌(市販CDやYouTube動画)を毎日流して「耳からなじませる」
フラッシュカードを使って、テンポよく答える“ゲーム形式”で反復練習
「九九ビンゴ」や「九九カルタ」など、ルールのある遊びの中で自然に反復
→ 暗記に苦手意識がある子ほど、“楽しく覚える仕掛け”が有効です。
図や具体物を使って、九九の意味や構造を視覚的に理解させる
「数字だけで覚える」のではなく、見てわかる・手を動かして感じることで、かけ算の意味が深まります。
「九九は足りない」と感じる原因の多くは、これが抜けているためです。
実践例:
「3×4=12」を、3行4列の●を描いて確認(配列モデル)
おはじきや積み木を使って、同じ数を繰り返し並べる体験
紙にシールを貼って、「〇個を〇セット作ってみよう」といった作業型アクティビティ
→ 手や目を使った体感が、数のまとまりや構造理解を助けます。
言える段から少しずつ応用へとつなげ、「使える感覚」を積み重ねる
「全部言えない=ダメ」ではなく、できる段から“使う経験”を積ませることがモチベーション維持に効果的です。
実践例:
「2の段は言える」なら、2の段を使った文章題にチャレンジ
スーパーのチラシを使って、「100円のりんごを2個買ったら?」など実生活で活用
得意な段で「逆算」や「式作り」に発展させ、思考の幅を広げる
→ 「覚える」だけでなく「使える」感覚を早期に味わわせることで、自信につながります。
九九の習得が遅れていても、焦らずに“意味づけ”と“体験”を組み合わせたアプローチを取ることで、自然と定着していきます。
「かけ算 九九 足りない」と感じる子には、繰り返しよりも工夫の質が効果を生む鍵になります。
発達特性のある子に合う学習の工夫
発達特性のある子どもにとって、かけ算や九九の暗記は特に難しく感じやすいものです。
周囲と同じやり方ではうまくいかず、「九九が言えない=できない」と誤解されることもあります。
重要なのは、その子に合った方法で“わかる体験”を積ませることです。
視覚・聴覚・身体感覚など、得意な感覚を活かしたアプローチを工夫すれば、「かけ算 九九 足りない」と悩むことなく、少しずつ理解を深めていくことができます。
型にはまらず、本人のペースと興味を尊重する姿勢が何より大切です。
具体的な工夫として、以下のような方法が効果的です。
- 音楽や動画で耳から覚える九九ソングの活用
- 色やイラストを使った視覚的なカード・ポスター
- 体を動かしながら覚える「ステップ九九」「九九ダンス」
- 好きなキャラクターや興味あるモノを九九に組み込んだオリジナル教材
以下で、それぞれの方法をより詳しくご紹介します。
以下に、発達特性のある子に向けた「かけ算九九の学習を助ける4つの工夫」について、具体的な方法と活用ポイントを詳しくご紹介します。
どの方法も「九九が足りない」と感じる子の学びを支える実践的な工夫です。
音楽や動画で耳から覚える九九ソングの活用
特徴:
視覚よりも聴覚優位な子にとって、リズムやメロディは強力な記憶の補助になります。歌詞に九九の式をのせた「九九のうた」は、繰り返すだけで自然と頭に入ります。
活用方法:
YouTubeの「九九ソング」「九九リズムラップ」などを毎日少しずつ流す
朝の支度や移動中など、“ながら”で自然に耳に入る時間を活用
歌に合わせて手を動かす、拍をとるなど身体も使って記憶に残す工夫を加える
色やイラストを使った視覚的なカード・ポスター
特徴:
情報を視覚で捉える力が強い子には、絵・色・配置が記憶の手がかりになります。「九九カード」や「九九表」も、白黒ではなくカラフルにすることで効果が倍増します。
活用方法:
段ごとに背景色を変える「色分け九九表」で視認性をアップ
絵カードに「りんごが3個×2列で6個」など、絵と式をセットにする
自作カードを子どもと一緒に作ることで、内容への理解も深まる
体を動かしながら覚える「ステップ九九」「九九ダンス」
特徴:
じっと机に向かうのが苦手な子には、「動きながら覚える」方法が向いています。全身を使って九九を唱えることで、感覚記憶(体の記憶)が働き、学びが定着します。
活用方法:
数字ごとにジャンプや手拍子など動作を決めて唱える「ステップ九九」
テレビや動画に合わせて踊る「九九体操」や「九九エアロビ」もおすすめ
音楽や動作とセットで「式の流れ」を身体で覚える感覚を育てる
興味あるキャラクターや好きなテーマで九九を自分ごとに
特徴:
「興味関心」と九九をつなげることで、苦手意識を和らげ、自分ごととして学べるようになります。子どもの「好き」を学習に取り入れることは、主体性を引き出す鍵です。
活用方法:
好きなキャラクターが登場する「九九すごろく」「九九かるた」を自作する
鉄道・昆虫・スポーツなどのテーマで「3列×2席の電車は何人分?」などの問題を作る
スタンプラリー形式で「できた段から進めるゲーム性」を導入し、成功体験を積ませる
発達特性のある子どもには、「こうあるべき」という学習法より、「この子に合ったやり方」を見つけることが何より大切です。
九九の定着が遅くても、それは「方法が合っていない」だけのこと。
音・色・動き・好きなもの――どこかに必ず“突破口”があります。
柔軟な発想で、かけ算への扉を一緒に開いていきましょう。
九九以外に必要な「かけ算力」を育てる教材・アイデア

九九を暗記しただけでは、応用的なかけ算の問題に太刀打ちできません。
大切なのは、「考える力」と「使いこなす力」を育てる学びを取り入れることです。
単なる記憶ではなく、思考力としてのかけ算力を身につけることが、これからの学習を支えます。
理由は、学年が上がるにつれて文章題や図形、単位変換など“意味を理解して解く”かけ算が増えていくからです。
九九だけでは、かけ算の式をつくったり、実生活と結びつけたりする力まではカバーできません。
多角的な教材や声かけが求められます。
例えば、図形問題に強くなるドリル、Z会やRISUといった「考える力」に重点を置いた教材、さらに日常の中で「かけ算力」を育てる習慣づくりが有効です。
以下で詳しく解説します。
文章題・図形問題に強くなるドリル紹介
「かけ算 九九 足りない」と感じる背景には、文章題や図形問題への対応力不足があることが多いです。
九九の暗記はスタート地点に過ぎず、「読んで意味を捉え、式を立てる力」まで育てる必要があります。
これは、単に計算をするのではなく「なぜそのかけ算になるのか」を考える力が求められるからです。
文章の状況を図に表したり、式に置き換えたりする力がないと、正確な理解にはつながりません。
特に図形の面積や単位のかけ算では、九九だけでは不十分です。
おすすめのドリルは次のとおりです。
- 『教科書ぴったりトレーニング(教育出版)』:文章題の構造理解に効果的
- 『図形が得意になるドリル(学研)』:面積・長さなど図形と数の関係を視覚的に練習できる
- 『文しょうだいに強くなる かけ算編(くもん)』:文脈から式を組み立てる力を養う
それぞれのドリルについて「どのような特徴があるか」「どんな子におすすめか」「どのような力が育つか」を詳しく解説します。
『教科書ぴったりトレーニング(教育出版)』
特徴: 教科書の内容に完全準拠しており、文章題や図形問題にも段階的に取り組めます。
おすすめの子: 学校の授業内容をしっかり理解したい子、文章題が苦手な子に。
育つ力: 読解力、式の構造理解力、「何を聞かれているのか」を読み取る力。
『さんすう考具!図形ドリル ひらめき編』/『······天才編』(学研出版)
特徴: 坪田耕三先生監修、図形を手や頭で「使って考える」構成で、小学校全学年に対応した内容です。
新指導要領の教科書を作った“算数教材の神さま”坪田耕三先生が教える「図形」がよくわかる虎の巻。
頭で覚えず手で使って“見えない図形”が見えるようになり、図形問題が得意になる。「考具」<タングラム><ブロークンハート>を付録で収録。
おすすめの子: 図形問題に苦手意識がある子、視覚で理解する方が得意な子に。
育つ力: 空間認識力、かけ算の応用力、図と数値の対応をつかむ力。
『文しょうだいに強くなる かけ算編(くもん)小学1年から小学6年まで』
特徴: 「式の立て方をくりかえし練習できる」「細かいステップにより,難易度が急激に上がることを防ぎ,止まることなく学習することができる」という特徴により,学習の力を着実につけることができます。
おすすめの子: 九九は覚えたけれど、文章題でつまずく子に。
育つ力: 状況の把握力、計算の意味理解、かけ算の活用力。
Z会やRISUなど「考える力」を育てる教材
Z会やRISUなどの教材は、九九のその先にある「考える力」を育てるのに最適です。
単に正解を導くのではなく、なぜその式になるのか、どう考えて解いたのかを重視する設計が特長です。
「かけ算 九九 足りない」と感じたときに、思考力の土台作りとして効果的でしょう。
思考力系教材は、かけ算の意味を深く理解させ、「図を使って考える」「問題の条件を整理する」といった力を育てます。
九九の暗記だけでは対応しきれない文章題や図形問題に強くなる子どもを育てたい場合に、これらの教材はとても頼りになります。
以下で詳しく解説します。
Z会:論理的思考と文章読解を同時に伸ばす
Z会の算数教材は、教科書レベルを超えた「考えさせる問題」が豊富です。
たとえば、単に「4×3=12」ではなく、「4つの箱に3個ずつリンゴがあります。
1つの箱に2個食べられたら、残りはいくつ?」のように、複数の条件を整理しながら考える設問が多く出されます。
これにより、九九の結果を覚えているだけでは解けない応用力を自然に伸ばすことができます。
また、図や文章を正確に読み取る力も求められるため、国語力と算数力を同時に育成できる点も特徴です。
『Z会グレードアップ問題集 小学◯年 算数 計算・図形』
小学3〜6年生向けに発行されており、教科書+アルファの問題構成です。
図形理解や応用の文章題を含み、思考力・図の読み取り力・かけ算応用力を伸ばします。
パズル的な設問や複雑な条件整理を含む問題が豊富です。
RISU算数:AIが苦手を見抜き、思考力を伸ばす
RISU算数は、タブレット型の教材で、AIが学習履歴を解析し「どのタイプの問題でつまずいているか」を判断します。
九九ができても応用に弱い子どもに対して、ピンポイントで「なぜそれがかけ算になるのか?」という理解を深める問題を出してくれるのが大きなメリットです。
たとえば、「長方形の面積」や「倍の関係」を図と一緒に考えるステージでは、視覚的理解と思考の両方を必要とします。
これにより、ただの暗記では対応できない問題への対応力が身につきます。
RISU算数(タブレット教材)で購入できる教材名
- RISUきっず
年中・年長向けの無学年対応教材で、小学校低学年レベルの算数の基礎(数の読み書き・数感覚・九九の基礎など)を身につけることが可能です。詳細はこちら - RISU算数
主に小学生向けの算数専用タブレット教材。無学年制カリキュラムで、学年の枠を超えた先取りや苦手分野の復習に対応。かけ算の応用力や思考力を育てる問題設計が特徴です。
詳細はこちら
家庭でできる「かけ算の使い方」練習アイデア

かけ算の理解を深めるには、家庭での「使う練習」が欠かせません。
九九を覚えるだけでは不十分で、実際の生活の中でどのように活用できるかを体感することで、学びが定着していきます。
かけ算が身につくと、子どもたちは自信を持って問題に取り組めるようになるでしょう。
学校ではドリル中心になりがちな算数も、家庭ではもっと柔軟に「楽しく・実感できる形」で練習することが可能です。
買い物や料理、ゲームなど、日常の中にある“かけ算の種”を活かすことで、「九九だけでは足りない」力が育ちます。
買い物ごっこや料理を活用した実生活での応用
かけ算を「九九で覚える」だけでは、実生活で使いこなせる力は育ちません。
家庭での買い物ごっこや料理の時間は、かけ算を自然に使う絶好のチャンスです。
遊びや生活の中で繰り返し使うことで、「九九はわかるけど足りない」という状態から抜け出せるでしょう。
なぜなら、実際の買い物や料理では「単価×個数」や「分量×人数」など、かけ算の意味を理解していないと対応できない場面が多くあるからです。
数字に触れ、考える機会を与えることで、応用力がぐんぐん育ちます。
「かけ算は便利!」を実感できる体験を与える
九九を覚えただけでは、「かけ算って便利!」という実感にはつながりません。
子どもがかけ算を本当に理解し、「使える力」として身につけるには、日常生活の中で“便利さ”を体験することが大切です。
九九がわかっていても足りないと感じる背景には、この実感の不足があるのです。
たとえば、「友だち5人に3個ずつお菓子を配る」場面で自然と出てくるかけ算。
こうした場面に出会うことで、子どもは九九の意味や使いどころを体で理解し、学びが深まります。
親子で楽しめるアプリ・ゲーム活用法
かけ算や九九の理解が足りないと感じたとき、親子で楽しめるアプリやゲームの活用が効果的です。
遊び感覚で取り組める教材は、学習へのハードルを下げ、繰り返し練習につながりやすくなります。
家庭での取り組みとしても継続しやすく、親子のコミュニケーションのきっかけにもなります。
子どもが苦手意識を持ちやすい「かけ算」も、ゲームやアプリを使えば自然と反復でき、九九の定着や応用力の強化にも役立ちます。
特に、楽しさを感じると「もっとやりたい」という自主性も引き出せるのが大きなメリットです。
よくある質問(Q&A)
Q1. 九九が完璧でもテストで点が取れないのはなぜですか?
A. 九九を覚えることと、それを実際の問題で使いこなす力は別物です。
とくに文章題や図形の問題では、「何の数をかけているのか」という意味理解がないと正しい式を立てられません。
計算だけでなく、状況を読み解く力も必要です。
Q2. かけ算の意味を家庭で教えるとき、何から始めればいいですか?
A. まずは「同じ数をいくつ分」という考え方を、具体物を使って体験させることがおすすめです。
たとえばお菓子を使って「3個入りの袋が4つあると全部で何個?」など、身近な場面で会話しながら教えると自然に理解が深まります。
Q3. 子どもが「かけ算は嫌い」と言い出したらどうすればいい?
A. 無理に覚えさせようとせず、楽しい遊びや体験を通して「かけ算って便利だね」と感じられる機会をつくることが大切です。
ゲームやアプリ、買い物ごっこなどを通じて、「嫌い」から「ちょっと面白いかも」へと気持ちを切り替えてあげましょう。
Q4. 九九を間違えるたびに叱ってしまいます。どう声をかければいいですか?
A. 間違いを責めるのではなく、「どうしてその答えになったのか教えて?」と聞くことで、子ども自身の思考に寄り添う姿勢が伝わります。
正解を教えるよりも、「考え方を一緒に見直す」声かけが効果的です。
まとめ:九九の「その先」を教えてこそ本当のかけ算力
九九を覚えるだけでは、かけ算の力は不十分です。4年生までに必要なのは、「九九を使って考える力」を育てること。
数の意味や関係を理解し、実生活や文章題に応用できるようになることが本当のゴールです。
なぜなら、かけ算は暗記だけで完結する単元ではないからです。図形の面積や割り算、単位量の理解など、学年が上がるほど「かけ算の意味を使いこなす力」が求められます。
九九が「足りない」と言われるのは、その先の応用が難しくなるからです。
九九を基礎としつつも、「なぜこの式になるのか」「どう使えばいいのか」を考える経験が、算数の力を大きく伸ばします。
九九のその先にある「本当のかけ算力」を、今こそ意識して育てていきましょう。

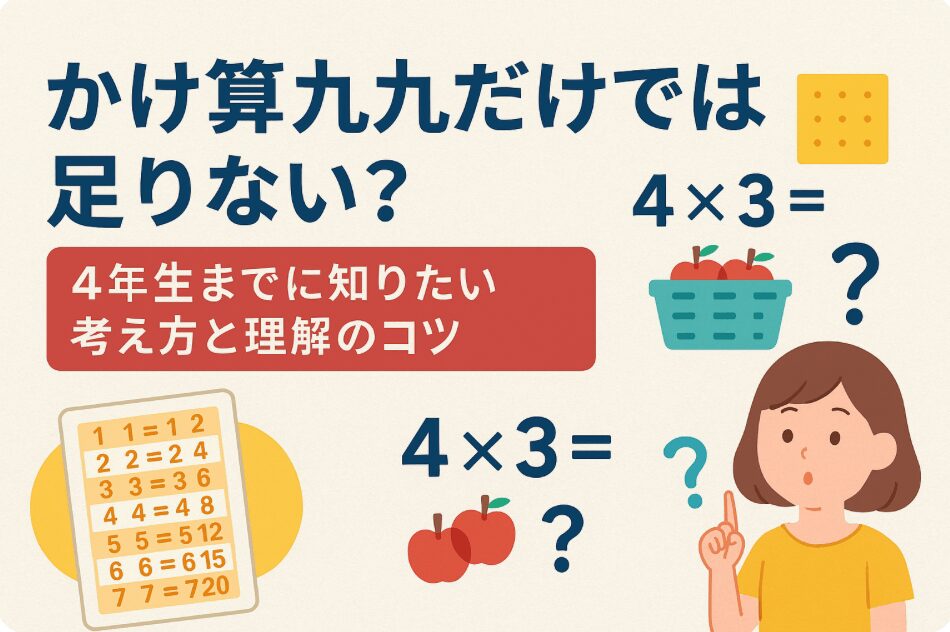

















コメントを残す