中学受験の準備、何から始めればいいのか迷っていませんか?
「今のペースで大丈夫?」「周りはどこまで進んでるの?」そんな不安を感じる保護者の方も多いはず。
実は、小5・小6の1年間にはそれぞれ意味があり、どの時期に何を重点的に取り組むかが合否を分けるポイントになります。
中学受験の算数、どの参考書を選べばいい?」
迷ったらこちらの記事をチェック!お子さんにピッタリの算数参考書が見つかります。
👉 [中学受験おすすめ算数参考書まとめ]
最近、中学受験を成功させるために、塾に通う以外の選択肢としてオンライン家庭教師が注目されています。
オンライン家庭教師って実際どうなの? メリット・デメリットや活用法を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください!
👉 オンライン家庭教師 中学受験|メリット・デメリットから選び方・活用法まで徹底解説!
💭「親として、どこまで関わればいいの?」「子どもがやる気を失ってきてる…」
特殊算の勉強だけでなく、日々の学習サポートそのものに不安を感じている方へ。
今話題のAI・ChatGPTが、実は中学受験家庭の“心強い味方”になるんです。
目次
中学受験の準備はいつから始めるべき?
中学受験の準備は、小4から塾に通い始めるご家庭が多いですが、本格的に学力を伸ばしていくのは小5から。
小6では過去問や志望校対策など実戦力を問われる学習が中心になります。
小5でしっかり基礎を固め、小6で応用・実戦へ進むのが合格への王道ルートです。
中学受験|小5の年間スケジュールと学習のポイント
小学5年生は、中学受験に向けて本格的な学習習慣を確立する重要なステージです。
この1年間でどれだけ基礎学力を高め、苦手分野を克服できるかが、小6での応用学習や志望校対策の成果に直結します。
また、学習面だけでなく、家庭での声かけや学習環境の整備など、親のサポートも非常に大きな意味を持ちます。
塾の授業や模試を通じて、徐々に自分の得意・不得意が明確になる時期でもあるため、ただ学習時間を確保するだけではなく、「中身の濃い学習」を目指す必要があります。
春(4月〜6月):学習習慣と基礎力の定着
新学年が始まる春は、学習習慣を固める絶好のタイミングです。
この時期に毎日の家庭学習リズムを確立できれば、その後の学習がスムーズに進みます。
まずは、計算問題や漢字練習、読解力を鍛える音読など、基礎学力の定着に重点を置くことが効果的です。
また、塾のカリキュラムも本格化していくため、授業で習った内容をその日のうちに復習する習慣も必要です。
学習時間の目安としては、平日90分、休日は2〜3時間が理想的とされています。
家庭では、勉強の進捗を見える化する「学習チェックリスト」などを活用すると、子どもの学習意欲を高める助けになります。
夏(7月〜8月):苦手克服と復習強化
夏休みは、時間を確保しやすく集中して学習に取り組める時期です。
特にこの時期は、これまでの学習内容を復習し、苦手分野の洗い出しと克服を進めることが大切です。
塾の夏期講習では、基礎から応用への橋渡しとなる演習問題が増え、思考力が求められる課題にも取り組むようになります。
家庭では、過去の模試や確認テストを見直し、「どの単元でミスが多いか」を具体的に分析することが必要です。
また、朝型の学習リズムに切り替えることで、夏休み明けの生活にもスムーズに移行できます。
保護者は学習内容だけでなく、生活リズムの管理や心のケアも意識して関わるようにしましょう。
秋(9月〜11月):実力チェックと応用学習
秋は、小5の学習が一段階ステップアップする時期です。
塾でも応用問題が増え、単なる暗記では対応できない、論理的思考力や問題解決力が求められる場面が増えてきます。
この時期に実施される模試(合不合判定テストなど)では、自分の学力位置を客観的に把握でき、志望校選定の材料にもなります。
重要なのは、模試の結果に一喜一憂せず、間違えた問題の原因をしっかり分析して次に活かすことです。
また、志望校の出題傾向を少しずつ調べ始めると、来年度の学習計画が立てやすくなります。
家庭では、子どもが問題に取り組む姿勢を観察し、集中力や理解度に合わせて適切な声かけを意識することが大切です。
冬(12月〜3月):小6に向けた準備
小5の冬から小6にかけては、受験モードへの移行準備期間です。
この時期には、これまで学習してきた単元の「総まとめ」を行い、知識の定着度を確認することが求められます。
特に算数・国語は得点差がつきやすい科目のため、基本問題を確実に解ける力を身につけておくことが合格への近道です。
また、冬期講習では応用問題も多く出題されるため、問題に対するアプローチ方法を一緒に整理しておくことも効果的です。
家庭では、春から始まる志望校対策に備えて、通学可能圏や学校の教育方針などを整理し、受験校の候補をある程度決めておくと、学習の目的意識が明確になります。
この時期に親子で目標を共有できるかどうかが、小6でのモチベーションを大きく左右します。
中学受験|小6の年間スケジュールと学習のポイント
小学6年生は、中学受験本番に向けた仕上げの1年です。
この1年間は、基礎の確認から志望校別対策、過去問演習、併願校の選定、直前期の調整まで、やるべきことが一気に増えていきます。
小5までの学習成果をどう活かし、どのタイミングでどんな対策を進めるかによって、受験結果が大きく左右されます。
🔍具体的な解説:
小5までに積み重ねてきた学習は、いわば中学受験の“基礎工事”です。
この基礎がしっかりしていれば、小6での応用学習・過去問演習にスムーズに移行できます。
逆に、基礎に抜けがあるまま小6に入ると、応用問題に対応できず成績が伸び悩むケースが非常に多く見られます。
たとえば、算数の「割合」「速さ」「比」などは、小5で習得しておくべき重要単元です。
これらが不安定なまま小6の応用問題に取り組むと、「問題の意味はわかっても、式が立てられない」「計算に手間取り時間が足りない」といった壁に直面します。
したがって、小6の春〜夏前までに、小5の学習内容を一度総点検し、苦手な単元は早期に克服しておくことが必須です。
この段階での「弱点潰し」ができているかどうかが、夏以降の過去問演習や志望校別対策の成果に直結します。
さらに、成績を上げやすい子の多くは、「どの時期に何をやるべきか」が明確になっており、計画的に進めています。
たとえば、小6の4月〜6月で基礎の再確認、小6夏で応用・演習、小6秋からは過去問中心というように、段階的な学習戦略を組み立てることが合格への近道になります。
また、学習だけでなく、メンタル面や生活リズムの安定、家庭の関わり方も合否に影響を与える重要な要素となります。
各時期での目的を明確にし、計画的に取り組むことで、焦りのない受験準備が実現できます。
春(4月〜6月):志望校決定と学習の土台固め
新年度のスタートとともに、志望校の方向性を具体化していく時期です。
小5で積み上げた基礎学力を確認しつつ、苦手単元の早期克服に集中することが求められます。
塾でも志望校別クラス編成や対策講座が始まる場合が多く、自分の立ち位置や強化すべき教科が明確になります。
また、模試の結果を活用し、出題傾向に合った学習内容へと軌道修正していくことが必要です。
家庭では、「どんな学校に通いたいか」「通学時間や校風はどうか」などを親子で話し合うことで、学習のモチベーションも上がります。
この時期に目標がはっきりしている子ほど、夏以降の伸びが加速します。
夏(7月〜8月):受験勉強のピーク・演習中心へ
夏休みは、受験勉強の最大の山場です。
この時期には演習量を大幅に増やし、実戦形式の問題に多く触れることで、得点力を高めていきます。
過去問を使った学習も本格化し、志望校の出題傾向を実感しながら、自分の得意・不得意を明確にしていきます。
また、夏期講習では応用・難問演習が中心となり、スピードと正確さの両立が求められます。
家庭では、演習の“質”を高めるために、ミスの原因分析・解き直し・時間配分の確認を日々行いましょう。
同時に、集中力を持続させるためには休憩・運動・栄養管理も意識する必要があります。
体力面・精神面のケアは、保護者にしかできない大切な役割です。
秋(9月〜11月):志望校・併願校の最終決定と実戦力強化
秋は、実戦力を高めながら志望校・併願校を最終決定する重要な時期です。
塾では本番形式の模試が増え、実際の入試を想定した問題に取り組む機会が多くなります。
この段階では「合格点を取る学習」が必要です。
得点源となる単元に集中し、確実に得点できる問題の精度を上げることが求められます。
過去問演習では「何点取れているか」だけでなく、「時間内にどう解くか」も意識してください。
また、併願校については、入試日程・出題傾向・通学距離などを具体的に比較し、家庭で最終判断を行いましょう。
保護者の冷静なサポートが、受験生の精神的安定につながります。
冬(12月〜1月):入試直前対策と心の準備
いよいよ入試本番が目前に迫る時期です。
この期間は、今までの学習内容を総仕上げし、得点源の最終確認を行います。
新しい内容を詰め込むより、自信を持って解ける問題を確実に得点できるようにすることが大切です。
また、本番に向けた時間配分の練習、当日の持ち物チェック、健康管理も忘れてはいけません。
直前期は、不安やプレッシャーで精神的に不安定になることもあります。
保護者は「できているところを褒める」「一緒に深呼吸する」「いつも通りを大切にする」など、小さな工夫で子どもを支えましょう。
最終的には、これまで努力してきた積み重ねが自信になります。
中学受験|年間スケジュールを見える化しよう|一目でわかる学習の流れ
中学受験に向けた学習を効果的に進めるためには、「いつ・何を・どのように取り組むか」を家族全体で共有することが重要です。
とくに小5・小6の2年間は、塾のカリキュラムも複雑になり、模試や講習、志望校対策など多くのタスクが重なっていきます。
そのため、年間スケジュールをあらかじめ“見える化”しておくことで、やるべき内容が明確になり、受験に向けた学習計画をブレずに進めることができます。
計画的な学習はお子さんの不安を減らし、保護者にとっても精神的なゆとりをもたらします。
以下に、小学5年生・6年生それぞれの時期ごとの学習目標と家庭でのサポートのポイントを表形式で整理しました。家庭での学習管理にぜひお役立てください。
中学受験小5・小6年間学習スケジュール表(参考例)
| 時期 | 学習の目標 | 塾・模試の動き | 家庭でのサポートポイント |
|---|---|---|---|
| 小5 春(4〜6月) | 学習習慣の定着・基礎力の確認 | 塾授業開始・確認テスト・面談 | 学習リズムの安定化・毎日の声かけ |
| 小5 夏(7〜8月) | 苦手単元の整理と復習強化 | 夏期講習・塾内模試・復習テスト | 過去のミス問題の解き直し・生活リズム調整 |
| 小5 秋(9〜11月) | 応用問題に対応する思考力育成 | 合不合判定テスト・講習 | 模試分析・志望校情報収集のスタート |
| 小5 冬(12〜3月) | 総まとめ・小6への移行準備 | 冬期講習・模試・個別面談 | 志望校候補の検討・次学年の学習計画共有 |
| 小6 春(4〜6月) | 志望校決定と基礎の再確認 | 塾カリキュラム強化・志望校別講座開始 | 苦手単元の早期克服・情報収集の具体化 |
| 小6 夏(7〜8月) | 応用力・実戦力の定着 | 夏期講習・過去問演習開始・模試 | 時間配分練習・過去問進捗管理・メンタルケア |
| 小6 秋(9〜11月) | 志望校仕上げ・併願校調整 | 志望校別模試・過去問演習本格化 | 学習成果の定着・家庭での目標確認 |
| 小6 冬(12〜1月) | 直前対策・入試本番準備 | 最終講習・本番形式演習・入試本番 | 健康管理・当日の流れ確認・声かけ支援 |
このスケジュール表を活用すれば、各時期にどのような学習テーマに取り組むべきかが明確になります。
また、保護者が学習の進捗状況を見える化することで、お子さんも安心して学習に取り組むことができます。
📖【体験談】「計画が見えたことで、親子で前向きに」
小5の夏休みに入った頃、うちは完全に行き当たりばったりの勉強でした。
毎日とりあえずドリルをこなしているだけで、「本当にこれでいいのかな…」と不安ばかり。
そんなとき、年間スケジュールを立てて、月ごとの目標を書き出してみたんです。
見える化することで、子どもも「今はこれに集中すればいい」と落ち着いて取り組めるようになりました。
振り返ると、「今、何をしているか」を親も子も明確にできたことが、何より大きな支えになったと思います。
💡 家庭での学習をもっとスムーズに!
この記事で紹介した「年間スケジュール&チェックリスト」をPDFで無料配布中!
「今やるべきこと」が一目でわかると、迷わず受験準備を進められます✨
📩 メルマガ登録で今すぐダウンロード!
🎁 【特典内容】
✅ スケジュール管理に役立つチェックリスト付き
✅ 何を・いつ・どこまでやるべきかが明確に!
✅ 受験生の親が実際に活用している貴重な資料
\今すぐ無料でダウンロード /
📩 メルマガ登録でスケジュールPDFを無料GET!
中学受験準備に役立つ「年間スケジュール&チェックリスト」PDFをプレゼント中です。
今の学習の進め方に迷っている方は、ぜひこの特典をご活用ください。
受験スケジュールを上手に活用するためのコツ
中学受験の成功には、計画的なスケジュール管理が欠かせません。
特に小5・小6では、塾の授業や模試、講習、家庭学習など、こなすべきタスクが急増します。
学習内容が難しくなる一方で、家庭のサポートが学習の質を大きく左右します。
この時期は「中学受験 小5・小6でやるべき年間スケジュール」を元にした進捗管理を徹底することで、迷いや焦りを減らすことが可能です。
具体的には、日々の学習状況を見える形で管理し、模試や講習の予定を事前に整理しておくことが効果的です。
また、勉強ばかりに偏らず、子どもの心と体のバランスを整える工夫も受験を乗り切る大切な鍵になります。
【塾長の声】「成績が伸びる子ほど、スケジュール管理が上手です」
私たちが日々見ている中で感じるのは、「学力が伸びる子には共通点がある」ということです。
それは、学習のリズムと目標が明確であること。
単元別に「いつ」「どこを」「どのくらい」学ぶかが明確な子ほど、無駄が少なく、伸び方も加速します。
逆に、ただ時間を費やしているだけの学習は、どうしても成績に結びつきにくいです。
年間スケジュールを軸に、模試や講習を戦略的に組み合わせることで、家庭でも実践的な学習が可能になります。
スケジュール表で進捗管理
年間スケジュールは作成するだけではなく、日々の学習状況に合わせて「進捗を確認する」ことが重要です。
スケジュール表には、各単元の達成状況や模試の振り返り内容を記録しておくと、見直しの際に非常に役立ちます。
たとえば「今週の目標は計算単元の演習100問」「国語の記述問題10問復習」など、数値で具体化することで達成感も得られやすくなります。
保護者が一緒にチェックすることで、子ども自身も学習への意識が高まります。
チェックリスト方式やシール式など、家庭ごとに続けやすいスタイルを取り入れるのがコツです。
模試・講習の予定を先に決めておく
受験スケジュールの中でも、模試や講習の日程は早めに決めておくことで、学習リズムが安定します。
特に小6では「志望校別模試」や「実戦演習講座」など、イベント的な内容も多く、スケジュールが埋まりやすくなります。
模試のスパンに合わせて復習のタイミングも組み込んでおくと、理解の定着がスムーズになります。
また、夏期講習・冬期講習の日程は塾から早期に案内されるため、家族の予定と重ならないように調整が必要です。
あらかじめ年間予定表に書き込んでおけば、直前で慌てることがありません。
月ごとの目標&振り返り時間を親子で共有
毎月のはじめに「今月の学習目標」を決めておくと、学習にメリハリが生まれます。
たとえば「9月は算数の割合・比を重点強化」「10月は理科の記述対策に集中」といったテーマ設定が効果的です。
また、月末には親子で「どこがうまくいったか」「次に強化すべき点はどこか」を振り返る時間を取りましょう。
この共有時間は、子どものモチベーション維持だけでなく、保護者の気づきを得る場にもなります。
記録を残しておくことで、成長の軌跡を見返すこともでき、学習への自信につながります。
学習以外のことも大切に(休息・趣味・気分転換)
中学受験の学習は、精神的な負担も大きくなりがちです。
長時間勉強に向き合っていると、集中力が切れたり、ストレスが蓄積されたりすることがあります。
そのため、意識的に「休息時間」「気分転換の時間」を設けることも、学習効率を高めるうえで非常に重要です。
たとえば、週に1回は趣味の時間を取り入れる、短時間でも散歩や音楽で気持ちを切り替えるなど、小さな工夫が効果を発揮します。
「意識的に『休息時間』『気分転換の時間』を設けることが学習効率を高める」ことの具体例を、中学受験生の実際の家庭で取り入れられている工夫としてご紹介いたします。
あるご家庭では、「45分集中 → 10分休憩」という学習リズムを習慣化しています。
休憩の10分間は、好きな音楽を聴いたり、軽くストレッチをしたり、おやつタイムにするなど、学習から頭を切り替える時間にあてています。
こうすることで、次の学習もリフレッシュした状態で集中でき、ダラダラと続けるよりも学習効率が高まるそうです。
毎日学習を続けると、どうしても疲れが蓄積されていきます。
あるご家庭では、**週に1日は「勉強しない日」**をあらかじめ予定に組み込んでいます。
その日は映画鑑賞や家族で外食、ショッピングなど、受験から意識的に離れる時間にしているとのことです。
子ども自身も「リフレッシュできるから頑張れる」と話しており、精神的な安定につながっています。
モチベーション維持のために、「休憩中にやりたいことリスト」を子どもと一緒に作成しているご家庭もあります。
たとえば「折り紙を折る」「お気に入りのYouTube動画を1本だけ見る」「絵を描く」など、ちょっとした息抜きになることを選ぶのがポイントです。
計画的に“楽しみ”を取り入れることで、学習も前向きに取り組めるようになります。
受験を乗り越えるには、体力・メンタル・生活リズムすべてが整っていることが理想です。
保護者の配慮が、子どものバランスの取れた受験生活を支える大きな柱になります。
中学受験|小5・小6でやるべき年間スケジュール完全ガイドに関するQ&A
中学受験を控えた小5・小6の保護者の方の多くが、「年間スケジュール通りに進められるか」「日々の勉強時間は足りているか」など、さまざまな疑問や不安を抱えています。
このQ&Aでは、「中学受験 小5・小6でやるべき年間スケジュール」にまつわる代表的な悩みに対して、専門的な視点からわかりやすく解説します。
実際の受験生家庭でも多く寄せられる相談をもとに、現実的で実践的なアドバイスをお伝えします。
- 小5・小6の勉強時間はどれくらいが理想ですか?
- スケジュール通りに進まなかったらどうすればいい?
- 習い事と受験勉強は両立できますか?
- 親が口を出しすぎると逆効果になりませんか?
- 親が口を出しすぎると逆効果になりませんか?
小5・小6の勉強時間はどれくらいが理想ですか?
小5の場合、平日は1〜2時間、休日は3〜4時間程度が平均的な学習時間です。
小6になると徐々に学習時間を増やし、平日は2〜3時間、休日には5時間以上を目指すご家庭も多くなります。
ただし、時間だけを重視するのではなく、「何を、どのように学んだか」を振り返ることが重要です。
特に小6では、過去問演習や志望校別対策が加わるため、時間配分と内容のバランスが求められます。
勉強時間を決める際は、塾の授業時間と家庭学習の比率も意識すると、無理なく継続しやすくなります。
スケジュール通りに進まなかったらどうすればいい?
年間スケジュールはあくまで“理想の道筋”であり、実際には予定通りに進まないこともよくあります。
その場合は焦らず、優先順位を見直すことが第一です。
「苦手単元の克服」や「得点源の強化」など、効果の高い項目から再調整することで、学習の質を落とさずに軌道修正できます。
また、週単位・月単位での小さな目標設定に切り替えると、達成感を持ちながら前に進めます。
スケジュールにこだわりすぎず、柔軟に対応する姿勢が、家庭学習の安定につながります。
習い事と受験勉強は両立できますか?
小5の段階では、習い事と受験勉強の両立は十分に可能です。
むしろ、音楽・スポーツ・アートなどの活動は、子どもの心身のバランスを整える効果もあります。
ただし、小6になると学習量が増加し、習い事との両立が難しくなるケースが多くなります。
その場合は、習い事の回数を減らす・一時的に休止するなど、家庭ごとに無理のない形を選ぶことが大切です。
習い事の継続は「気分転換」として有効である一方、学習の負担になってしまう場合は調整が必要です。
お子さん自身の様子を見ながら、学習とのバランスを保っていきましょう。
親が口を出しすぎると逆効果になりませんか?
保護者の関わり方は、子どもの学習に大きく影響します。
ただし、過度な干渉はプレッシャーや反発の原因になることもあります。
重要なのは「管理する」のではなく、「見守る」姿勢です。
たとえば、「もう勉強したの?」という言葉よりも、「頑張ってるね、今日どんなことやったの?」と声をかけるほうが、子どものやる気を引き出しやすくなります。
また、家庭では学習内容に立ち入るよりも、学習環境の整備や感情面のサポートに力を入れると効果的です。
お子さんの自主性を大切にしつつ、安心して学べる空気づくりが家庭の役割になります。
スケジュール通りやっても成績が上がらないこともあります。原因は?
「頑張っているのに成果が出ない」と感じる場合、その原因は“学習の質”にあることが多いです。
スケジュール通りに進めていても、理解が不十分なまま進んでいると、知識が定着せず点数に結びつきません。
特に小6では、ただ問題を解くだけではなく、「なぜその答えになるのか」を自分の言葉で説明できるレベルを目指す必要があります。
また、復習不足やアウトプット不足も、成績停滞の要因になります。
学習記録やテストの見直しを通して、どの単元が弱いのか、どの解き方が非効率なのかを見極めましょう。
学習スタイルを少し変えるだけでも、大きな成果につながることがあります。
まとめ:中学受験|年間スケジュールを見える化すれば、不安は自信に変わる
中学受験の学習は、ただ時間をかけるだけでは成果につながりません。
小5・小6という大切な2年間をどのように過ごすかが、合否を分ける最大のポイントです。
今回ご紹介した年間スケジュールの流れをもとに、各時期での学習目標や家庭でのサポートを明確にしておけば、焦ることなく受験準備を進められます。
特に、「今は何をやるべきか」が見えていれば、お子さんの学習意欲も高まり、保護者も安心して支えることができます。
計画通りに進まないことがあっても大丈夫です。
振り返りと調整を繰り返しながら、親子で一歩ずつ進んでいくことが、最も大切な受験対策になります。
無理のないペースで、着実にステップアップできるよう、ぜひ今回のスケジュール表やチェックリストを活用して、家庭での学習を見える化してみてください。
お子さんの6年間を決める大切な受験。
一番の支えは、そばで見守る保護者の存在です。
心を整え、家庭を整えるところから、受験の準備は始まります。
中学受験の算数、どの参考書を選べばいい?」
迷ったらこちらの記事をチェック!お子さんにピッタリの算数参考書が見つかります。
👉 [中学受験おすすめ算数参考書まとめ]
最近、中学受験を成功させるために、塾に通う以外の選択肢としてオンライン家庭教師が注目されています。
オンライン家庭教師って実際どうなの? メリット・デメリットや活用法を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください!
👉 オンライン家庭教師 中学受験|メリット・デメリットから選び方・活用法まで徹底解説!
「このままでいいのかな」と不安になる夜に。
中学受験を“がんばる親”に向けた無料メールレッスン、はじめました。
➤ ChatGPTと対話しながら、気持ちを整える6日間。
📩 保護者の心に寄り添う、無料メール講座(全6回)を始めませんか?
ChatGPTと一緒に、イライラ・不安・親子のすれ違いを少しずつ整えていく6日間。
特典PDFもプレゼント中です。
よく読まれている記事TOP5!

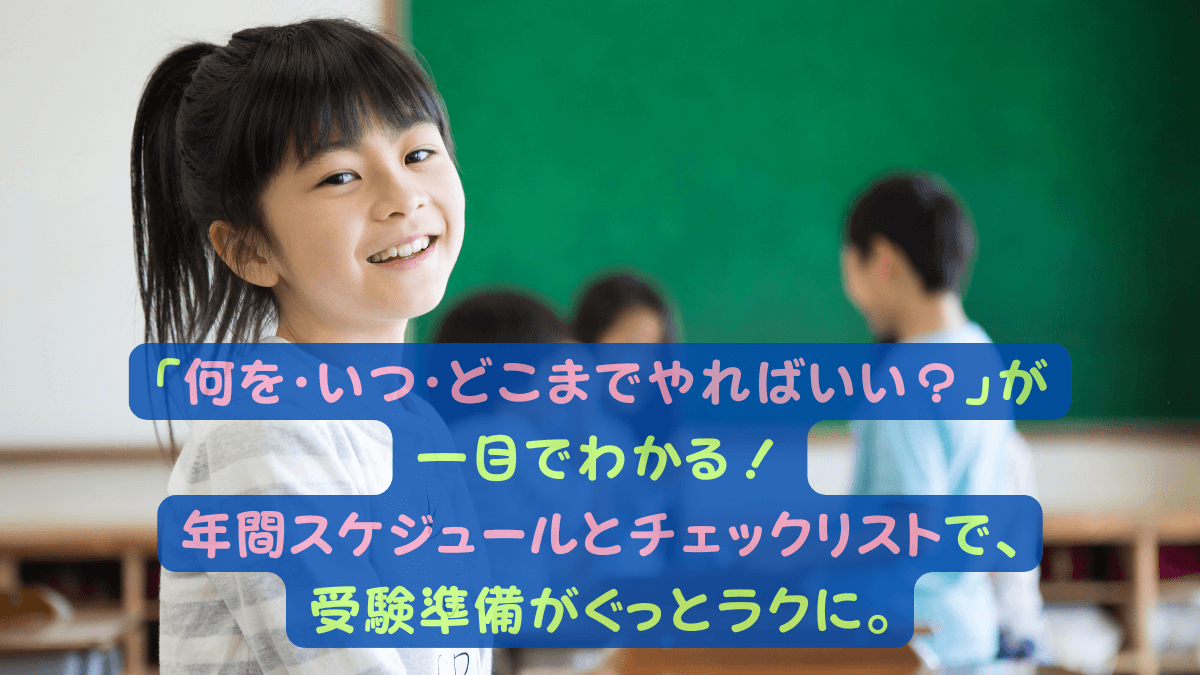






















📖【事例紹介】親子で目標を共有して前向きに走り抜けたご家庭の話