中学受験に向けた家庭学習を進める中で、「子どもがつまずいたときにどう教えればいいのか」「毎日の学習管理に限界を感じる」といった悩みを抱えている保護者の方も多いのではないでしょうか。
そんなご家庭にいま注目されているのが、AIを活用した“第2の先生”、ChatGPTです。
この記事では、中学受験家庭におけるChatGPTの具体的な使い方から、効果的な活用法、注意点、そして実際に使ってみて感じる変化までをわかりやすく解説します。
小学6年生の保護者の方に向けて、無理なく・楽しく・効果的に家庭学習を進めるヒントをお届けします。
- ChatGPTとは何か、初心者向けにわかりやすく理解できる
- スマホやパソコンで、無料で使い始める方法
- 中学受験の家庭学習でChatGPTを「家庭教師」として使う具体的な方法3選
- 作文添削や理科の実験解説など、応用的な活用アイデア
- 子どもに任せきりにしない、保護者が気をつけるべきポイント
- ChatGPTを「一緒に考えるツール」として使うための視点
- 時間の使い方や学習記録など、家庭内でのルールの作り方
- ChatGPTを活用したことで起きた家庭学習の変化(親の負担軽減・子どもの成長)
- 親子の会話が増え、学習ペースが安定するメリット
- AIを“味方”として取り入れるための考え方と姿勢
💭「親として、どこまで関わればいいの?」「子どもがやる気を失ってきてる…」
特殊算の勉強だけでなく、日々の学習サポートそのものに不安を感じている方へ。
今話題のAI・ChatGPTが、実は中学受験家庭の“心強い味方”になるんです。
目次
塾なし中学受験でも家庭学習で合格できる?家庭が抱える不安と課題

近年、「中学受験 家庭学習」を選択するご家庭が増えています。
塾に通わず、家庭中心で受験対策を進めるスタイルは、子どもの生活リズムに合わせやすく、移動時間の削減や保護者の関与による安心感など、数々のメリットがあります。
しかしその一方で、「この方法で本当に合格できるのか」「学習の進め方がこれで合っているのか」といった不安を抱える保護者が急増しています。
特に小学6年生のこの時期は、受験本番までの時間が限られており、計画性を持った学習スケジュールの管理が必要不可欠になります。
塾に通わない場合、模試や進捗管理の仕組みが不足しがちで、保護者が「指導役」として多くの責任を担うことになります。
そのため、情報収集や教材選び、学習計画の立案・見直しといった役割をすべて家庭内で担わなければならず、負担を感じる方も少なくありません。
一方で、家庭学習の魅力を最大限に活かせば、子どもが自分のペースで自学自習する力や思考力を伸ばすことも可能です。
塾とは異なるアプローチで、合格に必要な実力を養う道も確かに存在しています。
では、塾に頼らない中学受験において、どのような課題が立ちはだかるのでしょうか。
ここからは、特に多くのご家庭が悩む2つの現実的な問題について具体的に見ていきます。
「塾代が高すぎる…」という現実的な理由
中学受験における塾の年間費用は、一般的に80万円〜100万円以上と言われています。
6年生の後期になると、志望校別の特訓講座や直前講習が加わり、月額で10万円を超えるケースも少なくありません。
このような高額な出費は、家計に大きなインパクトを与えるため、「塾に通わせたいけれど、現実的に厳しい」と悩む家庭も多く見られます。
その結果、「費用を抑えながらも質の高い家庭学習による受験対策ができないか」と考える保護者が増えています。
近年では、スタディサプリやYouTubeなど、低コストで利用できるオンライン教材や動画講座も充実しており、自宅での学習環境を整える選択肢は確実に広がっています。
しかし、こうしたツールを最大限に活用するには、保護者自身が教材を選び、子どもに合った学習計画を立てて伴走する力が求められます。
通塾しない=孤独になりやすい家庭学習
塾では、同じ目標を持つ仲間たちとともに学び、切磋琢磨できる環境が自然と整います。
これに対して家庭学習では、子どもが一人で机に向かう時間が増え、「自分だけが孤独に頑張っている」と感じることがあります。
特に小学6年生の後半は、精神的にも不安定になりやすい時期。
周囲の友達が塾の話題で盛り上がる中、自分だけが自学自習で勉強しているという状況は、モチベーションの低下や自己肯定感の低下にもつながりかねません。
また、保護者が常に学習を見守れるとは限りません。
仕事や家事で忙しく、「気づいたら放任状態になっていた」と感じる家庭も少なくないのです。その結果、思考力を育てるプロセスが不十分になり、表面的な学習に偏ってしまう危険性も出てきます。
こうした事態を防ぐためには、家庭内だけで完結せず、外部とのつながりや定期的な振り返りの場を設けることが効果的です。
たとえば、オンライン学習グループへの参加、SNSでの情報交換、ChatGPTなどのツールによる“対話型学習”の導入など、孤立を防ぐ工夫が重要です。
そんなときに頼れる“第2の先生”|ChatGPTで家庭学習と受験対策をもっとスムーズに

中学受験に向けた家庭学習では、「子どもがつまずいたときにどう教えればいいのか」「親が忙しくて毎日つきっきりにはなれない」といった悩みがつきものです。
特に塾に通わずに自宅中心で受験対策を行っているご家庭では、保護者が抱える負担は決して小さくありません。
そんなときに頼りになるのが、AIによるチャット型の学習支援ツール「ChatGPT(チャットジーピーティー)」です。
ChatGPTは、子どもが入力した質問に対して、まるで家庭教師のようにやさしく・ていねいに答えてくれるAIです。
24時間いつでも使えるため、「わからない」をその場で解消しやすく、子どもの“自学自習力”を自然に育てるツールとして注目を集めています。
中学受験では、思考力・記述力が求められる問題が増加傾向にあり、ただ解答を覚えるだけでは対応が難しい場面も多くなっています。
ChatGPTは、そうした問題に対して「どう考えるか」「どこから手をつけるか」を会話形式で導いてくれるため、家庭学習の中で思考力を高めていくサポート役にもなってくれます。
また、保護者がそばにいなくても、子どもが自分で質問しながら学びを進められるので、「教えてあげたいけど時間がない」というご家庭でも、学習の質を下げずに日々の学びを継続することが可能になります。
それでは、ChatGPTの基本情報と使い方について、さらに詳しく見ていきましょう。
今話題のChatGPTって何?(初心者向けに超やさしく)
ChatGPTとは、アメリカのOpenAI社が開発したAIチャットアシスタントです。
「GPT」は「Generative Pre-trained Transformer」の略で、世界中の膨大な文章を学習しており、人間のような自然な受け答えができるのが特徴です。
たとえば、算数の「速さ・時間・距離の関係」が苦手な子どもが、「この問題、どうやって考えたらいいの?」と入力すれば、式の意味や考え方のポイントを、例や図に置き換えながらわかりやすく説明してくれます。
これは、思考のプロセスを丁寧にたどる力を養う助けとなります。
また、国語の作文練習にも活用できます。「将来の夢」というテーマで書いた文章を入力し、「もっとよくするにはどうすればいい?」と尋ねると、構成や表現の改善点を具体的にアドバイスしてくれます。
これにより、表現力や論理的な構成力も強化されていきます。
このように、ChatGPTは「答えを出す」だけでなく、「どうやって考えればいいか」を一緒に考えてくれる存在です。
これは、自学自習を中心とした家庭学習を支える上で大きな武器になるでしょう。
どこで使える?スマホ・パソコン・無料でOK?
ChatGPTは、スマートフォン・パソコン・タブレットなど、インターネットにつながる端末があればすぐに使えます。
iPhoneやAndroidのスマホでも、「ChatGPT公式アプリ」(OpenAI社)がApp StoreやGoogle Playから無料でインストール可能です。
また、ブラウザ版はOpenAIの公式サイト(https://chat.openai.com/)でアカウントを作成すればすぐに使い始められます。
アカウントの作成の具体的な方法については以下の記事からどうぞ。
💭「親として、どこまで関わればいいの?」「子どもがやる気を失ってきてる…」
特殊算の勉強だけでなく、日々の学習サポートそのものに不安を感じている方へ。
今話題のAI・ChatGPTが、実は中学受験家庭の“心強い味方”になるんです。
無料プランでも十分に家庭学習や受験対策に活用できる機能が備わっており、まずは気軽に試してみるのがおすすめです。
さらに、ChatGPTは「1日30分だけ使う」などのルールを設けることで、学習習慣を定着させたり、計画的な学びを促すツールとしても活用できます。
たとえば、「平日は学校の宿題を終えたらChatGPTで質問する」「毎週日曜に1週間の復習をする」などの形で使えば、自然と学習計画のサイクルができあがります。
このように、ChatGPTは機能的にも操作性の面でも、小学生でも扱いやすく、家庭学習を支える“第2の先生”として十分に頼れる存在です。
中学受験の家庭学習でChatGPTを“AI家庭教師”にする具体的活用法9選

中学受験に向けて家庭で学習を進めていると、「この問題、どうやって教えたらいい?」「学習計画がうまく立てられない」「子どもが集中してくれない」など、さまざまな悩みが出てきます。
特に塾に通わず家庭学習中心で受験対策を行っている場合、保護者の負担は大きくなりがちです。
そんなときに力を発揮するのが、AI家庭教師ともいえるChatGPTです。
ChatGPTは、質問に対して会話形式で答えてくれるだけでなく、子どもが自分で考えながら学ぶ姿勢=自学自習力の育成にもつながります。
さらに、苦手単元を中心に学習を組み立てたり、定期的に振り返る習慣をつけたりと、受験に向けた日々の学習を戦略的に進めるサポート役にもなってくれます。
ここでは、家庭学習を支えるツールとしてChatGPTを“家庭教師代わり”に活用するための、実践的な使い方をわかりやすく紹介します。
①「わからない問題」をその場で解説してもらう
例:「この食塩水の問題、どう解くの?」と聞いてみる
家庭学習中に「答えはあるけれど、なぜそうなるかがわからない」という場面はよくあります。ChatGPTに質問すれば、その問題の解き方をていねいに順を追って解説してくれるので、理解が深まりやすくなります。
たとえば、「5%の食塩水100gに、何gの水を加えると2%になる?」という問題も、ChatGPTなら計算手順だけでなく、「なぜその式になるのか」「どこに注目すればいいか」といった思考のプロセスまで教えてくれます。
実際に、ChatGPTに「5%の食塩水100gに、何gの水を加えると2%になる?」の質問をしたChatGPTからの回答を下に示します。
この問題は、濃度と重さの関係を使った典型的な食塩水の問題です。
一緒にステップで解いてみましょう。
✅ 問題
5%の食塩水100gに、何gの水を加えると2%の食塩水になるか?
✅ ステップ1:5%の食塩水100gに含まれる食塩の量を求める
5% = 100g中に5gの食塩が含まれているということ。
食塩の量 = 100g × 5% = 5g
✅ ステップ2:水をx g加えたとき、全体の重さを表す
水を加えても、食塩の量は変わらず5gのまま。
全体の重さは:
100g(もとの食塩水)+ x g(加えた水)=(100+x)g
✅ ステップ3:濃度2%になる式を立てる
濃度は「食塩の量 ÷ 全体の重さ × 100」で表されます。
5 ÷ (100 + x) × 100 = 2

✅ 答え:
150gの水を加えると、2%の食塩水になります。
これは、ただ答えを覚えるのではなく、思考力を伸ばすトレーニングとして非常に効果的です。
保護者がそばにいない時間でも、子どもがChatGPTと対話しながら自学自習を進めることができるのは大きなメリットです。
② 学習スケジュールや勉強の優先順位を一緒に考える
例:「小5で週4回、1時間勉強したい」と相談
実際に、ChatGPTに「小5で週4回、1時間勉強したい」の質問をしたChatGPTからの回答を下に示します。
いいですね!「週4日×1時間」という条件で、中学受験に向けた家庭学習のバランスよいスケジュールを作るときは、以下のポイントを押さえると効果的です:
✅ ポイント
算数は週2回以上(得点源・苦手になりやすい)
国語も週1回以上(読解や語彙力は積み重ねが大事)
理社はセットで週1回が基本(暗記+考察力をバランスよく)
週末や平日の空き時間に復習やテスト見直しもおすすめ
🗓️ おすすめスケジュール例(週4日×60分)
曜日 内容 目標・意識すること
月曜 算数(応用+計算練習) 苦手単元の演習やミス直し、計算の精度UP
火曜 国語(読解+語彙) 記述対策・要約練習・語彙問題で基礎強化
木曜 理科+社会(交互) 暗記だけでなく「なぜ?」を意識して学習
土曜 算数+週の復習 過去問/ミス直し/学習記録の振り返り
📝 アレンジ例(目的別に)
🔹 記述力を伸ばしたい場合
→ 火曜の国語に 作文 or 要約練習(10〜15分)を加える
🔹 理社の暗記が不安な場合
→ 木曜を 理社のみ各30分ずつ にして交互に小テスト形式で復習
📌 小さな工夫で続けやすく
毎回の学習前に「今日やること」をメモ
勉強後は「どこができたか・どこが難しかったか」を記録(家庭学習ノートやアプリもOK)
月末に1回、学習計画の見直し&目標リセットがおすすめ!
ご希望があれば、志望校や学年別にさらにカスタマイズしたスケジュールも提案できますよ!お気軽にどうぞ 😊
中学受験では「何を、いつ、どれだけ学ぶか」を計画的に管理する力が求められます。
これは、塾に通わずに家庭で受験勉強を進める場合、特に重要な要素です。
ChatGPTに「週4日、1時間ずつ勉強したいけど、どんなスケジュールがいい?」と聞くと、教科のバランスを考慮した学習計画の提案をしてくれます。
実際に、ChatGPTに「週4日、1時間ずつ勉強したいけど、どんなスケジュールがいい?」の質問をしたChatGPTからの回答を下に示します。
了解です!
「週4日・1日1時間」で中学受験の家庭学習を効率よく進めるスケジュールをご提案します。
以下は、小学5〜6年生を想定した、バランス重視&無理なく続けやすいプランです。
🗓️ 週4日・1時間の学習スケジュール例(中学受験対策向け)
| 曜日 | 教科 | 内容例(ポイント) |
|---|---|---|
| 月曜 | 算数 | 応用問題、図形・割合などの重点単元の演習+ミス直し |
| 火曜 | 国語 | 読解演習(物語文・説明文)、語彙力強化、記述練習 |
| 木曜 | 理科 or 社会 | 理社を週替わりで交互に:用語の暗記+なぜ?の確認 |
| 土曜 | 算数+総復習 | 計算トレーニング+1週間の見直し、間違えた問題の復習 |
✅ 続けるコツ
- 毎回10分ずつに区切る(集中力UP)
例:算数→20分(応用)+10分(ミス直し)+10分(復習)+20分(計算) - ノート1冊を「家庭学習記録帳」にする
学んだこと・できたこと・疑問点を書いておくと、親子の共有にも◎ - 毎月1回は「振り返りの日」を設ける
今月の成果と課題を一緒に確認するとモチベーションが続きやすくなります。
📌 こんなアレンジもOK!
- 理社を30分ずつにして「理科+社会」の日にする(木曜:各30分)
- 土曜の算数を「過去問の日」にして入試形式の問題に慣れる
- 火曜の国語を「作文・記述練習」に切り替える(志望校に応じて)
必要があれば、志望校別・教科ごとの配分強化プランもお作りできます。
お気軽に「うちは○○中志望」「算数が苦手」など教えてください!それに合わせて調整しますよ 👍
このように、「月曜:算数の応用、火曜:国語の読解、木曜:理科/社会、土曜:復習・確認テスト」など、目標に合わせたプランがすぐに得られます。
さらに、「国語の記述が苦手だから多めにしたい」と伝えれば、それに応じて内容を調整してくれるなど、個別最適化された学習計画の提案も可能です。
実際に、ChatGPTに「国語の記述が苦手だから多めにしたい」の質問をしたChatGPTからの回答を下に示します。
なるほど!「国語の記述が苦手だから多めにしたい」ということですね。
それを踏まえて、週4日・1時間ずつの学習スケジュールを国語記述強化型にアレンジしてご提案します。
🗓️ 国語記述を重視した週4日・1時間スケジュール
| 曜日 | 教科 | 内容(記述対策を意識した構成) |
|---|---|---|
| 月曜 | 国語(記述演習+語彙) | 記述問題を1〜2問練習+語彙・表現チェック |
| 火曜 | 算数(応用中心) | 図形・割合・速さなどの応用/文章題もOK |
| 木曜 | 国語(読解+要約) | 長めの読解文+要点整理/文章の要約練習 |
| 土曜 | 理科 or 社会+復習 | 理社を隔週交互に。残り時間で1週間の記述振り返りもおすすめ |
✏️ 国語記述を鍛えるための具体的メニュー例
| 練習内容 | 目安時間 | ポイント |
|---|---|---|
| 記述問題1問(20〜50字) | 約20分 | 問われている「型」を分析するクセをつける |
| 語彙・漢字練習 | 約10分 | 書ける語・使える語を増やすと表現力UP |
| 要約練習(本文の要点) | 約15分 | 「誰が・何を・なぜ」などを整理する力がつく |
| 回答の書き直し | 約15分 | 「書きっぱなし」ではなく推敲する習慣を |
💡 さらに効果的にする工夫
- ChatGPTに「この記述、直してくれる?」と聞いて添削してもらう
→ 文章のクセ・曖昧表現の指摘がもらえて、自分では気づきにくい改善点が見える - 親子で回答を読み合って「どこが伝わりにくいか」を話す
→ 読者視点での表現力が身につきます - 学校や塾の記述問題を「ジャンル別ノート」にまとめておく
→ 物語/説明文/資料読み取りなど、出題パターンが整理できる
ご希望があれば、
- 記述が出やすい中学の過去問傾向
- おすすめの記述練習教材(市販 or 無料)
などもご案内できます!
お気軽に「この学校を志望している」など教えてくださいね ✍✨
このように的確に答えてくれ、さらに「何かご希望は?」と保護者のニーズを聞いてくれる点も良いですね!
これは、子ども自身がChatGPTとの対話を通して、“自分で学習をマネジメントする姿勢”を身につけるきっかけにもなります。
③ 子どもへの声かけや励まし方を相談する
例:「模試で落ち込んでいるけど、何て言えばいい?」
実際に、ChatGPTに「模試で落ち込んでいるけど、何て言えばいい?」の質問をしたChatGPTからの回答を下に示します。
模試で落ち込んでいるお子さんに、どんな声をかければよいか…悩みますよね。
でも、その気持ちにちゃんと寄り添うことが、次に進む一歩になります。
ここでは、小学6年生の受験生に向けたおすすめの声かけ例と、NGになりやすい言い方も併せてご紹介します。
✅ 声かけの基本は「感情に共感」+「次の行動への視点」
💬 こんな言葉が効果的です
🔹【共感+寄り添い編】
- 「悔しかったね。がんばってたの、ちゃんと見てたよ。」
- 「その気持ち、大事だよ。落ち込むってことは、本気だったってことだもんね。」
- 「点数じゃなくて、ちゃんと模試を受け切ったことがまずすごいよ。」
🔹【前向きな行動につなげる編】
- 「今回の結果で、どこを直せばいいか分かってきたね。一緒に見直してみようか。」
- 「この模試でつまずいた分、今直せば本番で絶対に強くなるよ。」
- 「間違えたってことは、まだ伸びしろがあるってこと。これからだよ!」
❌ NGになりやすい声かけ(気をつけたい)
- 「なんでこんなミスしたの?」
- 「こんなんじゃ受からないよ」
- 「もっとちゃんとやればよかったのに」
→ 子どもの心が閉じてしまい、自信を失う原因になります。
🌱 ちょっとした工夫で励まし効果が高まる!
- ✔ 模試のあとには必ず「良かったところ」を一つ見つけて伝える
→ 例:「この算数の1問、前回は解けなかったのに今回はできてたね!」 - ✔ 「次にどう生かすか」を一緒に考える時間を作る
→ 一方的に励ますよりも、「どうしたい?」と本人に聞いてあげると◎ - ✔ ChatGPTに一緒に相談してみるのもおすすめ
→ 「模試の見直し計画を立てて」「理科の苦手な単元を集中練習したい」と相談できて、行動につながりやすくなります
💡一言メッセージカードにしても◎
🌟「今回の結果はゴールじゃない。次のスタートにしようね。応援してるよ!」
✨「あなたなら大丈夫。失敗を次に生かす力、ちゃんと持ってるから。」
子どもは「結果」よりも「気持ちをわかってもらえること」で立ち直ります。
焦らず、でも見守りすぎず、ちょっと先を一緒に見る姿勢で寄り添ってあげてくださいね 😊
必要であれば、模試の見直しノートの作り方や、ミスを減らす家庭学習の進め方もお手伝いできますよ!
中学受験は長期戦。
継続的な学習だけでなく、モチベーション管理やメンタルサポートも非常に大切です。
保護者の声かけひとつで、子どものやる気が大きく変わることもあります。
ChatGPTに「模試で点数が下がって落ち込んでいる。どんな声をかけたら前向きになる?」と聞くと、「努力のプロセスを認める言葉」「次につながる具体的な励まし方」など、状況に応じた適切なコミュニケーションの例を提案してくれます。
実際に、ChatGPTに「模試で点数が下がって落ち込んでいる。どんな声をかけたら前向きになる?」の質問をしたChatGPTからの回答を下に示します。
とても大切な場面ですね。模試で点数が下がったときの子どもは、**「がんばったのに…」「自分はダメなんじゃないか」**と感じていることが多いです。
その気持ちをしっかり受け止めてから、前を向ける声かけをすることがポイントです。
✅ 落ち込んだ子どもが前向きになれる声かけの流れ
🔹 ① まずは「事実より気持ち」に寄り添う
「悔しかったよね。すごくがんばってたの、ちゃんと見てたよ。」
「点数のことよりも、ここまで毎日続けてきたのが本当にすごいと思うよ。」
→ まず感情に共感してあげることで、「わかってくれた」という安心感が生まれます。
🔹 ② 次に「今できること」を一緒に考える
「間違えたところを一緒に見直してみようか。次に活かせば大丈夫。」
「今回は“伸びるチャンス”をもらったんだよ。次、どうやって取り返そうか?」
→ 失敗を“成長の材料”に変える視点を一緒に持つことで、前向きさが戻ってきます。
🔹 ③ 努力や変化に目を向けさせる
「この前より時間配分がよくなってたね。そこはちゃんと成長してるよ。」
「国語の記述、前よりしっかり書けてたの、気づいてた?」
→ 点数だけでなく、プロセスや伸びたところに注目することで、自信につながります。
❌ 言ってしまいがちなNGワード
- 「なんでできなかったの?」
- 「また同じミスしてるじゃん」
- 「これじゃ志望校、無理なんじゃない?」
→ 意図せず子どもを否定・比較・プレッシャーしてしまうので注意が必要です。
🧭 ChatGPTを一緒に使うのも◎
もし子どもが「どこがいけなかったのか分からない…」と悩んでいたら、ChatGPTに:
- 「この模試の算数の問題、間違えた理由が知りたい」
- 「理科のこの単元、やり直したいけどどうすればいい?」
- 「次の模試までに復習スケジュールを立てたい」
などと聞いてみると、自分から改善策を考えるきっかけになります。
=前向きな行動にスムーズにつながるんです。
🌱 最後に、こんな一言を添えてみてください
「模試は本番じゃないから、ミスできてラッキーなんだよ。ここで直せば合格に近づけるからね。」
「今の悔しい気持ちが、次のがんばりに変わると信じてるよ。」
子どもの心が弱っているときこそ、言葉の力が大きく届く瞬間です。
がんばってきたことを認めて、次の行動を一緒に見つける声かけ、ぜひ意識してみてくださいね。
ご希望があれば、模試後の見直しシートの作り方や、弱点克服スケジュールもお手伝いします!
これにより、親が感情的に叱ったり焦らせたりするのを防ぎ、子どもが安心して学び続けられる家庭環境づくりがしやすくなります。
受験勉強を乗り切るうえでの心の土台も、ChatGPTはそっと支えてくれます。
④ 作文の添削をしてもらう
中学受験では、国語や総合型問題で表現力や思考力を問う記述問題が出題される学校も増えてきました。
特に「将来の夢」や「社会で気になっていること」など、自分の考えを筋道立てて書く力は、合否を左右する大切な要素です。
しかし、家庭で作文を添削するのは難しいもの。
「どこを直せばいいかわからない」「主観的になってしまう」と感じる保護者も多いのではないでしょうか。
例:「将来の夢についての作文、案を作ってくれる?」
実際に、ChatGPTに「将来の夢についての作文、案を作ってくれる?」の質問をしたChatGPTからの回答を下に示します。
もちろんです!
「将来の夢」についての作文の**お手本(400字程度)**を作成します。小学生でも無理なく書ける構成にしてありますので、書くときの参考にしてくださいね。
📝 作文例:「将来の夢」
ぼくの将来の夢は、小学校の先生になることです。なぜなら、今の先生のように、勉強だけでなく、思いやりやマナーなど、大切なことをたくさん教えられる人になりたいからです。
特に国語の時間が好きで、先生が読んでくれる物語を聞くと、頭の中にその場面が浮かんできます。自分でも、子どもたちにわかりやすく読み聞かせをしたり、難しい問題をかんたんな言葉で教えられる先生になりたいです。
そのために、まずは自分が勉強をがんばって、いろいろなことを正しく理解する力をつけたいと思います。そして、友だちとの関わりを大切にして、だれにでもやさしくできる人になりたいです。
これからも「先生になりたい」という気持ちを忘れずに、夢に向かって努力していきたいです。
(約390字)
✨ 作文を書くときのヒント
✅ 構成はこの流れで書くと◎:
- 【導入】自分の夢は何か
- 【理由】なぜその夢を持ったか
- 【工夫】どんな人になりたいか・どんなことをしたいか
- 【まとめ】夢のために今がんばっていること or 今後の目標
✅ 「理由」や「エピソード」を入れると伝わりやすい!
ご希望があれば「医者になりたい」「動物を助ける仕事がしたい」など、テーマに合わせた作文案もお作りしますよ!どんな夢を書きたいか教えてください😊
そんなとき、ChatGPTに作文を入力し、「よくするためのアドバイスがほしい」と依頼すると、構成や表現の工夫、論理展開の改善点などを具体的に指摘してくれます。
文末のバリエーション、語彙の幅、読み手に伝わる構成といった記述力を高める視点が自然に身につきます。
さらに、「この文章に具体例を入れたらもっと説得力が出るよ」といった提案もあり、子どもが自分で考えながら書き直すことで、自学自習的な作文トレーニングが可能になります。
⑤ 理科の実験内容の解説をしてもらう
例:「てこの実験、なんで右が上がるの?」
実際に、ChatGPTに「てこの実験、なんで右が上がるの?」の質問をしたChatGPTからの回答を下に示します。
いい質問ですね!
「てこの実験で右が上がる理由」は、**力の大きさだけじゃなく、どこに力をかけたか(距離)**も関係しているんです。
🔧 てこの基本ルール(てこの原理)
てこには、次のようなルールがあります:
力の大きさ × 支点からの距離(腕の長さ)= 力のはたらき(モーメント)
この「力 × 距離」で、左右のバランスが決まります。
🔍 具体的に見てみよう
たとえばこんな実験をしたとします:
- 棒のまん中に支点(軸)がある
- 左に 500g のおもりを 1目盛の位置に
- 右に 300g のおもりを 2目盛の位置にのせた
⚖️ 左と右の力のはたらきを比べてみると…
- 左側のはたらき:
500g × 1(目盛)= 500 - 右側のはたらき:
300g × 2(目盛)= 600
→ 右側の「力のはたらき(モーメント)」の方が大きい!
💡 結果 → どうなる?
- 右の方が強く押している状態になる
→ 左が下がって、右が上がる
✅ まとめ
てこは、「重いほうが下がる」ではなくて、
“重さ × 支点からの距離” の大きいほうが下がるんだよ!
他にも「てこがつり合う条件を使った計算問題」や、「ふりこの動き」も説明できるよ!気になる内容があればいつでも聞いてね😊
中学受験の理科では、「てこ・ばね・ふりこ」などの力学や「水溶液・電気・気体の性質」などの実験知識が問われます。
塾では実験の映像や器具を使った説明が受けられますが、家庭ではなかなか実演できないことも多く、理解が断片的になりがちです。
ChatGPTは、そうした理科の実験内容について「なぜそうなるのか?」「条件が変わるとどうなるか?」という観点から、因果関係を言葉でていねいに説明してくれます。
これは、単なる暗記ではなく、「理由を考える力=思考力」を育てる助けになります。
また、「この現象のポイントを3つにまとめて」といった使い方をすれば、要点整理や記述式対策としても効果的。家庭学習のなかで理科に苦手意識を持っていた子どもでも、会話形式で理解が進むことで前向きに取り組めるようになります。
⑥ ChatGPTを使う時間のルールを決める
例:「1日30分だけ」「土日は使わない」など家庭ごとの基準を設定
便利なChatGPTですが、使いすぎると「とりあえず聞く」クセがつき、自分で考える力が育ちにくくなることもあります。
だからこそ、「いつ・どれくらい使うか」のルールをあらかじめ決めておくことが重要です。
たとえば、「家庭学習の最後の15分はChatGPTと質問タイム」「週に3回だけ使う」「問題を1つ解いてから聞く」といったルールを設けることで、自分で考える力とAIのサポートを両立させることができます。
このように、ChatGPTを学習計画の中に組み込むことで、学びの習慣化や学習ペースの安定にもつながります。
保護者が時間のコントロールをしながら使い方を見守ることで、より良い家庭学習環境が整っていきます。
⑦ 学習記録を一緒につける
例:「今日は何を聞いた?」「答えはどうだった?」を毎日メモ
ChatGPTを活用した学習が「やりっぱなし」になってしまわないよう、日々のやりとりを簡単に記録しておくと効果が高まります。
たとえば、「質問内容・答えのポイント・自分の感想」の3点をノートに書き残すことで、復習時の振り返りや弱点の可視化がしやすくなります。
保護者が一緒に記録を見る習慣をつければ、「今日もがんばったね」「ここの理解が深まってきたね」といったポジティブな声かけができるようになり、学習モチベーションの維持にもつながります。
また、ChatGPTのチャット履歴機能を活用すれば、「どんなテーマに多く質問しているか」「繰り返しつまずいている内容は何か」が見えてきます。
これは、中学受験に向けた戦略的な受験対策の土台作りにも役立ちます。
⑧ 過去問の傾向を分析してもらう
例:「逗子開成の算数、どんな問題がよく出る?」
実際に、ChatGPTに「逗子開成の算数、どんな問題がよく出る?」の質問をしたChatGPTからの回答を下に示します。
逗子開成中学校の算数の入試問題は、例年大問5題で構成されています。 特に以下の分野が頻出とされています:
図形問題:点の移動、回転体の体積、相似比を利用した問題など、多岐にわたる出題が見られます。角度や長さ、面積に関する問題は毎年すべての回で出題されており、応用力が重視されています。
速さに関する問題:グラフとの融合問題として出題されることが多い傾向があります。
周期算:近年、2次入試で周期算が出題されています。
これらの分野に加え、基本的な計算力や応用的な小問集合の問題も出題されます。過去問を通じて、これらの頻出分野を重点的に学習し、出題傾向を把握することが効果的な対策となります。
中学受験では、学校ごとの出題傾向を正しくつかむことが合格への近道です。
算数なら「図形問題が多い」「グラフ読み取りが頻出」、国語なら「物語文中心」や「記述問題が多い」など、学校によって特徴はさまざまです。
ChatGPTに「○○中学校の過去問の傾向を教えて」と聞くと、過去に公開された情報などをもとに、出題傾向や頻出単元を整理して伝えてくれます。
これにより、効率的な学習計画を立てる材料として活用できます。
また、「この学校に合格するために、算数ではどんな対策が必要?」といった質問も可能で、志望校ごとの学習方針を明確にしやすくなる点もメリットです。
⑨ オリジナル問題を作ってもらう
例:「割合の応用問題を5問作って」とリクエスト
塾や市販の教材では物足りない、もう少し演習量を増やしたい――そんなときにもChatGPTは頼りになります。
たとえば、「小6レベルの割合の文章題を3問作って、解説もつけて」と指示すると、その場でオリジナル問題とわかりやすい解説を作ってくれます。これは、苦手単元の反復練習や応用力の養成にぴったりです。
実際に、ChatGPTに「小6レベルの割合の文章題を3問作って、解説もつけて」の質問をしたChatGPTからの回答を下に示します。
もちろんです!
以下に、小学6年生レベルの割合の文章題を3問、それぞれにわかりやすい解説つきでご用意しました。
✅ 問題①:割引の問題(売買の割合)
問題:
あるお店で、1500円のTシャツを2割引で売っています。
このTシャツはいくらになりますか?
解き方・解説:
❶ 2割引ということは、定価の20%を引くということ。
👉 1500円 × 20%(=0.2)= 300円(割引額)
❷ 定価から割引額を引く。
👉 1500円 − 300円 = 1200円
答え:1200円
✅ 問題②:もとの数の求め方
問題:
ある数の40%が48です。
この「ある数」はいくつですか?
解き方・解説:
❶ 「ある数の40%=48」なので、
👉 式にすると:
ある数 × 0.4=48
❷ 両辺を0.4で割って、もとの数を求める。
👉 48 ÷ 0.4 = 120
答え:120
✅ 問題③:割合の増減(何%増えた?)
問題:
あるクラスの男子の人数は、去年は20人でしたが、今年は26人になりました。
男子は何%増えましたか?
解き方・解説:
❶ 増えた人数を求める。
👉 26人 − 20人 = 6人増えた
❷ もと(去年)の人数に対する増えた割合を求める。
👉 6 ÷ 20 = 0.3 → 30%
答え:30%増
✨ ポイントまとめ
- 「○%引き」→ もとから引く金額を出して、引き算!
- 「○%が××です」→ 割合の式で、もとの数を出す!
- 増えた・減った → 「もとに対して何%か」で考える!
ご希望があれば、割合×図形、割合×速さなど応用バージョンもご用意できます!
「苦手なタイプ」や「逆に得意な単元」などあれば教えてください😊
子どもが「この単元をもっと練習したい」と思ったときに、自分から問題をリクエストする習慣がつけば、自発的な家庭学習=自学自習の土台づくりにもつながります。
カスタマイズできる学習は、AI家庭教師ならではの強みです。
中学受験の家庭学習でChatGPTを安全・効果的に使いこなすコツ

ChatGPTは中学受験の家庭学習を支える“第2の先生”として非常に便利なツールです。
しかし、AIである以上、すべてを任せきりにしてしまうと、思わぬ落とし穴に気づかないこともあります。
特に小学6年生の子どもたちは、情報の取捨選択がまだ難しい年齢です。
正確な理解や、受験本番に向けた応用力を身につけるためには、ChatGPTを「子どもが一人で使うもの」ではなく、「親子で一緒に活用するサポーター」として考えることが重要です。
そのためには、いくつかのポイントを押さえた使い方が欠かせません。
ここでは、家庭でChatGPTを上手に取り入れていくための注意点と、その効果を最大限に引き出すコツを具体的にご紹介します。
完全に任せない、親が“舵取り”することが大事
ChatGPTはどんな質問にも素早く反応し、わかりやすい回答を提示してくれるため、「子どもが自分で全部できそう」と思われがちです。
しかし実際は、すべてをAI任せにしてしまうと、誤解や表面的な理解にとどまってしまうこともあります。
たとえば、算数の解説をしてもらった後に「本当に理解できたかどうか」「説明通りに自力で解けるか」といった確認作業は、人間である保護者の役割です。
家庭学習では、内容の確認や復習の方向づけといった“舵取り”が非常に大切になります。
また、子どもがChatGPTに頼りすぎると、「聞けば答えてくれるから考えなくていい」となり、自分で考える力が育ちにくくなることも考えられます。
あくまでChatGPTは補助的な存在であり、中心にいるのは子ども自身であるという意識を持つことが大切です。
「どのタイミングで使うか」「どの質問を一緒に考えるか」など、親が活用の設計図を描いてあげることが、家庭学習の質を上げるためのポイントです。
誤情報もあるので「一緒に考えるツール」として使う
ChatGPTは非常に優れたAIですが、インターネット上の膨大な情報をもとに学習しているため、まれに誤った内容を含む回答をすることがあります。
特に中学受験のような専門的で細かい内容では、「少しズレた説明」や「最新の出題傾向と異なるアドバイス」が見られることもあります。
たとえば、「歴史の年号が間違っていた」「理科の実験の条件が実際と異なっていた」といったケースは、実際に家庭でも報告されています。
そのため、ChatGPTの回答はあくまで“参考意見”として受け取り、正解かどうかを一緒に確認する姿勢が必要です。
このような使い方こそが、AIとの理想的な付き合い方です。「一緒に考える」「一緒に確認する」ことで、子どもの思考力が伸び、親子の対話の時間も自然に増えていきます。
実際に、「ChatGPTがこう言ってるけど、本当にそうかな?」「調べてみようか」という会話を通じて、子どもが自ら疑問を持ち、自分で調べて納得する姿勢を育てることができます。
家庭学習を中心に進めるご家庭にとって、AIはあくまで“補助輪”のような存在です。
使い方次第で、子どもにとって最高の学びのパートナーにも、逆に依存につながるリスクにもなりえます。
ChatGPTが家庭学習をどう変える?中学受験家庭に起きた4つの変化

中学受験を家庭中心で進めるご家庭では、「親の関わり方」「子どもの自立」「日々の学習の質」が大きく合否に関わってきます。
とくに小学6年生のこの時期は、模試や志望校対策に追われ、親子ともにプレッシャーを感じやすいタイミングです。
そんな中でChatGPTを取り入れると、受験対策における日々の負担が軽減され、家庭学習の進め方にも前向きな変化が生まれたという声が数多く聞かれています。
ここでは、実際にChatGPTを家庭学習に取り入れたご家庭が実感した、4つの大きな変化をご紹介します。
① 親のストレスが減る
中学受験では、家庭学習において保護者が担う役割も非常に大きくなります。
特に塾に頼らず進める場合、学習内容の理解から進捗管理まで、すべての受験対策を親が把握する必要があることに負担を感じる方も多いはずです。
ChatGPTを活用することで、子どもが「この問題の意味がわからない」「なぜこの解き方になるのか」といった疑問を、その場で自分で解消できるようになります。
これにより、保護者が常に“解説係”としてつきっきりになる必要がなくなり、心理的なストレスが軽減されます。
また、「一緒に考える」姿勢で使うことで、親子の役割も自然に分担され、無理なく家庭学習が継続しやすくなるという利点もあります。
② 子どもの「考える力」が育つ
ChatGPTの最大の魅力は、「答えを教える」だけではなく、「どうしてそうなるのか」「別の考え方はないか」といった思考のプロセスを重視した応答が得られる点です。
このため、子どもはただ正解を覚えるのではなく、「なぜそう考えるのか?」をChatGPTと一緒に掘り下げながら、論理的な思考力や問題解決力を自然に身につけていくことができます。
また、自分の言葉で質問し、返ってきた答えを理解して再び整理するというプロセスを通して、自学自習の力も育ちやすくなります。
これは、受験だけでなく中学校以降の学習でも非常に役立つ力です。
③ 親子の会話が増える
ChatGPTを導入すると、子どもが「今日、これを聞いてみたよ」「この答え、おもしろかったよ」と、自分の学習を親に共有したくなるようになります。
これは、従来の「宿題やった?」「どうしてできなかったの?」といった管理型の声かけから、学習を通じた対話型のコミュニケーションへの転換を促します。
このような会話が生まれることで、保護者は子どもの理解度や関心を自然と把握できるようになり、必要なタイミングでの声かけやサポートがしやすくなります。
また、子どもにとっても「見てもらっている」「応援されている」という安心感が、学習意欲の向上に直結します。
④ 家庭学習のペースが安定する
塾と違って自由度の高い家庭学習では、つい学習のペースが乱れがちです。
保護者が忙しい日や、子どもの気分が乗らない日は「今日は休んでもいいか」となってしまうこともあります。
そこで、ChatGPTを日々の学習に取り入れることで、「今日の最後に1問質問する」「毎週金曜は復習と質問デーにする」など、学習計画の中に“AIとの対話時間”を組み込むことが可能になります。
こうした取り組みは、子ども自身が自分の学習をコントロールする意識(自学自習力)を育むうえでも非常に効果的です。
結果として、無理のない学習ペースを保ちながら、日々の積み重ねによる安定した受験対策が実現します。
塾に頼らず中学受験!ChatGPTを家庭教師代わりに使う方法に関する Q&A
ChatGPTを家庭教師代わりに使う方法に関する Q&Aよくある疑問は下記の通り。
ここからそれぞれの疑問について、1つずつ詳しく解説していきます。
- ChatGPTで使ってはいけない使い方や注意点はありますか?
- 子どもが間違った情報を信じてしまわないためには、どうしたらよいですか?
- 学習に集中できるよう、ChatGPTの会話以外の機能は制限できますか?
- ChatGPTを使うと成績は本当に上がるのでしょうか?
- 子どもがAIに頼りすぎてしまうのが心配です。依存を防ぐにはどうしたらよいですか?
ChatGPTで使ってはいけない使い方や注意点はありますか?
はい、特に以下の3点には注意が必要です。
- 個人情報は入力しないこと
ChatGPTに本名、学校名、住所、メールアドレス、写真などの個人情報を入力するのは厳禁です。保護者の方が最初に一緒に使いながら、危険性をしっかり説明しておきましょう。
- 「カンニング」のような使い方はNG
宿題や模試、過去問の答えを丸ごと聞いて終わらせるような使い方は、成績向上にはつながりません。考え方の補助やヒントをもらう目的で活用するのが適切です。
- 絶対に正しいとは限らない
ChatGPTはたまに計算ミスをしたり、内容に誤りを含むことがあります。教科書や参考書と照らし合わせて使うことが大切です。
子どもが間違った情報を信じてしまわないためには、どうしたらよいですか?
まず大事なのは、「ChatGPTの答え=正解」と思い込ませないことです。
そのために以下の習慣をつけましょう。
- 「教科書と見比べてみよう」などの声かけをする
AIの回答に対して、親子で「確認すること」を当たり前にすると、自然と正しい知識が身につきます。
- 一緒に調べる時間を作る
たとえば、社会の歴史問題で「年号があやふやだな」と思ったときは、地図帳や資料集、信頼できるサイト(たとえば文部科学省やNHK for School)と一緒に見ると良いでしょう。
- 子ども自身に「正しいかどうかを確認する力」を育てる
「この答え、納得できる?」「どこかおかしいところはない?」という問いかけを通じて、情報の受け取り方に敏感になっていきます。
学習に集中できるよう、ChatGPTの会話以外の機能は制限できますか?
現在のChatGPT(無料プラン/有料プラン共通)では、保護者が特定の機能や表示を制限する「ペアレンタルコントロール機能」はありません。
しかし、以下の方法で集中しやすい環境は作れます。
- 使う時間帯を固定する(例:17時〜17時30分)
「使っていい時間」を決めることで、だらだらと使うのを防げます。
- 「ChatGPT専用ノート」を作る
質問をする前にノートに書かせて、それを元に入力・回答を整理させると、目的意識が高まり集中力も続きます。
- 親のスマホやPCを使わせる
自分専用の端末だと誘惑も増えるので、「今日はパパ・ママのPCを一緒に使おう」と提案するのも有効です。
ChatGPTを使うと成績は本当に上がるのでしょうか?
ChatGPTはあくまで理解のサポートツールであり、成績を上げるためには以下のような使い方が重要です。
- わからない部分を質問する習慣をつける
たとえば、算数で「割合」の文章題に悩んだとき、「なぜ分数を使うの?」と聞くことで、仕組みを理解できます。
- 復習に使うと記憶が定着しやすい
その日にやった単元をChatGPTで要約させたり、「この問題の解き方をもう一度説明して」と使うと、自然にアウトプットが増えます。
- 苦手の把握と反復練習がしやすい
「同じタイプの問題をあと3問ください」といった形で練習できるので、苦手分野を繰り返し鍛えることができます。
成績アップに直結するかどうかは「使い方次第」ですが、正しく使えば家庭学習の質が大きく向上するのは間違いありません。
子どもがAIに頼りすぎてしまうのが心配です。依存を防ぐにはどうしたらよいですか?
依存を防ぐためには、以下のような「親子でのルール決め」が効果的です。
- まず自分で考える時間を必ず取る
「わからなくても3分間は自分で考えてから使おう」というルールにするだけで、思考のクセがつきます。
- 質問メモを作ってから使う
ChatGPTを使う前に「何を聞きたいか」「どこまで理解したか」をメモにまとめると、整理力もつき、漫然とした使い方を防げます。
- 親が“答え合わせ係”ではなく“伴走者”になる
AIと対話したあとに「どうだった?」「なるほど、それで納得したのね」と感想を共有するだけで、子どもの主体性が育ちます。
また、「今日は自分の力でどこまでできたか」を話し合う時間をつくると、子ども自身も“頼りすぎていないか”に気づけるようになります。
まとめ:AI家庭教師は“親子の味方”にできる!
中学受験を家庭中心で乗り越えようとすると、学習の計画立てから日々の理解チェック、モチベーション管理まで、保護者が担う役割は非常に多岐にわたります。
特に小学6年生のこの時期は、過去問演習や模試の結果に一喜一憂し、親子ともに疲弊してしまうケースも珍しくありません。
そんなときこそ、AIを活用した新しい家庭学習スタイルが力を発揮します。
ChatGPTは、子どもの「わからない」にその場で対応し、「なぜそうなるのか」を言葉で丁寧に説明してくれます。
さらに、ただの答え合わせにとどまらず、「どこで間違えたのか」「どんな考え方をすればよかったのか」まで一緒に考えてくれる存在です。
これにより、受験対策における学びの質が高まり、思考力や問題解決力も自然と育っていきます。
また、家庭での学習時間の中にChatGPTを組み込むことで、子どもは自分から質問し、学びを深めていく習慣が身についていきます。
こうした自学自習スタイルが定着すると、保護者がつきっきりにならなくても、子どもが自立して学習に向かえるようになります。
もちろん、AIは万能ではありません。
誤った情報が含まれる可能性や、使い方によっては思考停止につながるリスクもあります。
しかし、だからこそ「親子で一緒に使いながら学ぶ」「使う時間や目的を明確にする」といったルールと工夫が重要です。
AIを“敵”にするのではなく、“味方”として取り入れることで、家庭学習はもっと前向きに、もっと楽しく、そして効果的に変えていけるはずです。
塾に頼らなくても、子どもが自分の力で伸びていける家庭環境をつくる――そのための心強いパートナーとしてのAI活用を、ぜひ一度ご家庭でも試してみてください。
「このままでいいのかな」と不安になる夜に。
中学受験を“がんばる親”に向けた無料メールレッスン、はじめました。
➤ ChatGPTと対話しながら、気持ちを整える6日間。
📩 保護者の心に寄り添う、無料メール講座(全6回)を始めませんか?
ChatGPTと一緒に、イライラ・不安・親子のすれ違いを少しずつ整えていく6日間。
特典PDFもプレゼント中です。
下の画像(友だち登録で特典PDFプレゼント)をクリックして下さい!

「中学受験パスポート」人気記事(TOP5)

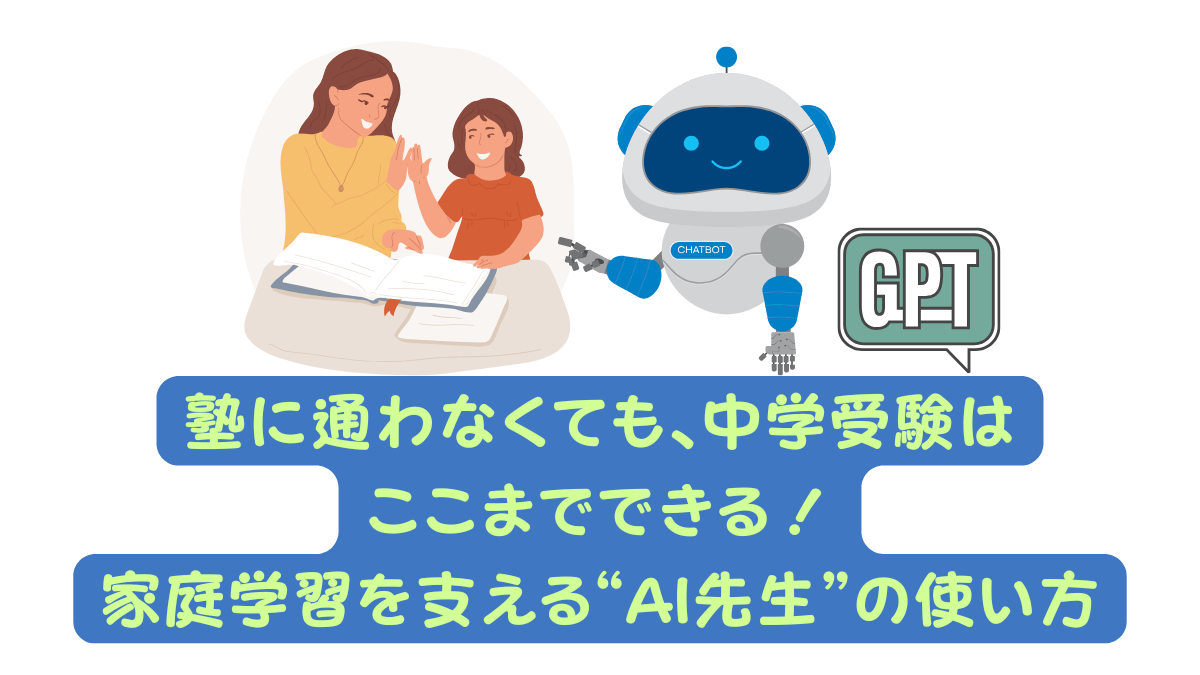






















chatgptの規約で13歳未満の利用は禁止では?
コメントありがとうございます。
ご指摘のとおり、ChatGPTは利用規約により13歳未満の子どもが直接アカウントを作って利用することは禁止されています。
当ブログでご紹介している活用法は、あくまで保護者の方や教育関係者の方向けに、お子さまの学習を支援する手段としての利用を想定しております。
そのため、お子さまが直接ChatGPTを操作することを推奨しているわけではございません。安心してご覧いただければ幸いです。どうぞご安心くださいませ。