「どうして“引く”と数が減るの?」
「3×4と4×3、どっちがどっち?」
子どもに算数を教えていると、そんな素朴な質問に戸惑うことがあります。
四則計算(足し算・引き算・掛け算・割り算)は、
小学校で最初に学ぶ算数の“基本のき”。 でも、その意味をきちんと理解していないまま進むと、 文章題や図形問題でつまずく原因になります。
四則計算は、単なる計算練習ではなく、
「数の動き方」や「関係の変化」を理解する学びです。
足し算は「ふやす」、引き算は「へらす」、 掛け算は「くり返す」、割り算は「分ける」。 この4つの考え方をイメージでつかむことが、算数の第一歩です。
家庭で教えるときは、ブロックやお菓子などを使って、 「目で見て、手で動かして」数の意味を感じさせると効果的です。
この記事では、次の4つの計算について、
考え方・つまずきやすいポイント・教え方のコツを、 具体的にわかりやすく紹介します。
- 足し算: 数のまとまりを意識する教え方
- 引き算: 「へらす」「ちがいを求める」2つの意味を整理
- 掛け算: くり返しの考え方と九九の覚え方
- 割り算: 「分ける」「いくつ分」の2つのイメージを理解
家庭でもできる声かけの工夫や、つまずき解消のヒントも合わせて解説します。
- お子さんに算数の意味をやさしく教えたい方
- 「なぜそうなるの?」と聞かれて説明に困った経験がある方
- 家庭学習で算数の基礎をしっかり固めたい方
そんな保護者の方に向けて、
今日から使える“教え方のヒント”をお届けします。
目次
- 四則計算とは?4つの計算の意味とやり方の基本
- 計算方法の基本と教え方のコツ【4項目を丁寧に解説】
- 足し算のやり方と教え方のコツ
- ✅ 教え方のポイント
- ✅ 教え方のポイント
- ✅ 教え方のポイント
- ✅ くり上がりは「10のまとまり」で考える
- ✅ 2桁・3桁の筆算は「声に出して」覚える
- 引き算でつまずかないための考え方
- ✅ 引き算は「減る体験」からスタート
- ✅ 引き算を「見える化」して理解を深めよう
- ✅ 「繰り下がり」は見える形で理解させよう
- ✅ 「10のまとまり」を見せて理解を助ける
- ✅ 「繰り下がり」は10をくずす動きで教える
- 掛け算の意味と九九の覚え方の工夫
- 🍎 具体的なものから「かけ算」を感じさせよう
- 🎵 九九は「リズム」で楽しく覚えよう
- 🎯 九九カード&タイムアタックで楽しく反復!
- 🛒 九九を「生活の中」で使ってみよう
- 🧩 覚えにくい九九は「工夫」でクリア!
- 割り算の基本と筆算ステップを理解しよう
- ✅ 具体例
- ⚠️ つまずきポイント
- ✅ 混乱の理由
- ⚠️ 「割れない」と感じる子のつまずき
- なぜ「2 ÷ 3 = 0あまり2」は間違いなのか?
- ⚖️ 「あまり」は割る数より小さくなる
- ✅ 正しい考え方は「分数・小数」で表現する
- 🧮 分数や小数で表すと?
- ✅ サポート方法(3ステップ)
- 🍪 日常の場面で考えてみよう
- 🧩 見てわかる!「2 ÷ 3」の考え方
- 📏 数直線で分け方を見てみよう
- ✅ 補足:学年と対応時期の目安
- 🎓 学年別の教え方のコツ
- ✅ 具体例:「84 ÷ 4」の筆算
- ⚠️ つまずきポイント
- ✅ 具体例:「17 ÷ 5」の考え方
- ⚠️ つまずきポイント
- ✅ 具体例:「132 ÷ 4」の計算の流れ
- ⚠️ つまずきポイント
- 🟢 補足アドバイス:繰り返しと見える学びがカギ
- 計算の順番(演算順序)のルールをおさえよう
- 四則計算が算数において重要とされる理由
- 子どもに四則計算を教えるときの工夫と注意点
- 練習にぴったり!四則計算の問題例と教材紹介
- おすすめ教材・ツールで四則計算をもっと楽しく
- まとめ|四則計算を子どもと楽しく学ぶコツ
四則計算とは?4つの計算の意味とやり方の基本
🧮 四則計算とは?すべての算数の出発点四則計算とは、「足し算・引き算・掛け算・割り算」の4つをまとめた言葉です。
小学校の算数では、この4つがすべての学びの土台になります。
日常生活でも、買い物・料理・時間の計算などでよく使う力です。
だからこそ、早い段階で“意味を理解して”身につけておくことが大切です。
四則計算は、それぞれ「数の動かし方」を表しています。
ただ覚えるだけでは、文章題や図形のような“考える問題”でつまずくこともあります。
「なぜそうなるのか?」を考える力を育てることで、
計算を“使える力”へと変えていくことができます。
基本をしっかり理解しておくことで、学年が上がっても応用力が自然に育ちます。
このブログでは、
4つの計算それぞれの「意味」「考え方」「家庭で教えるときのコツ」を、
わかりやすく紹介していきます。
四則計算に含まれる4つの計算とは
🧮四則計算とは?まずはここから四則計算とは、「足し算・引き算・掛け算・割り算」の4つをまとめた言葉です。
小学校で最初に学ぶ、算数のいちばん基本となる力です。
この4つの計算は、数のしくみや考え方を理解する土台になります。
ここをしっかり身につけることで、算数全体の理解がぐんと広がります。
それぞれの計算には、
「増やす・減らす・くり返す・分ける」という意味があります。
どれも、生活の中で自然に使われている考え方です。
たとえば、お菓子を分ける・りんごを何個ずつ配るなど、
身近な例を使うとお子さんもぐっと理解しやすくなります。
特に低学年のうちは、ブロックやおはじきなどの具体物を使って教えるのがおすすめです。
「見る」「動かす」ことで、式や記号の意味が自然に身につきます。
このあとでは、「足し算」「引き算」「掛け算」「割り算」それぞれの
特徴と教え方のポイントを、わかりやすく紹介していきます。
計算方法の基本と教え方のコツ【4項目を丁寧に解説】
💡算数が苦手になる理由と、家庭でできる工夫算数が苦手になる大きな原因は、暗記や反復練習だけに偏ってしまうことです。
計算の中にある「数の変化」や「生活とのつながり」を意識すると、
お子さんのやる気と理解の深さが大きく変わります。
また、ブロック・おはじき・絵や図などの「見える学び」を使うことで、
計算の意味が自然と身につきやすくなります。
この記事では、四則計算の4つのテーマについて、
つまずきやすいポイントと教え方のコツをやさしく解説します。
- 足し算:やり方と教え方のコツ
- 引き算:つまずかないための考え方
- 掛け算:意味の理解と九九の覚え方の工夫
- 割り算:基本の考え方と筆算のステップ
お子さんが「わかった!」と笑顔になる瞬間を増やすために、
意味を理解する学びを一緒に見ていきましょう。
以下で詳しく見ていきましょう。
足し算のやり方と教え方のコツ
➕ 足し算の教え方の基本足し算を教えるときは、「数がふえる」ことをイメージさせるのがポイントです。
おはじきやブロックなどの具体物を使い、目で見て数が増える感覚を体験させましょう。
視覚的に理解できると、計算への苦手意識も自然に減っていきます。
「くり上がり」が出てくると、子どもが混乱しやすくなります。
そこで“10のまとまり”を意識させると、理解がぐんと深まります。
計算の手順を教えるだけでなく、
「なぜそうなるのか」を言葉で説明することが大切です。
足し算の学び方には、いくつかの段階があります。
次の章で、具体的なステップと教え方のコツをくわしく紹介します。
足し算の教え方|5つのステップで段階的に理解を深める
具体物を使って「増える」感覚をつかむ
イラストや図を使って視覚化する
✅ 教え方のポイント
次は、イラスト・数直線・点の集合などを使って、
「見ることでわかる足し算」を練習します。
たとえば、
●●● + ●●
のように描いて、「全部で5こあるね」と数えさせましょう。
図で表すことで、「増える・まとめる」の様子が目で見てわかります。
数のまとまりを“感じる力”を育てるのにぴったりです。
数字と記号を使った式に置きかえる
✅ 教え方のポイント
図で足し算の意味を理解できたら、
「3+2=5」 のように数字と記号を使った式に進みましょう。
このとき、「+」は
『くっつける・まとめる記号』として伝えると、子どももイメージしやすくなります。
「数字=ものの数」「+=くっつける」という関係を、
身近な言葉でつなげてあげると、式に対する抵抗がなくなります。
繰り上がりのある足し算にチャレンジ
✅ くり上がりは「10のまとまり」で考える
10をこえる足し算では、まず10を作るのがコツ。
- 例: 7+5 → 7+3=10、残り2を足して 12
- 「10を作る → 残りを足す」の順で考える
🧩 ミニ練習
8+6=? → 8+2=10、残り4で 14
9+7=? → 9+1=10、残り6で 16
💡 指導のコツ
- 10玉そろばん・ブロックで「10のまとまり」を見せる
- 数直線で「10までジャンプ → 残りをジャンプ」を描く
- 言葉がけ:「まず10を作ろう」「残りは何?」
筆算に進む
✅ 2桁・3桁の筆算は「声に出して」覚える
筆算では、一の位 → 十の位 → 百の位の順で計算します。
ルールを声に出して唱えることで、自然と手順が身につきます。
- 「一の位から足す!」
- 「くり上がりは十の位へ!」
- 「上に1を書く!」
🧩 ミニ練習
37+45=? → 一の位:7+5=12(2を書いて1くり上がり) → 答えは82。
💡 指導のコツ
- 位ごとに色分けして整理するとミスが減ります。
- 「十の位・百の位」などを口に出しながら進めると定着が早いです。
- 間違えても「どの位でミスしたか」を一緒に確認しましょう。
この5ステップを意識すると、子どもは足し算の意味と手順をしっかり理解しながら進めることができ、将来の引き算・掛け算・割り算の学習にもつながります。
引き算でつまずかないための考え方
➖ 引き算の教え方の基本引き算は、「減る」「引く」という考え方が少しむずかしく、
子どもがつまずきやすい単元のひとつです。
とくに「ひく数が大きいとき」や「くり下がりがあるとき」は、
考え方が混乱しやすいため、丁寧な説明と確認が大切です。
引き算で大切なのは、「くらべる」「差を考える」という考え方です。
たとえば、
「お菓子が10個あって、3個食べたら残りはいくつ?」
このような身近な例で、“残りを考える計算”=引き算だと理解させましょう。
式だけでなく、図やブロックを使うと理解がぐんと深まります。
「なくなる」「差がある」という変化を目で見ることで、 頭の中のイメージが定着しやすくなります。
次の章では、「引き算の考え方」をより具体的なステップで見ていきましょう。
具体物で「ひく」動作を体感する
✅ 引き算は「減る体験」からスタート
りんご・ブロック・おはじきなどの具体物を使い、
「あったものが減る」体験を通して引き算の意味をつかませましょう。
たとえば、
🍎 5個 → 2個とったら、残りはいくつ?
このように実際に動かすことで、
「引く=なくなる」感覚を身につけられます。
💡 指導のコツ
- 実物を手で動かして考えると理解が早い
- 「なくなる」「減る」などの生活の言葉を使う
- 図に描いて見せると、イメージが定着しやすい
絵や図で「残り」や「差」を見せる
✅ 引き算を「見える化」して理解を深めよう
数直線や絵カードを使って、
引き算の流れを目で見える形にして教えましょう。
たとえば、10−7 の場合、
10から7まで数直線で戻ると、
その距離(残り)=3 が答えです。
💡 ここがポイント
- 「引く=減らす」だけでなく「比べる」考え方も教える
- 数直線を使うと、差のイメージがつかみやすい
- 絵カードで動きを見せると、低学年にもわかりやすい
繰り下がりを絵とペアで理解させる
✅ 「繰り下がり」は見える形で理解させよう
繰り下がりが苦手な子には、
ブロックや図を使って十と一の関係を見せましょう。
たとえば 13−8 の場合、
13は「10と3」でできています。
10から1を取り出して一の位に足すと、
「12−8」として考えやすくなります。
💡 指導のコツ
- 「10のかたまりをくずして使う」動作を見せる
- 色ブロックやおはじきで実際に移動させる
- 図やイラストで「借りた数」を可視化すると理解しやすい
✅ 「10のまとまり」を見せて理解を助ける
繰り下がりの理解には、「十」と「一」を
見える形で示すことがとても大切です。
たとえば 13 の場合、
- 10個まとまった棒ブロック(=十)を1本
- 1個ずつの小ブロック(=一)を3個
このように 13=10+3 を
目で見て・手で触って学ぶことで、
数の構造を自然に理解できます。
💡 指導のコツ
- 10のかたまりを棒やカードで見せる
- 実際にブロックを動かして感覚で覚える
- 「10のまとまりをくずす」動作を視覚的に説明する

✅ 「繰り下がり」は10をくずす動きで教える
たとえば 13−8 の場合、
まず1の位(3個)から引けるだけ引きます(3個)。
残りの5個は足りないので、
10のまとまりを1本くずして
1のブロック10個にします。
その中から5個を引くと、ちょうど8個引けます。
この「10をくずす」動きを目で見せることで、
繰り下がりの仕組みが自然にわかります。
💡 指導のコツ
- 「10をくずす=1のブロックを増やす」と伝える
- ブロックを実際に移動させて理解を促す
- 繰り下がりを動作として体感できるようにする
文章だけでは難しい部分こそ、視覚とセットで教えることが鍵です。
掛け算の意味と九九の覚え方の工夫
✖️ 掛け算の教え方の基本掛け算は、「同じ数をくり返し足す」計算です。
たとえば「3×4」は、3が4つあるという意味になります。
この考え方は、日常生活の中でもよく使われます。
計算をすばやく、正確に行うための大切な基礎です。
まずは掛け算の“意味”を理解させることが、九九の暗記にもつながります。
九九は丸暗記ではなく、「数のまとまり」や「並びの法則」として覚えるのがコツです。
たとえば、
「5の段は手の指で数えられる」
「2の段は偶数が並ぶ」など、パターンを見つけると記憶がスムーズになります。
また、逆から言ったり、飛ばして言ったりする練習をすると、
九九を“使える知識”に変えることができます。
掛け算は暗記だけではなく、意味と体験をセットで学ぶことが大切です。
次の章では、九九を楽しく身につける工夫や
家庭での教え方のポイントを紹介します。
掛け算の意味を「絵」で体感させる
🍎 具体的なものから「かけ算」を感じさせよう
最初は数字ではなく、
「3個入りの袋が4つでいくつ?」など
身近なもので教えるのが効果的です。
○を並べたり、積み木を使ったりして、
同じ数がいくつ分あるかを
目で見て数える体験を積み重ねましょう。
💡 指導のコツ
- 式にする前に絵やブロックで体感させる
- 「同じ数が何組あるか」を言葉で説明させる
- 最初は「3が4つ」など声に出して練習する
リズムや歌で「九九」を耳から覚える
🎵 九九は「リズム」で楽しく覚えよう
九九は、リズムや音に合わせて覚えると定着が早まります。
YouTube・学習CD・九九ソングなどを活用して、
耳と口で覚える学習を取り入れましょう。
たとえば、
2×2=4(ににんがし)
のように節をつけて唱えると、自然に記憶に残ります。
💡 指導のコツ
- テンポの良い音源を使って楽しく反復させる
- 拍手・手拍子を加えるとリズムが定着しやすい
- 「声に出して」「動きながら」覚えると記憶が強化されます
カードやクイズでゲーム感覚にする
🎯 九九カード&タイムアタックで楽しく反復!
九九カードやタイムアタック形式のクイズは、
遊びながら練習できる効果的な方法です。
たとえば、
「3の段を5秒以内に全部言おう!」など
簡単なルールを作ると、子どもはゲーム感覚で取り組みます。
さらに、ごほうびシールやポイント制を導入すると、
楽しみながら自然と反復練習が続きます。
💡 指導のコツ
- テンポ良く答える練習を習慣化する
- 1日1段など小さな目標を設定する
- 成功体験を見える形(シール・得点表)で残す
応用問題で「使う」経験をさせる
🛒 九九を「生活の中」で使ってみよう
買い物ごっこや身近な計算場面を使って、
九九を実際に使う練習をしましょう。
たとえば、
「1個120円のりんごを5個買うといくら?」
という質問に九九を使うと、
120×5=600円と計算できます。
こうした体験が、
「覚える九九」から「使える九九」への
ステップアップにつながります。
💡 指導のコツ
- お買い物・料理などの生活シーンで九九を使う
- 「いくつ分?」「いくら分?」など問いかけ型で練習
- 答えを出すだけでなく考え方を言葉で説明させる
苦手な段は順番を変えてアプローチ
🧩 覚えにくい九九は「工夫」でクリア!
九九がなかなか覚えられないときは、
逆から言う・偶数の段だけ練習するなど、
少し変えた方法を試してみましょう。
また、
「今日は3の段だけ」のように、
小さな目標を立てて取り組むと、
負担が減って達成感を得やすくなります。
💡 指導のコツ
- 「できた!」を感じさせるスモールステップ学習
- 苦手段はカードや歌で繰り返す
- できた段から色塗りシートで可視化するとやる気アップ
これまでの方法を組み合わせると、掛け算は“楽しい”と感じられる学びになります。
子どもの様子を見ながら、興味を引き出す工夫を重ねていくことが大切です。
掛け算をただ覚えるだけで終わらせず、
“考える力”を育てるステップに進んでいきましょう。
次の記事では、
九九の先にある「考え方のコツ」をわかりやすく紹介しています。
👉 かけ算九九だけでは足りない?4年生までに知りたい考え方と理解のコツ
※リンク先では、九九を応用して思考力を伸ばす方法を詳しく解説しています。
割り算の基本と筆算ステップを理解しよう
➗ 割り算の基本:「等しく分ける」割り算は、「等しく分ける」計算です。
はじめはブロックやおはじきなどの具体物で、「いくつずつ分ける」感覚を身につけさせましょう。
意味がつかめると、筆算などの抽象的な処理にもスムーズに進めます。
割り算には「割られる数」「割る数」「商」の3つがあります。
筆算では、どの数をどの順で扱うかを丁寧に教えましょう。
また、あまりのある計算や、くり下がりに似た処理で混乱しやすいので、
段階的な練習が効果的です。
- 割り切れるか・大小関係を確認(例:12÷3は割り切れる?)
- 1けたずつ割るしくみを教える(上から順に処理)
- あまりの扱いを具体的に伝える(「足りない分は次の位から下ろす」)
- 商の位置(位取り)に注意(答えを置く場所をそろえる)
この流れで、「見える→わかる→できる」へと段階的に育てます。
数の大小関係と割り切れるかを確認する
✅ 具体例
「12 ÷ 3」は、
12の中に3が何回あるかを考える計算です。
→ 3 × 4 = 12 なので、答え(商)は 4。
割り切れる問題の例です。
⚠️ つまずきポイント
- 「÷」の意味をイメージできない
- 割られる数より割る数が大きい(例:2 ÷ 3)ときに混乱する
ブロックや図を使って「いくつ分あるか」を見せると、
割り算の考え方がすぐに理解できます。
最初は実物を動かして教えるのがおすすめです。
✅ 混乱の理由
⚠️ 「割れない」と感じる子のつまずき
小学生は「割り算=分ける計算」と考えることが多いため、
割る数が大きいと“割れない”と感じてしまうことがあります。
たとえば、
2 ÷ 3 を 「0あまり2」 と間違えるケースです。
これは、「1より小さい数」(分数や小数)の考えが
まだしっかり身についていないことが原因です。
「2個を3人で分けたら1人分はどのくらい?」など、
実際に物を分ける体験を通して教えると効果的です。
視覚的に「1より小さい数」を理解しやすくなります。
なぜ「2 ÷ 3 = 0あまり2」は間違いなのか?
① 「あまり」の定義に合わない
⚖️ 「あまり」は割る数より小さくなる
割り算のあまりは、必ず割る数より小さい整数です。
たとえば 2 ÷ 3 の場合、
割る数(3)>割られる数(2) なので、1回も割れません。
商は0になりますが、あまり2というのは正しくありません。
この式は分数や小数で表す計算であり、
「あまり付き割り算」ではなく“割り切れない計算”です。
「2 ÷ 3」は2を3等分すると考えるとわかりやすいです。
1人分は 3分の2(2/3) になります。
お菓子やブロックを3人で分ける体験を通して、
「分数=1より小さい数」の感覚を育てましょう。
✅ 正しい考え方は「分数・小数」で表現する
🧮 分数や小数で表すと?
2 ÷ 3 は割り切れない計算です。
- 分数で表すと → 2/3(3分の2)
- 小数で表すと → 約 0.666…
つまり、「あまりが出る」のではなく、
“部分的に分ける”という考え方が大切です。
「2個を3人で分けたらどうなる?」と質問して、
実際にお菓子やブロックを分けさせると理解が深まります。
「1人分は2/3個」という感覚が自然に身につきます。
✅ サポート方法(3ステップ)
① 場面の置き換えで理解を助ける
🍪 日常の場面で考えてみよう
「2個のクッキーを3人で分けるとどうなる?」と質問してみましょう。
子どもは自然に、
1人あたり 2/3 個とイメージできます。
身近な例を使うことで、
“割り算=分けること”の意味がよくわかります。
お菓子・おはじき・ブロックなどを使って
実際に分ける体験を取り入れると、理解がさらに深まります。
見て・触って・動かす学びが効果的です。
② 図やブロックを使って視覚化
🧩 見てわかる!「2 ÷ 3」の考え方
2つの正方形ブロックをそれぞれ 1/3ずつにカット して、3人に配ります。
すると1人あたりは、
2 × 1/3 = 2/3(3分の2) になります。
このように 実際に「分ける」様子を見ると、
2 ÷ 3 = 2/3 の意味が直感的に理解できます。
紙を折って切る、積み木を動かすなど、
「分ける動作」を見せると理解がぐっと深まります。
図や動画を使うのもおすすめです。
③ 数直線で小数や分数の意味を示す
📏 数直線で分け方を見てみよう
「1を3つに分けると1/3」になります。
つまり、「2を3で割る」は、2個分を3で分けることです。
この様子を数直線で表すと、
分数の位置関係が目で見て理解できます。
数直線上で「0 → 1 → 2」を3等分し、
1/3・2/3・3/3(=1)と印をつけると効果的です。
「2 ÷ 3 = 2/3」の意味が、視覚的にわかります。
✅ 補足:学年と対応時期の目安
🎓 学年別の教え方のコツ
🧮 小2〜小3:
「分ける」場面を言葉で説明しながら、
紙・おはじき・粘土などを使って実際に体験させます。
📘 小4以降:
分数や小数とつなげて考えられるように、
算数ブロックや図を使って視覚的に理解させましょう。
「見る・触る・動かす」体験を通して学ぶことで、
抽象的な計算もスムーズに理解できます。
遊びながら学ぶ感覚を大切にしましょう。
1ケタずつ割っていくしくみを教える
✅ 具体例:「84 ÷ 4」の筆算
8 ÷ 4 = 2
4 ÷ 4 = 1
👉 答えは 21 になります。
⚠️ つまずきポイント
「位ごとに計算する」意味がわからないと混乱しがちです。
84を80と4に分ける考え方で、
十の位 → 一の位の順に計算すると理解が深まります。
位取りを色分けしたり、十の位・一の位を指で押さえながら教えると効果的です。
「十のかたまり→ばらばらの1の数」という感覚をつかませましょう。
余りのある割り算を理解する
✅ 具体例:「17 ÷ 5」の考え方
5 × 3 = 15 → 商は3、残りは2
👉 よって 答えは 3 あまり 2 です。
⚠️ つまずきポイント
余りを忘れたり、書く場所がわからなくなることがあります。
おはじき・ブロックなどで余った数を見える形にし、
「分けられなかった分」として教えると理解しやすいです。
余りのある問題では、実際に分ける体験を通して学ぶのが効果的です。
お菓子・鉛筆など身近なものを使うと楽しみながら覚えられます。
商を立てる位置と位取りに注意する
✅ 具体例:「132 ÷ 4」の計算の流れ
- 13を4で割る → 商は3、余りは1
- 余り1に2をつけて「12」を4で割る → 商は3
👉 最終的な答えは 33 になります。
⚠️ つまずきポイント
商の位置を間違えると答えがずれることがあります。
筆算用のマス目プリントや位取りガイドを使うと、正しい位置関係が身につきます。
はじめは1桁ずつ区切る練習を繰り返すと安心です。
慣れてきたら「商を書いたあとにチェックを入れる」習慣も効果的です。
🟢 補足アドバイス:繰り返しと見える学びがカギ
割り算は足し算・引き算・掛け算の理解が土台になります。
- 具体物を使う → 目で見て操作しながら理解する
- 筆算に進む → 手順の意味を確認しながら練習する
時間がかかっても大丈夫。
焦らずステップごとに進めれば、確実に身につきます。
おはじき・ブロック・お菓子など、身近なものを使うと「わり算=分ける感覚」が自然に理解できます。
計算の順番(演算順序)のルールをおさえよう
🔢 計算の順番を理解しよう四則計算を正しく使うには、「計算の順番」を理解することが欠かせません。
足し算・引き算・掛け算・割り算が混ざると、順番を知らない子は混乱しがちです。
だからこそ、早い段階でルールを身につけておくことが大切です。
計算には順番のルールがあります。
特に、掛け算・割り算は足し算・引き算よりも先に計算するという決まりです。
順番を間違えると、まったく違う答えになってしまうこともあります。
例:3+2×4
- 足し算を先にすると → 3+2=5、5×4=20 → 答え15(誤り)
- 正しい順番(掛け算を先に) → 2×4=8、3+8=11 → 答え11(正解)
このように、順番を正しく守ることで、計算の仕組みがしっかり身につきます。
- 「先に掛け算・割り算」を口に出して覚える
- カードやクイズ形式で「どっちが先?」を楽しく練習
- 間違い例をあえて見せて「なぜ違うのか」を考えさせる
楽しみながら覚えると、計算のルールが自然と身につきます。
覚えるべき基本ルールは3ステップ
🔢 計算の順番をマスターしよう四則計算の順番を理解するには、3つの基本ルールを覚えるのが近道です。
順序に迷わず計算できるようになると、
文章題や複雑な式でもスムーズに解ける力が身につきます。
計算の順番を早いうちに整理しておくことで、
ミスを減らすだけでなく、
「なぜこの順番なのか?」を自分で説明できるようになります。
理解を定着させるには、段階を追って丁寧に伝えることが大切です。
- かっこがある計算 → 最優先で行う
- かけ算・わり算 → 先に計算する
- たし算・ひき算 → 最後にまとめて行う
これらを図や色分けで視覚的に教えると、より理解しやすくなります。
- 「3つのルール」を口に出して覚える
- 図・色・カードを使って視覚的に整理
- 間違えた例を見せて「なぜ違うのか」を考える
ルールを“体で覚える”教え方が、長く残る理解につながります。
「見える化」で理解を深める
👀 「見える化」で理解を深める四則計算の順番を理解させるには、「見える化」がとても効果的です。
式を図・色・ブロックなどで表すことで、
子どもが計算の流れを直感的に理解できるようになります。
「どれを先に計算するのか」がわかりにくい子には、
視覚情報が大きな助けになります。
目で見てルールを感じ取ることで、
理解が深まり、計算ミスも減ります。
- かっこや掛け算の部分を色分けして強調
- 計算の順番を番号付きの矢印で示す
- ブロックやカードを並べて「順番の見える教材」にする
こうした工夫で、計算の順序が自然と頭に残りやすくなります。
次の章では、
「見える化」で理解を深める|ステップ別の工夫を紹介します。
実際の教材アイデアや家庭での活用法もあわせて見ていきましょう。
式の中の“かっこ”や“優先される演算”を色分けする
🎨 色分けで「計算の順番」を見える化
計算のルールを色で区別すると、どこから計算するかがすぐにわかります。
- かっこ → 緑
- 掛け算・割り算 → 赤
- 足し算・引き算 → 青
このように式全体をマーカーで色分けすると、
計算の順番が感覚的に理解できます。
例: 3 + 2 × (4 + 1)
→ (4 + 1) を緑、2 × □ を赤、+ を青で示すと、計算の順番がひと目でわかります。
色を使うと「先にどこを計算するか」が直感的に理解できるため、
文章題や複雑な式でもミスが減ります。

ブロックやチップを使って手を動かす
🧩 手を動かして学ぶと理解が深まる
頭の中で考えるだけでなく、手を使って学ぶことで、理解がぐんと深まります。
- 積み木や100玉そろばんで「実際に数える」
- 掛け算は「3×4=3が4つ」のように具体化して伝える
こうした体験により、記号と数の動きが結びつき、計算の意味が自然に理解できます。
おうちではブロック・ビー玉・おはじきなど、身近なものでOK。
「見て・触って・動かす」体験が、算数の土台を育てます。
手順を矢印や番号で「フローチャート化」
🔢 計算の流れを「見える化」しよう
複数の計算があるときは、どこから計算するかを図で示すとわかりやすくなります。
- 「①→②→③」と番号をつけて順番を示す
- 矢印やアニメーションで手順を見せる(スライド・紙芝居形式も◎)
このように流れを見せる工夫は、図やイメージで考えるタイプの子に特に効果的です。
「順番を声に出して追う」練習を組み合わせると、理解がさらに深まります。
紙だけでなく、動画やスライドを使うと楽しく覚えられます。
四則計算が算数において重要とされる理由
🧮 四則計算は“算数の土台”四則計算(足し算・引き算・掛け算・割り算)は、
すべての算数・数学の基礎となる大切な力です。
文章題・図形・単位・割合など、どんな分野でも
四則計算の理解が学びの土台になっています。
この基礎があいまいなままだと、
たとえ考える力があっても正しい答えにたどりつけないことがあります。
逆に、計算を正確に・すばやくできるようになると、
思考の幅が広がり、応用力も育ちます。
たとえば、2けた同士の掛け算や、
文章題に出てくる「ひとつ分を出して全体を求める」割り算など、
一見むずかしそうな問題も、四則計算が身についていれば
順を追って考え、正しく解けます。
計算力はまさに“算数の土台”です。
ここをしっかり育てることで、子どもの理解力や考える力が大きく変わります。
子どもに四則計算を教えるときの工夫と注意点
🧩 教え方の基本は「ゆっくり・段階的に」子どもに四則計算(足し算・引き算・掛け算・割り算)を教えるときは、
段階的に無理なく進めることが大切です。
一気に詰め込むよりも、理解のペースに合わせて教えることで、
苦手意識を防ぎ、「わかった!」「できた!」という喜びを育てられます。
四則計算はすべてがつながっているため、
ひとつのつまずきが他の計算にも影響します。
「できたつもり」で進めず、早めに立ち返って確認する姿勢が大切です。
日常生活の中にも、数字を使うチャンスがたくさんあります。
- 買い物ごっこでお金の計算をする
- おやつを分けるときに「いくつずつ?」と考える
- 階段や信号待ちで数を数える
こうした「遊び×数字」の体験が、
机の上の勉強を「実感できる学び」に変えていきます。
四則計算は、生活の中で“使って覚える”ことが大切です。
数字を見る・触れる・考える機会を増やして、
自然に身につけていきましょう。
年齢・学年別のおすすめ指導アプローチ
🎯 学年に合わせた教え方がカギ四則計算を教えるときは、年齢や学年に合わせたアプローチが効果的です。
段階的に理解を深めることで、
計算力の土台をしっかり築くことができます。
低学年では、数の概念を理解させることが最優先です。
指・ブロック・イラストを使い、
「見る」「触る」「動かす」学びを通して、数の感覚をつかませましょう。
中学年では、掛け算や割り算の意味をしっかり理解させることが大切です。
文章題や図を使って、「どうしてそうなるのか」を考える学びを重ねましょう。
高学年では、スピードと正確さのバランスが重要です。
練習問題の難易度や形式を工夫することで、
達成感や自信につなげましょう。
小学1年生〜2年生:数のしくみと足し算・引き算の土台づくり
🧮 ① 10までの数を「見て」「触って」理解するまずは1〜10までの数の大きさや組み合わせを、
ブロックや指を使って体感させましょう。
たとえば「7は5と2に分けられる」など、
数を分けたり合わせたりする感覚を身につけることで、
計算の基礎がしっかり育ちます。
イラストやブロックを使って、
10をつくってから計算する流れを見せましょう。
たとえば「8+5」は、
「8と2で10をつくり、残りの3を足す」と教えると、
くり上がりの仕組みが自然に理解できます。
「おはじきが3つあります。2つふえました。ぜんぶでいくつ?」
このように絵や場面と式(3+2=5)を結びつけて教えましょう。
目で見た場面と式を対応させることで、
算数の意味理解が深まります。
小学3年生〜4年生:掛け算・割り算の導入と文章題への応用
✖️ 掛け算は「くり返しのたし算」からスタート掛け算は、まず「くり返しのたし算」として導入しましょう。
たとえば「3が4つある」=「3+3+3+3」。
このように意味を理解してから九九を覚えると、
暗記だけでなく“考えて使える力”が育ちます。
割り算は、「分ける」または「いくつ分あるか」を求める計算です。
「12個のクッキーを3人で分ける」など、
身近な例や図を使って、
割り算の意味を自然に理解させましょう。
文章題を解くときは、式と場面をつなげることが大切です。
テープ図や絵を使って「どんな場面でどの式を使うのか」を
見える形で教えると、応用力がぐんと伸びます。
小学5年生〜6年生:計算の正確性と速さをバランスよく伸ばす
🧮 筆算の定着と工夫大きな数の掛け算・割り算では、桁をそろえる・途中で確認することを意識させましょう。
また、「なぜそうなるのか」を考える習慣をつけると、計算の仕組みが自然に理解できます。
(3+2)×4 や 24÷(6−2)など、かっこを含む計算を練習して、順番を意識させましょう。
正しい順序で計算できるようになると、文章題や応用問題にも強くなります。
「合計いくら?」「半分にすると?」など、
生活の中で計算を使う場面を増やしましょう。
日常のやり取りの中で、自然に暗算力が身につきます。
学年が上がるごとに、具体物 → 図 → 式 → 応用の順で
少しずつ抽象的な思考に進めましょう。
親や先生が「今どの段階にいるか」を見極め、
子どものペースに合わせることが大切です。
よくあるつまずきポイントとその対処法
⚠️ 四則計算でつまずきやすいポイントとは?四則計算(足し算・引き算・掛け算・割り算)は、
多くの子どもがつまずきやすい共通の課題を持っています。
理解不足を放置せず、早めにフォローすることが学習定着のカギです。
計算が苦手になる主な理由は次の3つです。
- 考え方があいまい
- 暗記ばかりで意味がわからない
- 文章題とのつながりが弱い
やり方だけを覚えても、
「なぜそうなるのか」がわからないと応用できません。
| 計算の種類 | つまずきやすい点 | 対処法 |
|---|---|---|
| ➕ 足し算・引き算 | くり上がり・くり下がりで混乱 | ブロックや図で見える化 |
| ✖️ 掛け算 | 九九の暗記だけで理解が浅い | 「何が何個ある?」の具体例から始める |
| ➗ 割り算 | 割る数・割られる数があいまい | 分ける体験・まとめる活動で理解 |
| 🧩 文章題 | 式が立てられない | 絵やテープ図で状況を整理 |
計算につまずいたときは、早めに気づいて、見える形で説明することが大切です。
子どもの理解の段階に合わせて、具体的→抽象的に進めていきましょう。
それぞれのケースについて、次のセクションで詳しく解説していきます。
「8+5=?」のように一の位が10を超えると、
“10のまとまり”を作る感覚がつかめず、
指を使って何度も数え直す子がいます。
また、「13−7=?」などのくり下がりでも混乱しやすいのが特徴です。
- ブロックや10のまとまりを使って、数の増減を“見える化”
- 「10の合成・分解」の練習(例:8+2=10→10+3=13)で基礎を固める
- 数直線を使って、数が動く様子を目で見せる
視覚的に理解させることで、計算の仕組みを自然に身につけられます。
抽象的な計算を目で見て感じる体験に変えることで、
「わかった!」「できた!」という達成感が生まれます。
最初のつまずきを早めに解消することが、算数への自信につながります。
「3×4=12」は言えるけれど、
「3が4つ分ってどういうこと?」と聞かれると答えられない…。
そんな子は意外と多いです。
つまり、九九を唱えて覚えていても“意味がつながっていない”状態です。
- 「何が何個ある?」という具体例(例:みかん3個入りの袋が4袋)から考えさせる
- 配列図や絵を使い、数の並びを視覚化して理解を深める
- 九九は暗記より“意味の理解”を優先し、
「かける数」「かけられる数」の違いを意識させる
九九を言えることより、イメージできることが大切。
「数のまとまり」を理解してから覚えると、
文章題や応用問題にも強くなります。
「12÷3」を見て“どっちが先?”と迷ったり、
“3を12に分ける”と逆に考えてしまう子がいます。
わり算の意味を理解しないまま、形だけ覚えてしまうのが原因です。
- 実物や絵を使って「分ける」「何人に分ける?」を体験させる
- 文章題から入って、“意味”を先に教える
- 「わり算はかけ算の逆」という関係を意識させ、
セットで教えると定着が早くなります
“分ける体験”+“かけ算とのつながり”が、
わり算を理解するカギです。
「式を覚える」よりも「どういう場面で使うか」を意識させましょう。
「1個80円のりんごを3個買いました。いくらでしょう?」
この問題で、“何をどうすればいいの?”と
式が立てられない子が多くいます。
文章の中から数の関係をイメージできていないのが原因です。
- 絵やテープ図で、問題の状況を“見える化”
- 「読み取り → 図 → 式 → 答え」の流れで整理する練習を重ねる
- 何を聞かれている?「どの数を使う?」を一緒に確認する
目で見て考えるステップを入れることで、式を自分で立てる力が育ちます。
文章題は、文字の中に隠れた“数の関係”を見つける練習です。
読んで→描いて→考える流れを大切にすれば、
「式が立てられない」悩みを防げます。
これらのつまずきを一つずつクリアしていくことで、
子どもは四則計算の基礎をしっかり身につけられます。
大切なのは、保護者や先生の声かけとサポート。
「どこでつまずいたのか?」「どうすればできるか?」を
一緒に考えることが、理解への近道です。
四則計算を教える中では、筆算のつまずきもよく見られます。
家庭でも簡単に確認できるポイントをおさえておきましょう。
「うまく教えられるかな…」と不安に思う必要はありません。
大切なのはできた!を一緒に喜ぶ姿勢です。
学びは安心感と対話から生まれます。
日常の中で自然に学べる場面と声かけ例
🌟 日常生活こそ、算数の教室!日常の中には、足し算・引き算・掛け算・割り算を学べるチャンスがたくさんあります。
机の上の勉強だけでなく、生活の中で数字に触れる体験が
「算数=身近で使える力」に変わっていきます。
買い物・料理・遊びなど、数を扱う場面は日常にあふれています。
- 買い物で「りんご2つでいくら?」→ 足し算
- 折り紙を半分にして「何枚ずつ分けられる?」→ 割り算
意味のある場面で声をかけることで、
「なぜ計算するのか」を実感でき、理解が深まります。
こうした体験を繰り返すうちに、
子どもは自然と四則計算の考え方を身につけていきます。
算数が「勉強」から「生活の一部」へ変わる瞬間です。
家庭の中には、算数を自然に学べる場面がたくさんあります。
買い物・おやつ・おもちゃなど、身近なシーンを活用しましょう。
- スーパーで買い物をするとき
- おやつを一緒に分けるとき
- おもちゃの数を数えるとき
- 「このリンゴは1個100円だね。2個でいくらかな?」
- 「クッキーが3枚と4枚あるね。全部で何枚あるかな?」
- 「おはじきが5個と2個、合わせていくつ?」
ちょっとした声かけで、“考える算数”が生まれます。
計算の答えよりも、「なぜその数になるのか」を
一緒に話し合うことが大切です。
手元で数える・書く・動かすなど、
見て・触って考える活動を増やすと理解が深まります。
引き算は「減る」「残る」を体験しながら学ぶと、
ぐっと理解が進みます。
日常の中で数が変わる場面を見つけて、
「いくつ減った?」「あといくつ?」と声をかけてみましょう。
- お菓子を食べたあとに何個残っているかを考える
- 遊びのあとで使った道具の数を確認する
- 家族の人数から取り分を考える
- 「5個あったクッキー、3個食べたらあと何個?」
- 「10本の鉛筆を6人で使うよ。2本使ったら残りは?」
- 「おにぎりが8個あって、4個配ったらどうなる?」
身近な会話から“引き算の感覚”を育てましょう。
引き算は「減る」「残る」を実感できると理解が深まります。
日常の中で“残りを確認する”“比べる”体験を重ねて、
自然に数の変化を感じ取れるようにしましょう。
掛け算は“同じ数のくり返し”を表す計算です。
生活の中でこの感覚を体でつかむと、九九の理解がスムーズになります。
- 同じお菓子を人数分に分けるとき
- テーブルに同じ数ずつ並べるとき
- 時間ごとに同じ動作をくり返すとき
- 「クッキーを3人に2個ずつあげたら全部でいくつ?」
- 「1箱に4個入ってるね。それが5箱あると?」
- 「5分で5回ジャンプしたら、10分で何回になる?」
身近な会話から、“くり返し=掛け算”を自然に感じさせましょう。
掛け算の理解には、「同じ数がいくつ分あるか」を体験することが欠かせません。
九九を覚える前に、生活の中の“くり返し”を見つける体験を増やしましょう。
割り算の基本は“分ける”こと。
数を分けたり、同じグループを作る体験を通して、
自然と割り算の意味が身につきます。
- 人数に合わせておやつを分けるとき
- おもちゃやブロックを均等に配るとき
- 時間や距離を等分する遊びの中で
- 「12個のあめを4人に同じ数ずつ分けると?」
- 「10本の鉛筆を2本ずつ配ると何人に配れる?」
- 「15個のレゴを3人で分けたら何個ずつ?」
「分ける」「そろえる」など、動きを伴う声かけが効果的です。
割り算の理解には、“分ける”体験が欠かせません。
おままごとや配膳ごっこなどの遊びを通して、
等しく分ける楽しさを感じさせましょう。
どの計算も「正しい式にたどりつくこと」よりも、まずは具体物・日常体験を通じて意味を理解させることが最優先です。
身近な生活の中にある「数字のヒント」をキャッチして、自然に学べる環境づくりを意識しましょう。
練習にぴったり!四則計算の問題例と教材紹介
🧮 四則計算の定着には「練習」と「教材選び」がカギ!足し算・引き算・掛け算・割り算をしっかり身につけるには、
繰り返しの練習と適切な教材選びが欠かせません。
コツコツ問題を解くことで、理解が深まり自信につながります。
- レベルに合った問題から始める
- 少しずつ難易度を上げてステップアップ
- 無理をせず「できた!」体験を積み重ねる
難しすぎる問題から始めると、
つまずきや苦手意識が生まれやすくなります。
視覚的にわかりやすいカラー教材や、
ゲーム感覚で学べるアプリもおすすめです。
遊びながら自然と四則計算が身につきます。
- 学年別の練習問題
- よく間違える問題パターン
- 自宅で使える無料教材・学習アプリ
次の章で、目的別・年齢別におすすめ教材を詳しく紹介します。
学年別のステップアップ問題(小1〜小3)
🧮 学年に合ったステップで、四則計算を無理なく習得!四則計算の力を伸ばすには、学年に合ったレベルで練習を進めることが大切です。
無理に先へ進むよりも、理解→定着→応用の流れを意識しましょう。
- 難しすぎる問題は苦手意識の原因に
- ちょうどいい問題で成功体験を積み重ねる
- 「できた!」が増えると意欲と自信が育つ
お子さんの理解に合わせたペースで進めることが、
長く続く学習習慣につながります。
以下では、小学1〜3年生を対象に、
学年別のステップアップ問題を紹介します。
- 各学年の特徴とつまずきポイント
- 実際の練習問題と家庭での声かけ例
- 段階的に力をつけるコツ
学年ごとの成長に合わせて、無理なく計算力を伸ばしましょう。
■小学1年生:足し算・引き算の土台をつくる時期
1年生の算数では、「10までのたし算・ひき算」を中心に学びます。
ブロックやおはじきなど手で触れる教材を使うことで、
数の大きさや変化を目で見て理解できます。
- 【足し算】3+4=?
- 【引き算】9-2=?
- 【応用】5といくつで10になりますか?
どの問題も、「数の増え方・減り方」を感じ取ることがポイントです。
- 「あといくつで〇になる?」と質問して、考える力を育てる
- 指や具体物を使ってOK! 感覚で覚えるのが近道
見て・動かして・話しながら覚えると、
計算の意味が自然に身につきます。
■小学2年生:繰り上がり・繰り下がりに慣れる+九九の習得
2年生では、2桁の計算・筆算・九九(掛け算)が学びの中心になります。
筆算をスムーズに理解するためには、
10や100のまとまりを意識する力が大切です。
- 【足し算】27+38=?
- 【引き算】62-48=?
- 【掛け算】7×6=?
- 【応用】9×3の意味を説明してみよう
「数が増える・減る・まとまる」のイメージを、
図や動きで伝えるのが効果的です。
- 繰り上がり・繰り下がりは図やブロックで“見せて理解”
- 九九は語呂・リズム・歌で楽しく暗記
「覚える」よりも、“感じて理解する”学びを意識しましょう。
■小学3年生:筆算・割り算の導入で四則の完成に近づく
3年生では、3桁の計算・割り算の導入・あまりのある計算へと進みます。
計算だけでなく、文章を読んで式を立てる力も大切になってきます。
- 【足し算】146+287=?
- 【引き算】523-378=?
- 【掛け算】36×4=?
- 【割り算】28÷4=? 35÷6=あまり?
- 【応用】1個120円のノートを3冊買ったら、全部でいくら?
式を自分で立てられるように、
場面をイメージする練習を取り入れましょう。
- 割り算は「分ける」「何回分あるか」を具体物で理解
- 筆算は位をそろえて書く習慣を徹底
- 円・cmなど生活の中の数を使って応用力を育てる
生活と結びつけて学ぶことで、
“使える算数”が自然に身につきます。
間違えやすい問題パターンを解説付きで紹介
🚨 計算ミスには“パターン”がある!原因を見極めよう計算ミスの多くは、桁・繰り上がり・あまりの扱いに関係しています。
原因は「位置のずれ」や「手の動かし方」がまだ安定していないことがほとんどです。
焦らずゆっくり・見せながら教えることで、確実に直せます。
- 繰り上がり・繰り下がりのある筆算(足し算・引き算)
- 0や1を含む掛け算(例:6×0、1×8など)
- あまりのある割り算(例:23÷4など)
- 単位の書き忘れ(例:「円」「こ」など)
これらはどれも、視覚的な理解不足から生じるケースが多いです。
- 筆算では桁をそろえて書く習慣を身につける
- 図・色分け・具体物を使って見せる
- 間違いを「なぜ?」と一緒に考えて自分で気づかせる
ゆっくり丁寧に教えることで、
計算ミスは必ず減らせます。
自宅学習に使える無料プリント・アプリまとめ
🏠 家庭学習で“できる!”を積み重ねよう四則計算を定着させるカギは、家庭での反復練習です。
無料のプリント教材やアプリを使えば、
手軽に・楽しく・継続的に取り組めます。
- お子さんのペースで学べる
- ゲーム感覚で楽しめる
- 保護者の負担が少ない
「続けやすい環境」を作ることで、
計算練習が自然な習慣になります。
- ちびむすドリル:学年・単元別に使える四則計算プリントが豊富
- ぷりんときっず:見やすく、初めての子にもわかりやすい構成
- 算数忍者:ゲーム形式で楽しみながら計算練習できる人気アプリ
- くもんのうたとドリル:音と絵で学べる幼児向け教材
「やらせる」よりも“一緒に楽しむ”姿勢が大切です。
おすすめ教材・ツールで四則計算をもっと楽しく
🧮 四則計算を“楽しく”学べる教材を選ぼう!四則計算の学習は、楽しさを感じられる教材を使うと、ぐんと効果が上がります。
ゲーム性のある教材やカラフルな教具を使うことで、
集中力とやる気を引き出せます。
子どもが計算を続けられるかどうかは、
楽しく続けられる仕組みがあるかどうかにかかっています。
- 達成感を得やすい教材を選ぶ
- 視覚的・体験的に理解できる内容にする
- 少しの工夫で「自分からやる」学びに変わる
保護者の負担も減り、学習が自然と日課になります。
- 📖 小学生向け市販ドリル・通信教材の比較(Z会・くもん)
- 💻 無料で使えるオンライン学習サイト・プリント集
- 🧩 塾講師おすすめ!教具と学習サポートツール
お子さんの興味に合った教材を選んで、
「できる!」体験を増やしましょう。
小学生向け市販ドリル・通信教材の比較(Z会・くもん)
🧮 小学生の四則計算におすすめ!Z会 vs くもん四則計算の力をつけるには、市販ドリルや通信教材の活用が効果的。
特にZ会とくもんは人気が高く、
お子さんのタイプに合わせて選べます。
| 教材 | 特徴 | おすすめタイプ |
|---|---|---|
| Z会 | 考える力を育てる問題構成。 応用・文章題にも強くなる。 | 思考力を伸ばしたい子 |
| くもん | 反復練習で計算力を強化。 スモールステップで無理なく進める。 | 基礎力・スピードをつけたい子 |
- 「基礎から着実に」なら → くもん
- 「考える力も育てたい」なら → Z会
- 両方の良さを取り入れるなら → 平日はくもん+週末にZ会の組み合わせも◎
どちらも自宅で続けやすい教材です。
お子さんの性格や目標に合わせて選びましょう。
以下で詳しく解説します。
- Z会:文章読解と論理的思考を伴う問題が特徴
- くもん:数の概念を自然に身につける徹底反復ドリル 詳しくはこちら
- 使い分けのポイントと保護者のサポート方法
| 項目 | Z会(通信教育) | くもん(市販・教室学習) |
| 対象学年 | 小1〜小6(学年別コースあり) | 主に年長〜小6(進度に応じて無学年制) |
| 月額価格 | 約2,400円〜(小学1年生) | 教室:約7,700円/月 ドリル:約700円前後 |
| 教材 | 図を使った応用問題や考えさせる設問が多い | シンプルで反復型の計算練習が中心 |
| 学習スタイル | 自宅で添削付き教材+動画指導 | 教室通学 or ドリル自習 |
| 問題の特徴 | 応用・文章題が多く「考える力」重視 | 単純計算を大量に反復「正確さとスピード」重視 |
| 継続率(目安) | 約80%以上(Z会小学生コース全体) | 約90%以上(公表値・くもん教室平均) |
| サポート体制 | 添削・質問対応あり/オンライン講座も併用 | 教室なら先生の個別指導あり/家庭用ドリルには解答付き |
| おすすめタイプの子ども | 考えるのが好きな子/中学受験にも対応 | 素直に繰り返し練習できる子/習慣づけが必要な子 |
無料で使えるオンライン学習サイト・プリント集
🌟 無料で使える!四則計算のオンライン教材&プリント集四則計算の家庭学習には、無料のオンライン教材が大活躍!
費用をかけずに、お子さんのペースで反復練習ができます。
プリント学習とアプリの両方を組み合わせるのもおすすめです。
- 何度でも繰り返し練習できる
- 学年や目的に合わせて自由に選べる
- 進み具合を見える化できる(保護者にも便利)
- 印刷やスマホでも簡単に使える
遊びながら学べる教材が増えており、
「楽しい=続けられる」学習が実現します。
- ちびむすドリル:学年別プリントが豊富。家庭学習の定番サイト。
- ぷりんときっず:カラフルで見やすく、初学者に最適。
- 算数忍者:ゲーム感覚で楽しめるスマホアプリ。
- すぐる学習プリント:レベル別に整理された四則計算ドリル。
- とけいの森:低学年の「数の感覚」も育てる補助教材。
目的や年齢に合わせて選ぶことで、
無理なく・楽しく・続けられる学習になります。
| サイト名 | 対象学年 | 主な特徴 | 対応計算 | 詳細 |
| ちびむすドリル | 小1〜小6 | 学年別・単元別の豊富なプリント教材。家庭学習に最適。 | 足し算、引き算、掛け算、割り算 | 詳しくはこちら |
| ぷりんときっず | 年長〜小3 | シンプルで見やすいデザイン。初学者向けに最適。 | 足し算、引き算、九九 | 詳しくはこちら |
| すきるまドリル | 小1〜小6 | スモールステップ式で反復学習に強い。難易度も幅広い。 | 四則計算すべて | 詳しくはこちら |
| RISUきっず体験プリント | 年長〜小1 | 幼児・低学年向けのやさしい導入教材。図解多め。 | 足し算、引き算(主に1桁) | 詳しくはこちら |
| 教育出版の算数ワークシート | 小1〜小6 | 教科書準拠のPDF教材で、授業補助にも使える。 | 四則計算+単元ごとの応用 | 詳しくはこちら |
教材は、学年に合ったレベルを選ぶことで、学びやすさと達成感が生まれます。
ここでは、年齢別におすすめの使い方を紹介します。
- 年長〜小1:ぷりんときっず・RISUきっずなど、
1枚で終わる教材で達成感を感じさせる。 - 小2〜小3:ちびむすドリル・すきるまドリルで、
掛け算・割り算の基礎をしっかり反復。 - 小4以降:教育出版などのワークシートで、
応用力・文章題にチャレンジ。
- 「できた!」を感じられる分量がベスト
- 難易度よりも継続できる教材を選ぶ
- 学年が上がるにつれ、応用問題を少しずつ増やす
「ちょうどいいレベル」が、
学びを続ける原動力になります。
塾長が選ぶ!おすすめの教具と学習サポートツール
🧩 遊びながら学べる!四則計算のおすすめ教具・ツール教具やツールを使った学びは、
子どもの「わかる!」を引き出す最短ルートです。
手を動かしながら学ぶことで、数の感覚や考える力が自然に育ちます。
- 目で見て理解できるので、抽象的な計算がイメージしやすい
- 手を動かす体験で、記憶に残りやすい
- 遊び感覚で取り組めるから、集中力が続く
「楽しみながら学ぶ」ことが、
学びの継続力につながります。
- 100玉そろばん:数のまとまりを体感でき、足し算・引き算に最適
- ブロック教材(レゴや算数積み木):数の構成を“形”で理解できる
- 九九カード・かけ算すごろく:遊びながら九九を覚えられる
- ホワイトボードやマグネット式教材:家庭でも使いやすく、繰り返し練習できる
どれも「楽しさ×わかりやすさ」を両立できるアイテムです。
- 計算ブロック・算数タイル:具体物を動かして数の合成や分解を体験できる。
- 九九表ポスター・カード:視覚的に九九を定着させるための基本アイテム。
- ホワイトボード・マグネット数字:自由な操作ができ、遊び感覚で学べる。
- そろばん・計算アプリ:数の位置や繰り上がりの感覚を身につけやすい。
- タイマー・学習記録シート:集中力アップや継続学習の管理に有効。
| 教具・ツール名 | 対象学年 | 価格帯 | おすすめの使い方 |
| 計算ブロック・算数タイル | 小1~小3 | 1,000~2,000円 | 数の合成・分解の理解に最適。10のまとまりで足し算・引き算の構造を視覚化できる。 |
| 九九表ポスター・カード | 小2~小4 | 100~1,000円 | 毎日目に触れる場所に貼ったり、ゲーム感覚で暗唱練習。反復による九九の定着を図る。 |
| ホワイトボード・マグネット数字 | 小1~小3 | 500~2,000円 | 式の組み立てや計算の途中過程をその場で操作。自宅学習や親子の対話式学習にも向く。 |
| そろばん・デジタルそろばん | 小1~小5 | 2,000~5,000円 | 繰り上がりや繰り下がりの理解、数の感覚育成に効果大。習い事と併用でスキルアップも。 |
| 計算アプリ(例:トドさんすう) | 小1~小4 | 無料~月500円 | ゲーム形式で取り組める。スコア化されるためやる気が続きやすく、繰り返し練習にも最適。 |
| タイマー・学習記録シート | 全学年 | 100~1,000円 | 勉強時間の可視化や習慣化に有効。記録を親子で確認し、成功体験を共有しながら進めると効果的。 |
🟢 活用のポイント
- 学年・性格・学習スタイルに合わせて、1〜2種類からスタート。
- 手を使う体験で「わかる」「できる」を実感。
- 楽しみながら続けることで、計算への苦手意識がやわらぐ。
小さな成功体験が、学ぶ意欲につながります。
まとめ|四則計算を子どもと楽しく学ぶコツ
🧮 四則計算は「算数の土台」
足し算・引き算・掛け算・割り算は、算数の基本をつくる大切な単元です。
楽しさと達成感を大切に、段階的に身につけていきましょう。
計算力は他教科にもつながる力。
つまずきをそのままにせず、発達段階に合わせて丁寧にサポートしましょう。
- 数ブロック: 足し算・引き算の意味を体感できる
- 九九カード: ゲーム感覚で楽しく暗記できる
- 声かけ: 保護者や先生の励ましが意欲を高める
“できた!”という体験が、
子どもの自信と学ぶ力を育てます。

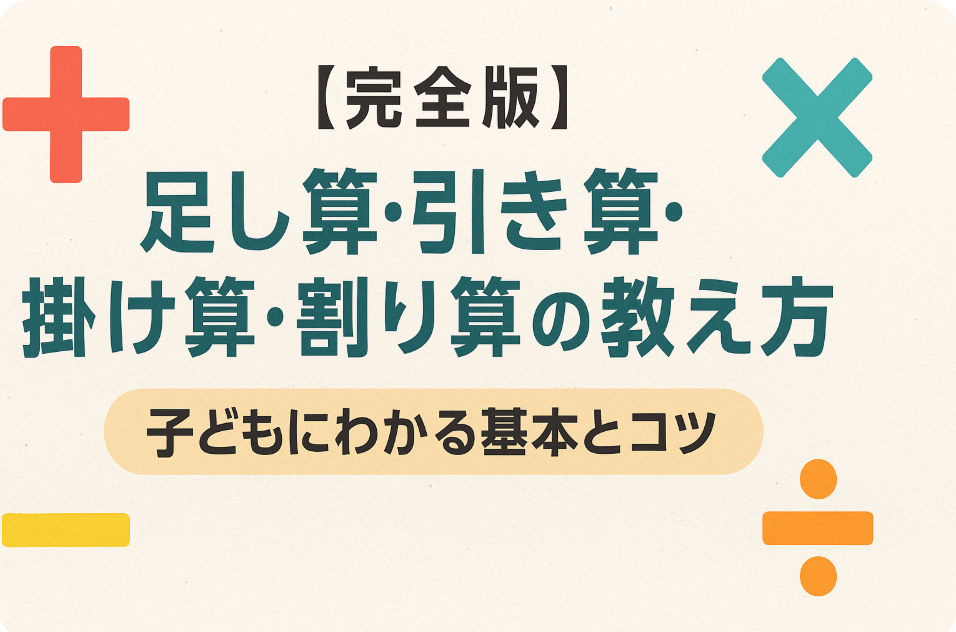

















✅ 教え方のポイント
りんごやブロックなどの身近なものを使って、
「3個あって、2個ふえたらいくつ?」と考えさせましょう。
目で見て数がふえることを実感できると、
足し算の意味が自然に理解できます。
「見る・触る・動かす」体験を通して学ぶと、
数字がただの記号ではなく“ものの数”としてつかめるようになります。