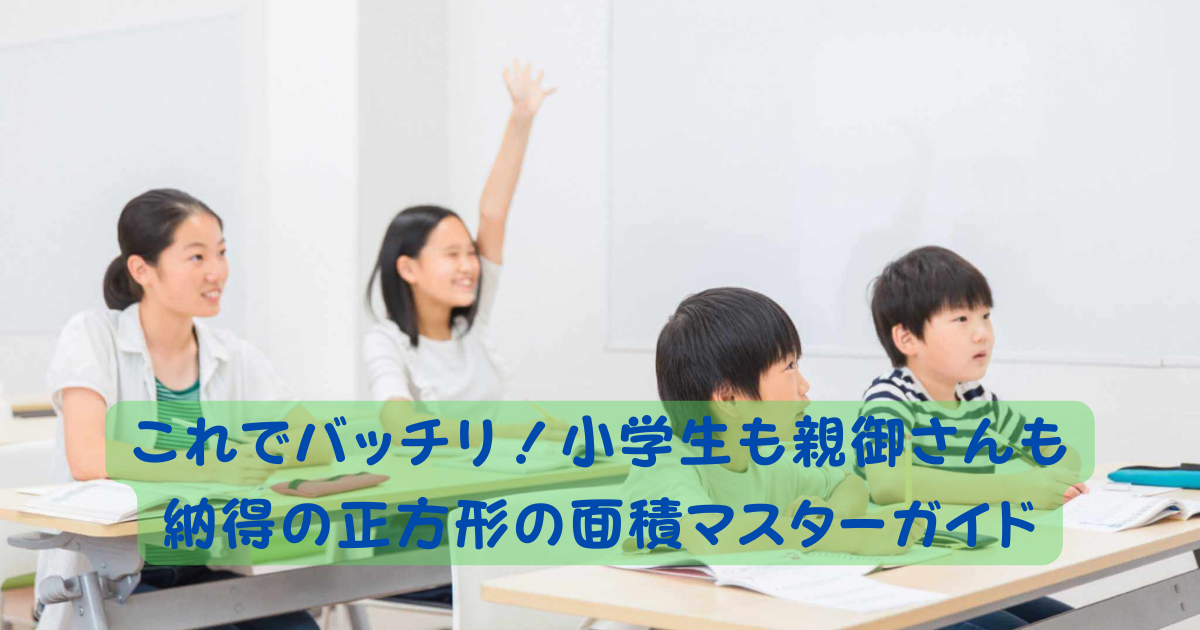今日の結論
- 解き方:図→関係性→式の順で固定。
- まず見る所:正方形は対角線=辺×√2 → 面積=対角線²÷2。
- 計算ミス回避:√2の²を忘れない・単位はcm²・丸めは最後に1回。
この記事では正方形の面積を対角線から求める方法を図解で解説。
公式が成り立つ理由、誤りや検算のコツ、入試頻出の応用パターンまで網羅し、中学受験レベルでも一度で理解できます。
- 正方形の面積の計算方法が理解できる: 対角線を使った面積の求め方を詳しく解説。
- 図や例題が豊富: わかりやすい図と具体的な例題で理解をサポート。
- 親子で学べる: 小学生と保護者が一緒に学ぶのに最適な内容。
- 数学の基礎を固める: 数学の基本的な概念をしっかり学べる。
- 興味を引く内容: 興味深い問題やQ&Aで学習意欲を引き出す
「中学受験の算数、どの参考書を選べばいい?」
迷ったらこちらの記事をチェック!お子さんにピッタリの算数参考書が見つかります。
➡ [中学受験おすすめ算数参考書まとめ]
💭「親として、どこまで関わればいいの?」「子どもがやる気を失ってきてる…」
特殊算の勉強だけでなく、日々の学習サポートそのものに不安を感じている方へ。
今話題のAI・ChatGPTが、実は中学受験家庭の“心強い味方”になるんです。
こんにちは!このブログでは、小学生高学年のみなさんと保護者の方々が、数学の基本である「正方形の面積」を対角線から求める方法について学べるよう、わかりやすく解説していきます。
正方形の面積の計算は、学校のテストや将来の勉強に役立つ大切な知識です。
楽しく学びながら、数学の力を身につけましょう!まずは基本的な概念から丁寧に説明していきますので、ぜひ一緒にチャレンジしてみてください。
目次
正方形の面積、公式と基本の考え方
正方形の面積を求める基本は「一辺の長さをかける」ことです。
中学受験では最も頻出の計算であり、この考え方を理解することで応用問題や対角線を使う公式もスムーズに身につきます。
シンプルな公式を正確に覚えることが、算数の得点力アップにつながります。
なぜ重要かというと、
- 第一に計算の基礎であるため入試問題の大半に関わるからです。
- 第二に、対角線やひし形といった図形問題の土台として活用できるからです。
- さらに、私の指導経験では「一辺×一辺」の感覚が早い段階で定着している生徒ほど応用の吸収も速く、得点の安定につながります。
本記事では次の2つの視点から整理します。
- 正方形の面積を辺の長さから求める方法
- 対角線を使った面積公式が便利な理由
どちらも中学受験の算数で必須の知識です。以下で詳しく解説します。
正方形の面積を辺の長さから求める方法
正方形の面積は基本的に「一辺×一辺」で求められます。
正方形の面積=一辺×一辺
中学受験算数の基礎力として必ず押さえておくべき内容であり、図形問題の出発点です。
対角線の公式を学ぶ前に理解しておくと応用がスムーズになり、得点の安定につながります。
なぜ重要かというと、
- 第一に最も出題頻度が高く暗記必須だからです。
- 第二に、図形の関係性を理解する際の基盤となるからです。
- さらに、授業での経験からも「一辺の長さを使った面積公式」が定着している生徒は、対角線やひし形の問題にも自信を持って取り組める傾向があります。
一辺が5cmの正方形なら、面積は5×5=25㎠となります
計算自体は単純ですが「四角形の中で最も扱いやすい図形」という実感を持つことで、学習への抵抗感が減ります。保護者の方も一緒に確認すると安心でしょう。
一方、実際の試験では一辺の長さではなく「対角線の長さ」から面積を求める問題も多く出題されます。そのときに役立つのが「正方形の面積を対角線で求める公式」です。公式の意味を理解しておけば、応用問題にも強くなります。
👉 正方形の基礎から応用までを整理した記事もあります。詳しくは 正方形の面積の求め方の基本 をご覧ください。
まとめると、正方形の面積を辺の長さから求める方法は算数の出発点です。
基礎を理解しておくことで、次の「対角線を使った面積公式が便利な理由」への学習がより分かりやすくなります。
対角線を使った面積、公式が便利な理由
正方形の面積を対角線から求める公式は、中学受験の算数で特に便利です。
なぜなら、一辺の長さが直接与えられない問題でも対角線だけで面積が計算でき、複雑に見える図形もシンプルに整理できるからです。
この公式を身につけることで、解答スピードと正答率の両方を高められます。
便利な理由は三つあります。
- 第一に、図形の一部にしか長さが与えられていない場合でも解答可能だからです。
- 第二に、ひし形など他の四角形の公式との関連が理解できるからです。
- 第三に、計算過程が短くなることで時間配分が改善されるからです。
私が教室で指導してきた経験でも、公式を使いこなす生徒は模試での得点安定につながっています。
対角線が8cmの正方形なら、面積は8²÷2=32㎠となります
一辺の長さを求める必要がないため計算が一段階減り、テスト中の焦りも軽減されます。
こうしたシンプルさは生徒にとって安心感につながるでしょう。
まとめると、対角線を使った公式は中学受験の図形問題を効率よく解く武器です。
理解を深めたい方は「正方形の面積を対角線から求める手順」で具体的な導き方を確認してみてください。
正方形の面積を対角線から求める手順
正方形の面積を対角線から求める手順を理解すると、図形問題が格段に解きやすくなります。
与えられた条件が辺ではなく対角線の場合でも公式を使って効率よく答えを導けるため、中学受験での得点力強化につながります。
便利な理由は三つあります。
- まず、対角線を利用することで計算の過程を短縮できる点です。
- 次に、直角三角形とピタゴラスの定理(a²+b²=c²)の知識を活用することで論理的に導ける点です。
- さらに、ひし形など他の図形にも応用できるため、幅広い単元をカバーできる強みがあります。
私が指導してきた生徒でも、この手順を理解したことで応用問題の正答率が上がったケースが多くあります。
ここで学べる内容は次の二つです。
- 公式の導き方(ピタゴラスの定理を利用)
- 例題で確認:対角線から面積を計算する流れ
どちらも入試本番で役立つ知識です。以下で詳しく解説します。
公式の導き方(ピタゴラスの定理を利用)
正方形の面積を対角線から求める公式は、ピタゴラスの定理を利用することで導けます。
この考え方を知っておくと、単なる暗記に頼らず自分で公式を再現できるため、応用問題や入試本番でも安心して使えるでしょう。
理解して身につければ、算数の得点力が安定します。
なぜピタゴラスの定理が関わるのかというと、正方形を対角線で分けると直角二等辺三角形ができるからです。
このとき斜辺が対角線、一辺が正方形の辺にあたります。
したがって a²+b²=c² という定理を使えば、対角線と一辺の関係が整理できます


本来は中学数学で学ぶ内容ですが、中学受験を目指す小学生にとって知識として先取りしておくと強力な武器になります。
私の教室でも、この原理を理解した生徒は応用問題の吸収が速く、模試で安定して得点できています。
実際の手順はシンプルです。
正方形の一辺を a、対角線を d とすると、d²=a²+a²=2a² となります。
これを変形すると a²=d²÷2 です。
ここで出てくる「二乗(²)【じじょう】と読む」は、「その数をもう一度かける」という意味です。たとえば 3² は 3×3=9 になります。

これを使うと、対角線 d の長さと一辺 a の関係は
d² = a²+a² = 2a²
と表せます。つまり「対角線の長さを二乗したものは、一辺を二乗したものを2つ合わせたもの」となります。
正方形の面積は a² なので、結果として「面積=d²÷2」が導かれます。
小学生でも流れを図で確認すれば十分理解できるでしょう。
要点をまとめると、ピタゴラスの定理を応用すると対角線から面積を導けます。中学受験の差をつけたい方は「例題で確認:対角線から面積を計算する流れ」も合わせて確認してみてください。
例題で確認:対角線から面積を計算する流れ
正方形の面積を対角線から計算する流れは、中学受験で頻出するため必ず理解しておきたい分野です。
結論から言うと、公式「面積=対角線²÷2」を用いることで、辺の長さがわからなくても面積をすぐに求められるのが大きなメリットです。
計算がシンプルになり、時間短縮にもつながります。
なぜ有効かというと
- 第一に多くの入試問題では「対角線の長さ」が直接与えられるからです。
- 第二に、ピタゴラスの定理(直角三角形の辺の関係)を基に導かれており、理屈を押さえることで忘れにくい仕組みになっています。
- さらに、正方形はひし形の一種であるため、対角線を使う発想が他の図形問題にも応用できる点が強みです。
対角線が10cmの正方形の場合、公式に当てはめると 10² ÷ 2 = 100 ÷ 2 = 50㎠ となります。
シンプルな手順ですが、受験生にとって「自分でもできた」という感覚が大きな自信につながります。私の教室でも、この例題で理解が一気に深まったという声を多く聞きました。
まとめると、対角線からの面積計算は効率的で理解しやすい方法です。
演習を重ねることで確実に身につけられますので、関連記事「正方形とひし形の関係」も参考にして、理解をさらに広げていきましょう。
正方形とひし形の関係
正方形とひし形の関係を理解すると、図形問題への応用力が大きく広がります。
結論から言えば、正方形はひし形の特別な形であり、面積公式を共通して使えるため、解法がシンプルになります。
特に中学受験の算数では、対角線を活用した面積の計算が頻出するので、大きな武器になります。
正方形を、45度回転します。元の正方形をひし形ととらえる事ができます。
ひし形の面積(正方形の面積)を求めるにはひし形の面積の公式を使います。

ひし形の面積は対角線×対角線÷2ですね。
正方形とひし形の面積は同じです。
従いまして正方形の面積は正方形の
なぜこの関係が重要かというと、
- 第一にひし形の面積公式「対角線×対角線÷2」を正方形にもそのまま適用できるからです。
- 第二に、正方形は「四辺が等しい」「角がすべて直角」という条件を満たしたひし形であり、性質を知っておくと図形分類の理解も深まります。
- さらに、複雑な図形を分解するときに「これはひし形として考えられる」と気づく力が養われます。
具体的には、以下のような学習効果があります。
- ひし形の面積公式を正方形にそのまま使えること
- 正方形がひし形の一種であることを理解できること
- 図形の性質の共通点と違いを整理できること以下で詳しく解説します。
まとめると、正方形とひし形の関係を押さえることは単なる知識ではなく、図形問題全般の応用力につながります。関連記事「ひし形の面積公式」も合わせて読むと理解が一層深まるでしょう。
ここで、正方形とひし形がどのような関係があるのかを調べてみましょう
| 正方形 | ひし形 | |
|---|---|---|
| 4つの辺の長さ | 同じ | 同じ |
| 対角線 | 対角線が互いに交差して直角に交わります(90度) | 対角線が互いに交差して直角に交わります(90度) |
| 内角 | すべての内角が90度 | 内閣は90度でない |
| 対角線の長さ | 等しい | 異なる |


形の特定の種類:
- 正方形: 正方形は特別なひし形の一種です。
すべての内角が90度であり、すべての辺の長さが等しいため、正方形はひし形の特別なケースといえます。
こうしたことから、正方形は特別なひし形の一種なので、今回のように正方形の面積を求める場合、正方形をひし形と捉えて、正方形の面積を求めるにはひし形の面積の公式を使います。
ひし型の面積の公式:
ひし型の面積=対角線✖︎対角線÷2 で求められる理由を確認します。
下図を見てください。

ひし形の面積は対角線①をたて、対角線②を横とする長方形の面積のちょうど半分になることがこの図からわかります。
📖 「小5・小6の年間スケジュール」を手元に置いて、計画的に受験準備を進めますか?
計画的に受験準備を進めるために必要な「年間スケジュール&チェックリスト」を
PDF形式で無料ダウンロードできます!
「今やるべきこと」が一目でわかると、迷わず受験準備を進められます✨
🎁 【特典内容】
✅ 小5・小6でやるべき年間スケジュール表
✅ 月ごとの学習目標&家庭でのサポートポイント
✅ 親子で進捗を管理できるチェックリスト
📩 今すぐメルマガ登録でプレゼント!
\今すぐ無料でダウンロード /
📩 メルマガ登録でスケジュールPDFを無料GET!
中学受験準備に役立つ「年間スケジュール&チェックリスト」PDFをプレゼント中です。
今の学習の進め方に迷っている方は、ぜひこの特典をご活用ください。
正方形の対角線で面積を求めるQ&A
正方形の対角線で面積を求める問題に関するよくある疑問は上記の通り。
ここからそれぞれの疑問について、1つずつ詳しく解説しています。
対角線から正方形の面積を求める方法はいつ習う?
正方形の面積を対角線を使って求める方法について、小学校のカリキュラムにおいては、通常4年生から6年生で習います。
この時期に、子どもたちは基本的な図形の性質や面積の計算方法を学び始めます。
正方形は見方を変えるとひし形と同じであり、ひし形の面積を求める公式である「対角線×対角線÷2」を利用することで、正方形の面積も簡単に計算できます。
正方形の対角線を使って面積を求める方法は、小学校高学年の算数の授業で習い、子どもたちはこの時期に基本的な幾何学の概念をしっかりと身につけます。
対角線を使った面積計算は、図形の理解を深めるうえで非常に役立つスキルです。
参考までに、文科省のHPで見てみましょう!
小学校・算数科・第5学年・平面図形の面積①
正方形の対角線の長さの求め方は?
正方形の対角線の長さを求める方法は、辺の長さを用いて簡単に計算できますが、この方法は、ピタゴラスの定理(ピタゴラスの定理は、直角三角形に関する有名な定理です)と呼ばれています。
この定理は、直角三角形の3つの辺の長さの関係を示しています)を利用するため、小学校の段階ではまだ導入されません。
ピタゴラスの定理は、三角形に関する特別なルールです。特に、直角三角形(ひとつの角が90度の三角形)に関するものです。
直角三角形の部品
- 直角:90度の角。
- 直角の両側の辺:この二つの辺は「直角の隣」にあります。
- 斜辺(しゃへん):直角の反対側にある一番長い辺です。
ピタゴラスの定理の内容
直角三角形の2つの直角の隣の辺の長さをそれぞれaaとbbとし、一番長い斜辺の長さをccとします。
このとき、ピタゴラスの定理はこう言っています:
aa✖️aa+bb✖️bb=cc✖️cc
これを簡単に言うと、直角三角形の「直角の両側の辺」の長さの2乗(それぞれの長さをかけたもの)を足すと、「斜辺の長さの2乗」になる、ということです。
中学数学のカリキュラムで、図形の基本的な性質を学ぶ際に、正方形や長方形の対角線に関する問題が出てきます。
一方、実際の試験では一辺の長さではなく「対角線の長さ」から面積を求める問題も多く出題されます。そのときに役立つのが「正方形の面積を対角線で求める公式」です。公式の意味を理解しておけば、応用問題にも強くなります。
👉 特に中学入試では、図形と割合や速さが組み合わさるケースも出ます。
応用力を養うには 図形と文章題が組み合わさる特殊算の問題 をあわせて確認しておくと安心です。
「中学受験の算数、どの参考書を選べばいい?」
迷ったらこちらの記事をチェック!お子さんにピッタリの算数参考書が見つかります。
➡ [中学受験おすすめ算数参考書まとめ]
まとめ:対角線の長さから正方形の面積を求めてみよう
今回のブログでは、正方形の面積を対角線の長さから求める方法について詳しく解説しました。対角線を使った計算方法を理解することで、数学の基礎をしっかりと固めることができます。
親子で一緒に学びながら、楽しく問題を解いていくことができます。豊富な図や例題を使って、正方形の面積計算のポイントを押さえましょう。
対角線を使った公式は「面積 = d² ÷ 2」とシンプルですが、ピタゴラスの定理(直角三角形の辺の関係)を理解して導けるかどうかが、入試本番での差を生みます。
単なる暗記で終わらせず「なぜその公式になるのか」を理解することが、応用問題で強みになります。
👉 図形全般のまとめはこちらの記事で整理しています → 中学受験でよく出る図形問題の解き方
これで、学校のテストや将来の勉強にも自信を持って取り組めるようになるはずです。
「このままでいいのかな」と不安になる夜に。
中学受験を“がんばる親”に向けた無料メールレッスン、はじめました。
➤ ChatGPTと対話しながら、気持ちを整える6日間。
📩 保護者の心に寄り添う、無料メール講座(全6回)を始めませんか?
ChatGPTと一緒に、イライラ・不安・親子のすれ違いを少しずつ整えていく6日間。
特典PDFもプレゼント中です。
下の画像(友だち登録で特典PDFプレゼント)をクリックして下さい!

「中学受験パスポート」参考記事
参考記事:【中学受験】時計算の裏ワザ!解き方をわかりやすく解説します
参考記事:旅人算の問題の解き方を徹底攻略!中学受験のための完全ガイド
参考記事:仕事算の問題・解き方を完全攻略!中学受験で使える公式も解説します
参考記事:食塩水の濃度の計算方法とは?公式の覚え方もわかりやすく解説します
参考記事:【中学受験】倍数算の解き方をわかりやすく解説します【簡単】
参考記事:通過算の問題の解き方をわかりやすく解説!基本問題から応用まで
参考記事:差集め算を完全攻略!裏ワザと解き方のコツで得点力を一気にアップ!
みなさんも、今日学んだことを使って、どんどん練習してみてくださいね!